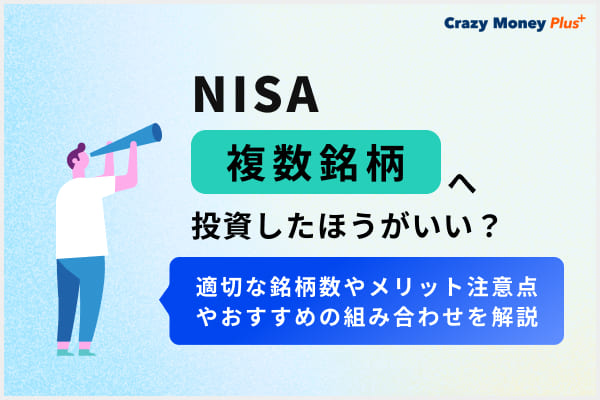2024年に開始された新NISAは、250本ほどの銘柄から自由に組み合わせて運用できます。
だからこそ、銘柄はいくつ買えばいいのか悩む方も少なくないでしょう。
本記事では、NISAで投資信託を複数銘柄を購入するメリットとデメリットを解説します。
また、おすすめの銘柄や組み合わせも解説するので、NISAで投資信託を始めてみたい方はぜひご覧ください。
- 複数銘柄へ投資すればリスクの調整や、オリジナルの資産構成での投資が可能に
- 異なる特徴を持つ資産同士や異なる国・地域の組み合わせが有効
- インデックスファンドとアクティブファンド、高リスクファンドと低リスクファンドの組み合わせも一案
\SBIの米国株式のインデックス投信へ投資するなら!/
- 【新NISA】投資信託、何本持つのが正解?つみたて投資枠・成長投資枠別に解説!
- NISAで複数銘柄へ投資するメリット
- NISAで複数銘柄へ投資するデメリット
- 複数銘柄へ投資するときの4つのポイント
- NISA初心者におすすめの投資信託
- NISAで複数銘柄投資するときのおすすめの組み合わせ
- NISA初心者は信託投資1本からでも十分
- まとめ|NISAで複数銘柄を保有すればリスク分散や自分に合った投資が可能に
【新NISA】投資信託、何本持つのが正解?つみたて投資枠・成長投資枠別に解説!
結論からお伝えすると、新NISAで購入する投資信託の適切な本数は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」、それぞれの枠の特性と、あなたの投資方針によって変わってきます。
金融庁が厳選した長期の積立・分散投資に適した投資信託が対象です。これらの多くは、1本でも十分に国際分散されています。そのため、基本的には1本に絞ってもOK!多くても2~3本程度で、管理のしやすさも考慮するのがおすすめです。
「成長投資枠」なら…
投資信託だけでなく、個別株やETFなど幅広い商品に投資できます。そのため、つみたて投資枠のファンドを補完する形で別の投資信託を数銘柄組み合わせたり、個別株と組み合わせたりと、より自由な設計が可能です。ただし、こちらも初心者の方は、まずは少数の分かりやすい投資信託から始めるのが良いでしょう。
「たくさん買えば買うほど分散されて安心!」というわけでもないのが、投資信託選びの奥深いところ。
銘柄数を増やしすぎると、かえって管理が煩雑になったり、同じような投資先に重複して投資してしまい、期待したほどの分散効果が得られなかったりすることもあるのです。
NISAで複数銘柄へ投資するメリット
NISAで複数の銘柄へ投資する主なメリットは、以下の3つです。
1.投資スタイルに合わせてリスク・リターンが向上する
複数銘柄を組み合わせることにより、自分の投資スタイルに合わせてリスク・リターンを調整できます。
基本的に金融商品は、リターンとリスクが比例関係にあるため、ハイリターン銘柄はハイリスクな傾向です。「ローリスク・ハイリターン」という夢のような商品は存在しません。
既存銘柄で自分が理想とするリスクとリターンのバランスの銘柄が見つからない場合は、「高リスクと低リスクのファンドを組み合わせる」など、複数銘柄を購入することで、希望に近しいリスクとリターンのポートフォリオの実現が期待できます。
また、値動きの特徴が異なる銘柄をうまく組み合わせれば、リスクを分散した投資が実現できるでしょう。
《例えば》
つみたて投資枠で全世界株式インデックスファンド1本に投資しているけれど、「もう少し積極的にリターンを狙いたいな」と感じたとします。
この場合、成長投資枠で、より高い成長が期待できる(ただしリスクも高い)新興国株式ファンドや、特定のテーマ(例:AI、半導体など)に特化したETFを少しだけ加えることで、ポートフォリオ全体のリターン向上を目指すことができます。
逆に、「もう少しリスクを抑えたい」という場合は、成長投資枠で債券ファンドやバランスファンドの比率を高める、といった調整も可能です。
2.投資先.オリジナルで組み合わせられる
複数銘柄を組み合わせれば、自分にあったオリジナルの資産構成を形成できます。
例えば「世界中の株に投資したいけど、よく知る日本企業に多めに投資したい」と考えている場合は、以下のような組み合わせを検討するのが有効です。
- 世界の株式へ投資するインデックスファンド
- 日経平均のインデックスファンド、もしくは日本の個別株
必ずしも市場指数に連動するインデックスファンドか、指数を上回るリターンを狙えるアクティブファンドの二択にする必要はありません。
また、インデックスファンドとアクティブファンドを好みの比率で組み合わせることもできます。
例えば、REITと株式といったような投資信託1本では見られない資産の組み合わせも可能です。
1本だけで自分の思い描く資産の組み合わせが実現できない場合は、複数銘柄を組み合わせて理想のポートフォリオを形成するのがおすすめです。
3.リスク分散効果が高まる
特徴の異なる銘柄を組み合わせることで、リスク分散効果を高められる場合があります。大きな損失リスクを抑制して、より安定した長期運用が可能です。
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の格言がありますが、これは異なる値動きをする複数の投資先に資産を分けて投資することで、全体のリスクを抑えるという「分散投資」の考え方を表しています。
NISAで複数銘柄に投資する大きなメリットの一つが、このリスク分散効果を自分なりに高められる点です。
典型的な例として、株と債券は次のように特徴が異なるため、組み合わせるとリスク分散効果が期待できます。
| 株 | 債券 | |
|---|---|---|
| リスク | 相対的に高い | 相対的に低い |
| 景気拡大時 | リターン向上が期待できる | リターン低下・損失リスクが高まる |
| 景気収縮時 | リターン低下・損失リスクが高まる | リターン向上が期待できる |
例えば景気収縮時には、株で損失が出ても債券が補って投資資産全体の損失を抑えられる場合があります。
このように値動きの特徴が異なる資産をうまく組み合わせると、損失リスクが低減し長期でより安定した運用が可能となります。
分散投資について詳しく解説した記事もあるのでぜひ読んでみてください。
> 分散投資は意味がない?株高の今だからこそ資産を守ることも考えよう
NISAで複数銘柄へ投資するデメリット
一方、NISAで複数の銘柄へ投資するデメリットは、銘柄の投資対象地域が一部被るような組み合わせで分散効果が下がったり、それを見極める商品選びや管理が大変になるという点です。
主なデメリットとして、以下の2つを具体的に解説します。
1.分散効果が薄まる可能性がある
国内株式と新興国株式、米国株式、欧州株式といった異なる地域の組み合わせはリスク分散に効果的ですが、以下のような対象地域が被るような組み合わせでは、分散効果が低下してしまいます。
- 全世界株式+日本株式
- 全世界株式+先進国株式
- 全世界株式+新興国株式
- 先進国株式+米国株式
全世界株式は、国内株式や先進国株式、新興国株式を含むため、どの銘柄を組み合わせても同じような運用成績となってしまいます。
また、先進国株式には米国株式が含まれるため、この組み合わせも分散効果が低いといえます。
2.管理が複雑になる
複数の銘柄を組み合わせれば、管理も複雑になります。
例えば、米国株式の銘柄と新興国の銘柄に投資している場合、両方の値動きを追いかける必要があります。
情報量が多くなり、自分が何に投資しているのかわかりづらく、どれくらい資産を持っているのか把握しづらくなるでしょう。
また、資産配分が時間の経過とともに変化し、その都度バランスを整える場合では、その運用自体が煩雑なものになってしまいます。
複数銘柄へ投資するときの4つのポイント
NISAの組み合わせを考えるときには、次のようなアイデアがあります。
この4つのなかから、自分が実践しやすい方法で組み合わせる銘柄を検討してみてください。
1.投資先の資産の違いを意識して組み合わせる
NISAで複数の銘柄に投資する際、まず考えたいのが「何に投資するか(資産クラス)」です。
主な資産クラスには、株式、債券、REIT(不動産投資信託)などがあり、それぞれ期待できるリターンやリスクの大きさが異なります。一般的にはそれぞれ下記の通りです。
- 株式:高いリターンが期待できるが、値動きも大きい。
- 債券:リターンは株式ほど高くないが、値動きが比較的安定している。
- REIT:株式と債券の中間的なリスク・リターン特性を持つとされる。
これらの値動きの異なる(専門的には「相関性が低い」と言います)資産クラスを組み合わせることで、どれか一つの資産が大きく値下がりした際に、他の資産でカバーし、ポートフォリオ全体の値動きを安定させる効果が期待できます。
【新NISAでの活用ポイント】
| つみたて投資枠 | 主に株式に投資するインデックスファンドが対象です。もし、つみたて投資枠で株式100%のファンドを選んでいるなら、成長投資枠で異なる資産クラスのファンドを組み合わせることで、より効果的なリスク分散が期待できます。 |
| 成長投資枠の活用 | 成長投資枠で、債券ファンドやREITファンド、あるいは複数の資産にバランス良く投資するバランスファンドを組み合わせることで、よりきめ細かなリスク分散が可能です。もちろん、成長投資枠で個別株を選び、投資信託と組み合わせるという考え方もあります。 |
なぜ異なる資産を組み合わせるとリスクが抑えられるの?
例えば、経済が不況になると一般的に株価は下落しやすいですが、安全資産とされる国債などの債券は逆に買われる(価格が上昇する)傾向が見られることがあります。
このように、一方が不調な時に他方が好調(または影響が少ない)という関係性を持つ資産を組み合わせることで、全体の資産価値の大きな目減りを防ぎやすくなるのです。
2.投資先の「国・地域」を戦略的に組み合わせて分散効果アップ!
投資信託を選ぶ際、どの「国・地域」に投資するかも重要なポイントです。
NISAで複数の銘柄を組み合わせることで、特定の国や地域に偏らず、よりグローバルな視点でリスクを分散したり、あるいは特定の地域の成長性を重点的に取り込んだりといった、自分なりの地域別ポートフォリオを構築できます。
そもそも、なぜ地域を分散することが重要なのでしょうか?
それは、各国の経済状況や市場の動向は、常に同じように動くわけではないからです。ある国が好調でも、別の国は不調なこともあります。
複数の異なる国や地域に投資を分散することで、特定の国が不景気になった場合の影響を和らげ、ポートフォリオ全体の値動きを安定させる効果が期待できます。
注意点:「全世界株式」との重複に気をつける
複数の地域別ファンドを組み合わせる際に特に注意したいのが、投資対象の「重複」です。
例えば、「全世界株式ファンド」は日本を含む先進国や新興国の株式に広く投資しており、その多くは米国株が大きな割合を占めています。ここに、さらに「先進国株式ファンド」や「米国株式(S&P500など)ファンド」を加えると、実質的に米国株への投資比率が意図せず高まり、分散効果が薄れる可能性があります。
より効果的な地域分散の組み合わせとしては、例えば、
- 「S&P500連動インデックスファンド」+「新興国株式インデックスファンド」:米国市場の成長を主軸に、新興国の成長も取り込む。
- 「先進国株式インデックスファンド(日本を除く)」+「日本株式インデックスファンド」:先進国中心の安定成長と、なじみのある日本市場への投資を両立。
あるいは、より細かく地域配分をコントロールしたい場合、「全世界株式ファンド」を選ばずに、「先進国株式」「新興国株式」「日本株式」の各ファンドを、自分の戦略に合わせて成長投資枠で個別に組み合わせる方法もあります。ただし、管理の手間は増える点に注意しましょう。
3.インデックス・アクティブファンドを組み合わせる
複数銘柄を組み合わせることで、インデックスファンドとアクティブファンドを組み合わせることもひとつの方法です。
投資信託は、大別すると市場指数に連動する「インデックスファンド」と市場指数を上回ることを目指す「アクティブファンド」に分けられます。
単一銘柄への投資では、事実上インデックスファンドとアクティブファンドのいずれかを選択しなければなりません。
一方、複数銘柄の投資信託を組み合わせれば、インデックスファンドとアクティブファンドの両方の特性を取り込むことが可能です。
例えば「インデックス投資を主体としつつも情報を入手しやすい日本だけアクティブ投資にチャレンジする」といった戦略も考えられます。
複数銘柄の組み合わせにより、さまざまな投資戦略の投資信託を取り入れることが可能になります。
4.低リスクファンドを取り入れてリスクを調整する
低リスクファンドを取り入れて、リスクを抑える方法も有効です。NISAの人気銘柄には、株式へ投資する投資信託が多く見られます。
過去の実績に基づくと、長期で見れば魅力的なリターンが期待できます。
しかし経済ショックの時期には、大幅な下落を見せる場合もあり「株式ではリスクが高すぎる」と考える方もいるでしょう。
資産の一部を債券へ投資する投資信託など低リスクファンドへ投資すると、損失リスクの抑制が期待できます。
複数銘柄を組み合わせることで、安心して長期で保有し続けられる資産構成が実現します。
2025年6月時点での、つみたて投資枠の対象銘柄には債券のみに投資する投資信託がありませんが、成長投資枠には複数銘柄が対象となっています。
成長投資枠もうまく活用して、投資銘柄の組み合わせを検討しましょう。
NISA初心者におすすめの投資信託
投資信託の組み合わせを考える前に、まずは初心者におすすめの投資信託を紹介します。
いきなり個別株やREITで組み合わせを考えるのは難易度が高いので、おすすめ銘柄を軸に複数銘柄の組み合わせを検討してみましょう。
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
SBI・V・全米株式インデックス・ファンドファンドは、アメリカの株式市場全体の値動きを示す代表的な指数である「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に連動するように運用されています。
アメリカの大型株から小型株まで、ほぼ全ての銘柄に幅広く投資することで、アメリカ経済全体の成長を取り込むことを目指します。
SBI・V・全米株式インデックス・ファンドのメリット
アメリカ経済の成長に期待できること、約4,000銘柄への分散投資によりリスクを抑えられること、運用コストが非常に低いことなどがメリットとして挙げられます。
長期的な視点で資産形成を考えている方におすすめです。
特定の企業に集中投資するのではなく、アメリカ市場全体に投資することで、個別企業のリスクを抑えながら成長を享受できる可能性が高いといえるでしょう。
\SBIの米国株式のインデックス投信へ投資するなら!/
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
世界中の株式に投資できるインデックスファンドで、先進国から新興国までを対象にしています。
1本の投資で約3,000銘柄に分散投資が可能で、リスクを抑えつつ世界経済の成長を享受できます。
信託報酬も業界最低水準で、コスト面でも初心者に優しい設計です。
どの地域に投資すべきか迷う方には、これ1本でバランスの良い投資が実現できるのでおすすめです。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)のメリット
世界経済の成長に期待できること、先進国と新興国を含む広範囲な分散投資でリスクを抑えられること、運用コストが低いことなどがメリットとして挙げられます。
世界経済の成長にまるごと投資したいという方におすすめです。
これ一本で世界中の株式に投資できるため、手軽に国際分散投資を始められます。
\eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)へ投資するなら!/
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
株式・債券・REITを含む8つの資産に均等に投資するバランス型ファンドです。
以下の8カテゴリーの資産に均等投資(すなわち1資産カテゴリーあたり12.5%)します。
- 1. 国内株式
- 2. 先進国株式
- 3. 新興国株式
- 4. 国内債券
- 5. 先進国債券
- 6. 新興国債券
- 7. 国内REIT
- 8. 先進国REIT
1つのファンドで多様な資産に分散投資ができるため、リスクを軽減しながら安定した運用を目指せます。
初心者でもわかりやすく、どの資産に投資するか迷わず始められるのが魅力です。
リスクを抑えた運用をしたい方や幅広く分散したい方にぴったりの選択肢です。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のメリット
分散投資の効果が非常に高く、リスクを抑えられること、様々な資産にまとめて投資できることなどがメリットとして挙げられます。
リスクを抑えながらバランスの取れた投資を行いたい方におすすめです。
これ一本で複数の資産に分散投資できるため、ポートフォリオ構築の手間を省けます。
\eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)へ投資するなら!/
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
このファンドは、日本の代表的な株価指数である日経平均株価に連動します。
日本の大手企業に分散投資でき、日本経済の成長を直接反映したリターンを期待できます。
信託報酬も低く、日本株に興味がある初心者におすすめです。
特に日本市場に馴染みがあり、国内投資を重視したい方には最適な選択肢です。
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)のメリット
日本経済の動向を把握しやすいこと、運用コストが低いことなどがメリットとして挙げられます。
日本の株式市場に特化して投資したい方におすすめです。
日経平均株価はニュースなどで頻繁に取り上げられるため、投資状況を把握しやすいという利点もあります。
\eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)へ投資するなら!/
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
米国の高配当株に投資するこのファンドは、配当収入を重視する方に最適です。
年4回分配金があり、安定的な収益を得られる可能性があります。
信託報酬も低水準で、米国市場の魅力を活かしながら収益を得たい初心者におすすめです。
配当金を得る喜びを感じながら投資を学ぶことができます。
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)のメリット
メリットは、安定した配当収入が期待できること、米国企業の成長と配当の両方を享受できる可能性があることなどが挙げられます。
インカムゲイン(配当収入)を重視する方におすすめです。
ただし、分配金は必ず支払われるわけではなく、また分配金を受け取ることで再投資の効果が薄れる場合もありますので、注意が必要です。
\SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドへ投資するなら!/
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
先進国の国債に分散投資するインデックスファンドで、リスクを抑えた運用が可能です。
株式投資が不安な方や、安定性を重視したい方に適しています。低い信託報酬でコストを抑えながら、世界主要国の安全性の高い債券に投資できる点が魅力です。
株式と組み合わせることでリスク分散効果も期待できます。
eMAXIS Slim 先進国債券インデックスのメリット
株式に比べて値動きが安定していること、ポートフォリオのリスク分散に役立つことなどがメリットとして挙げられます。
株式投資のリスクを抑えたい方や、安定的な運用を重視する方におすすめです。
債券は株式とは異なる値動きをするため、ポートフォリオに組み入れることでリスク分散効果が期待できます。
\eMAXIS Slim 先進国債券インデックスへ投資するなら!/
ひふみプラス
主に日本株に投資するアクティブファンドで、一部は海外株も対象としています。
市場の変動に応じて柔軟に運用し、下落時には現金比率を高めて損失を抑える仕組みが特徴です。
初心者でも手厚い運用が期待でき、日本企業に投資したい方や積極的な運用を目指す方におすすめです。
長期的な視野で資産を成長させたい方に最適です。
・ひふみプラスのメリット
積極的な運用による高いリターンが期待できること、運用会社による銘柄選定の恩恵を受けられることなどがメリットとして挙げられます。
市場平均を上回るリターンを積極的に狙いたい方におすすめです。
ただし、運用コストはインデックス型に比べて高くなる傾向があり、また市場平均を下回る可能性もあるため、注意が必要です。
ここまで紹介した投資信託の概要を以下にまとめました。
| 投資信託名 | 概要 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 米国株全体に低コストで分散投資。 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 世界中の株式へ幅広く分散投資。 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 株式・債券・REITを8資産に均等投資。 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日本の日経平均株価に連動投資。 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 米国高配当株に特化した投資信託。 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 先進国の国債に分散投資。 |
| ひふみプラス | 日本株中心の柔軟なアクティブ運用。 |
\信託報酬率に応じたポイント還元も受けられる!/
NISAで複数銘柄投資するときのおすすめの組み合わせ
今回紹介した投資信託も活用しながら、NISAで複数銘柄に投資するときのおすすめの組み合わせを4パターン紹介します。
1.米国株式+日本株式|米国と日本の主要企業に分散投資
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
- SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
- eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
1つ目は、米国株式と日本株式を組み合わせる例です。
▼この組み合わせの狙いと、どんな人におすすめ?
世界経済の中心である米国の力強い成長と、身近で情報収集しやすい日本企業の成長の両方を捉えることを目指す、ポピュラーで分かりやすい組み合わせです。
世界経済全体に投資する「全世界株式」も良い選択肢ですが、その中身の大部分は米国株が占めています。「もう少し日本株の比率を高めて、自国の経済を応援したい」「為替リスクを日本円資産で少し和らげたい」と考える方には、この組み合わせがぴったりです。
▼どんな市場環境で強みを発揮するか?
このポートフォリオは、米国経済が堅調で、かつ日本経済も安定または成長している局面で強みを発揮しやすいです。また、日米の景気サイクルが異なる場合、どちらか一方の市場が不調でも、もう一方が支えとなる可能性があります。
▼考えられるリスクや注意点
もちろん、米国と日本の両市場が同時に不調になる「世界同時株安」のような局面では、資産全体が下落するリスクがあります。また、米国株式は為替変動(円高)のリスクを直接受ける点も理解しておく必要があります。
▼【新NISA】つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
長期的な資産形成のコアとして、「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」などの低コストな米国株式ファンドをコツコツ積み立てる。
【成長投資枠】
つみたて投資枠を補完する形で、「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」などの日本株式ファンドを組み合わせる。あるいは、特定の日本の個別株(高配当株や応援したい優良企業など)を加え、自分だけのオリジナルポートフォリオを構築する。
2.世界株式+日本株式|世界と日本の主要企業に分散投資
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
「世界中の株式に分散投資しながら、日本株の比率を増やしたい」という方におすすめです。
▼この組み合わせの狙いと、どんな人におすすめ?
「世界経済の成長に乗りたいけど、やっぱり自国である日本の企業にもしっかり投資したい」という日本を応援する人におすすめなのが、この組み合わせです。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような全世界株式ファンドは、1本で世界中に分散投資できる非常に優れた商品ですが、その構成比率は各国の株式市場の規模(時価総額)に応じて決まっています。
そのため、2025年現在、日本株が占める割合は全体の5~6%程度しかありません。
「もっと日本株の比率を高めて、なじみのある日本企業の成長も資産形成に活かしたい」と考える方にとって、この組み合わせは自分好みに日本株への投資比率を調整できるという大きなメリットがあります。
▼どんな市場環境で強みを発揮するか?
このポートフォリオは、世界経済が全体的に成長しつつ、特に日本の株式市場が相対的に好調な局面で強みを発揮しやすいです。また、海外市場が不調な時に日本市場が底堅く推移すれば、リスクを和らげる効果も期待できます。
▼考えられるリスクや注意点
全世界株式ファンドと日本株式ファンドは、どちらも「株式」という同じ資産クラスです。そのため、世界的な金融ショックなどで株式市場全体が大きく下落する局面では、資産全体も同様に下落するリスクがあります。
▼【新NISA】つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
長期的な資産形成のコア(中核)として、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をコツコツ積み立てる。
【成長投資枠】
つみたて投資枠を補完する形で、「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」などの日本株式ファンドを組み合わせ、日本株比率を高める。あるいは、より積極的にリターンを狙いたい場合は、「ひふみプラス」のような日本株中心のアクティブファンドを成長投資枠で加えるという選択肢もあります。
3.世界株式+債券ファンド|債券を組み込みリスクを分散
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
▼この組み合わせの狙いと、どんな人におすすめ?
「世界経済の成長には期待したいけど、株式100%だと値動きの大きさが少し怖い…」という人におすすめなのが、この組み合わせです。
ポートフォリオに「債券」という異なる値動きをする資産を加えることで、全体の安定感を高めることを目指します。
一般的に、株式と債券は異なる値動きをする傾向があります。
例えば、景気後退局面で株価が下落する際に、安全資産とされる債券の価格は安定していたり、逆に上昇したりすることがあります。このように、お互いの弱点を補い合うことで、資産全体の値動きを緩やかにする効果が期待できます。
▼どんな市場環境で強みを発揮するか?
このポートフォリオは、株式市場が不安定な時期や下落局面で特に強みを発揮しやすいです。債券部分がクッションの役割を果たし、株式のみの場合に比べて資産の目減りを抑えてくれる可能性があります。
▼考えられるリスクや注意点
一方で、株式市場が非常に好調な局面では、債券部分のリターンが株式ほど高くないため、ポートフォリオ全体の収益率は株式100%の場合に比べて見劣りすることがあります。
また、金利が上昇する局面では債券価格は下落するリスクがある点も理解しておく必要があります。
▼「新NISA」つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
長期的な資産形成のコアとして、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」などの世界株式ファンドをコツコツ積み立てる。
【成長投資枠】
つみたて投資枠で購入した株式ファンドのリスクをコントロールするために、「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」などの債券ファンドを「成長投資枠」で組み合わせるのが基本的な使い方です。
4.インデックスファンド+アクティブファンド|着実なリターンを目指す方向け
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(インデックスファンド)
- ひふみプラス(アクティブファンド)
▼この組み合わせの狙いと、どんな人におすすめ?
「低コストで安定的に市場全体の成長についていきつつも、それだけでは物足りない。一部の資金ではプラスアルファのリターンを積極的に狙いたい」と考える方におすすめです。
これは「コア・サテライト戦略」と呼ばれる代表的な投資手法で、資産の大部分(コア)を低コストのインデックスファンドで手堅く運用し、残りの一部(サテライト)でアクティブファンドに挑戦する考え方です。これにより、ポートフォリオの「安定性」と「成長性の追求」の両立を目指します。
▼どんな市場環境で強みを発揮するか?
このポートフォリオは、株式市場全体が堅調な上昇相場で特に強みを発揮しやすいです。
コアのインデックスファンドで市場平均のリターンを着実に確保しながら、サテライトのアクティブファンドがそれを上回る成果を出せば、ポートフォリオ全体のリターンをさらに高めることが期待できます。
▼考えられるリスクや注意点
アクティブファンドは、専門家が銘柄を調査・選定するため、インデックスファンドに比べて信託報酬などの運用コストが一般的に高くなります。このコスト差を上回るリターンが得られるか、慎重な判断が必要です。
また、必ずしも市場平均を上回るとは限らないことも注意が必要です。
プロが運用するアクティブファンドでも、長期的に見てインデックスファンドの成績を下回ることは少なくありません。
実際、多くの調査データ(※)でも、大多数のアクティブファンドは対応する市場指数を下回る結果となっています。ファンド選びは非常に重要かつ困難です。(参考:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス「SPIVA® 日本スコアカード」)
▼「新NISA」つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
長期的な資産形成の土台として、低コストな「eMAXIS Slim 全世界株式」などのインデックスファンドを、この「つみたて投資枠」でコツコツと積み立てます。
【成長投資枠】
プラスアルファのリターンを狙う部分として、「ひふみプラス」のような、ご自身がその運用方針に共感できるアクティブファンドを「成長投資枠」で購入・積立します。
このように、枠の特性に合わせて役割分担をすることで、安定性と成長性を両立させたポートフォリオをNISAの非課税メリットを活かしながら構築できます。
NISA初心者は信託投資1本からでも十分
ここまで複数銘柄へ投資するときのポイントや考えた方を紹介してきました。
しかし初心者は、無理に複数銘柄へ投資する必要はありません。
投資信託は、1本でも分散効果が働くうえ、ファンドによっては1本で異なる特徴を持つ多様な資産へ投資が可能です。
投資信託は、投資家から集めた資金を多数の資産に分散投資する仕組みの金融商品です。
そのため1本に投資するだけでも分散効果が期待できます。
例えば、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、世界中の約3,000銘柄(2025年1月時点)の株式を組み入れており、個別株を購入するのと比べればはるかにリスクが分散されています。
「うまい銘柄の組み合わせが思いつかない」という方は、まず単一の投資信託を購入してみてはいかがでしょうか。
まとめ|NISAで複数銘柄を保有すればリスク分散や自分に合った投資が可能に
NISAで投資信託を複数銘柄保有すれば、リスク分散効果の向上や自分の理想に合った資産構成の構築が期待できます。
「株式だけではリスクが高すぎる」と感じる方は、適度なリスク水準にするために資産構成を調整可能です。
複数銘柄へ投資するときには、投資先の資産の違いや投資する国や地域の違いに着目して、銘柄の組み合わせを検討してください。