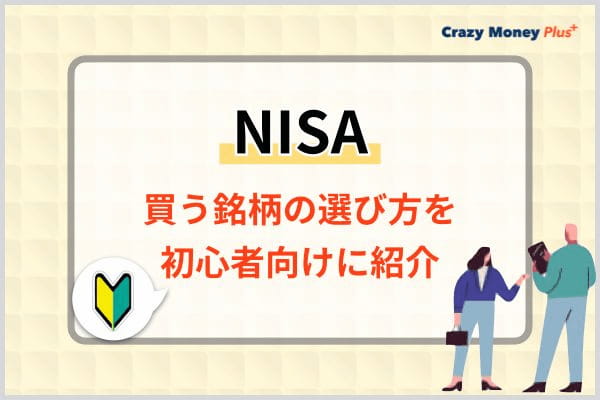NISAでの銘柄の選び方は投資信託と株で異なります。
投資信託は、つみたて投資枠対象銘柄からコストやリターンを比較して選びます。
日本株は初心者であれば日経平均採用銘柄から投資目的(値上がり益、配当、株主優待)に応じて選びましょう。
本記事では、NISAで買う銘柄の選び方やおすすめの銘柄を初心者向けに紹介します。
- NISAで投資信託を選ぶ場合、つみたて投資枠対象銘柄からコストやリターンを比較して選ぶ
- NISAで日本株を選ぶ場合は、投資目的(値上がり益、配当、株主優待)に応じて選ぶ
- NISAを始めるのにおすすめのネット証券は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券の5社
初心者向け投資信託の銘柄の選び方
NISAで買う投資信託は、以下の手順に従って選びましょう。
1.つみたて投資枠に絞る
まずは、つみたて投資枠対象銘柄に絞りましょう。
つみたて投資枠の対象銘柄は、保有コスト(信託報酬)が低い投資信託に限定されており購入手数料がかかりません。
投資信託のなかには、購入時の手数料が3.0%、保有コストが年率1.5%以上の銘柄もありますが、つみたて投資枠であれば高コスト銘柄を除外してくれます。
【NISAつみたて投資枠対象銘柄のコスト(信託報酬)上限】
| インデックスファンド | アクティブファンド | ||
|---|---|---|---|
| 投資対象が国内 | 投資対象が海外 | 投資対象が国内 | 投資対象が海外 |
| 年率0.55% | 年率0.825% | 年率1.1% | 年率1.65% |
コストと投資信託の利益は比例しないため、どの銘柄がいいのか判断できない人は、コストの低いつみたて投資枠対象銘柄から選びましょう。
2.リスク許容度に応じて絞り込む
リスク許容度に応じて絞り込むことは非常に重要です。
リスク許容度とは、投資によって損失を被る可能性をどれだけ受け入れられるかという個人の度合いを指します。
リスク許容度が高い人は、株式や新興国市場など、価格変動が大きいものの高いリターンが期待できる投資を選択肢に入れることができます。
一方、リスク許容度が低い人は、債券など、比較的安定した投資を選ぶべきでしょう。
投資信託を選ぶ場合は、運用方針や過去の運用実績などを確認し、自身のリスク許容度に合った商品を選びましょう。
日本株を選ぶ場合は、企業の財務状況や業績、市場での評価などを分析し、リスクとリターンのバランスを考慮して銘柄を選ぶことが大切です。
3.投資先が似た銘柄同士で比較して選ぶ
運用方針がほとんど変わらない銘柄が複数あるため、投資先が似た銘柄同士で比較して選びましょう。
リターンとコスト(信託報酬)で比べると、どの銘柄を選んだらいいのかがわかります。
直近のリターンが高い銘柄が将来のリターンも高いとは限りませんが、ほかの銘柄と比較してコストの高いものや、あまりにもリターンが低いものは避けましょう。
4.【複数買いたい人のみ】2銘柄以上選んで投資割合を決める
そもそも投資信託は、1銘柄で複数の銘柄や商品に分散投資しているため、分散投資目的で2銘柄以上選ぶ必要はありません。
どうしても複数買いたい人は、2銘柄以上選んで投資割合を決めましょう。
投資信託の複数保有や組み合わせについては以下の記事もぜひご覧ください。
投資信託を複数所有するメリット・デメリットとおすすめの組み合わせを解説!
年代別の投資信託のおすすめ銘柄
先ほど、リスク許容度に応じて銘柄を選ぶことをおすすめしました。
ここでは、一例として年代ごとにリスク許容度に応じたおすすめの銘柄を紹介します。
40代まで(リスク許容度高):株に100%投資する銘柄
40代までは、資産を守るよりも増やすことが大切です。
株価暴落時のリスクの高さを受け入れたうえで、株への投資割合が100%の投資信託を選びましょう。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、世界中の株式に分散投資できるインデックスファンドです。
このファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動しており、先進国と新興国の株式を含むため、リスクを分散しながら安定した成長を目指します。
信託報酬は業界最低水準の0.05775%以内で、長期投資においてコストを抑えられるのが大きな魅力です。
また、NISAやiDeCoを利用することで、非課税での資産形成が可能です。
全世界の経済成長を享受できるため、初心者から経験者まで幅広い投資家におすすめのファンドです。
これにより、将来的なリターンを期待しつつ、リスクを軽減した投資が実現できます。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、米国の代表的な株価指数であるS&P500に連動するインデックスファンドです。
このファンドは、米国の大型企業500社に投資することで、米国経済の成長を直接享受できます。
信託報酬は0.0814%と低コストで、長期的な資産形成に適しています。
過去の実績からも、S&P500は安定したリターンを提供しており、特に米国市場の成長を信じる投資家にとって魅力的な選択肢です。
また、NISA口座を利用することで、税金を気にせずに投資を行える点も大きな利点です。
これにより、資産を効率的に増やすことが期待できるため、特に米国株に興味がある方におすすめのファンドです。
50代(リスク許容度中):株に50%程度投資する銘柄
定年が近い50代は、売却して老後に備える場合も想定して40代までと比べてリスクを抑える必要があります。
40代までの運用を続けるのであれば、一部売却してリスク資産の割合を引き下げたほうがいいでしょう。
これから始める場合は、株への投資割合を50%程度にしてリスクを抑えている銘柄への投資がおすすめです。
50代の方には以下の投資信託がおすすめです。
- ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
- つみたて4資産均等バランス
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券の4つの資産に均等に投資するバランス型ファンドです。
各資産の投資比率は25%ずつで、リスクを分散しながら安定したリターンを目指します。
信託報酬は0.154%と低コストで、長期的な資産形成に適しています。
このファンドは、特に資産運用を始めたばかりの方や、リスクを抑えつつ安定した運用を希望する方におすすめです。
また、NISAを利用することで、非課税での資産形成が可能となり、資産寿命を延ばすことが期待できます。
自動的にリバランスが行われるため、手間をかけずに運用を続けられる点も魅力です。
つみたて4資産均等バランス
つみたて4資産均等バランスは、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に均等に投資するインデックス型のバランスファンドです。
このファンドは、各資産を25%ずつ配分し、安定した資産運用を実現します。信託報酬は0.242%と低く、長期的な投資に適しています。
特に、リスクを抑えつつ資産を増やしたい方に向いています。
60代以降(リスク許容度低):債券への投資割合が高い銘柄
本格的な老後が迫る60代以降は、万が一投資で大きな評価損を抱えると安いタイミングで売却せざるを得ない状況に陥る可能性があります。
株への投資割合が高い銘柄を引き続き保有する場合は、当面の生活費を現金で確保しましょう。
これから投資を始める人は、債券への投資割合が高い銘柄を選ぶのが無難です。
- DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
- 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)は、国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%という配分で、安定した運用を目指すバランス型ファンドです。
このファンドは、主に国内外の株式と債券に投資し、リスクを抑えつつリターンを追求します。
信託報酬は年率0.154%と低コストで、長期的な資産形成に適しています。
特に、安定した収益を求める投資家や、リタイア後の資産運用を考える方におすすめです。
また、確定拠出年金(iDeCo)向けに設計されているため、税制優遇を受けながら資産を増やすことが可能です。
リスクを抑えた運用を希望する方にとって、非常に魅力的な選択肢となります。
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%という配分で、債券を重視した安定型のバランスファンドです。
このファンドは、リスクを抑えつつ安定した成長を目指すため、特にリタイア世代や資産運用初心者に適しています。
信託報酬は年率0.242%と低く、コストを抑えた運用が可能です。
また、国内外の多様な資産に分散投資することで、リスクを軽減しながら安定したリターンを期待できます。
長期的な資産形成を考える方にとって、非常に有用な選択肢となるでしょう。
日本株の銘柄の選び方
NISAで個別企業の株を買う場合、はじめは情報量が多く、わかりやすい日本株から投資してみましょう。
株を買う場合は、各企業の業績(決算資料)をある程度確認したうえで買う必要があります。
主要な米国株など国内の投資家に人気のある海外株は、各証券会社が日本語で情報を提供していますが、日本株と比べて不十分です。
英語が苦手な人は、企業の決算資料などを自分の目で見て確認できる日本株を選んだほうがいいでしょう。
1. 日経平均採用銘柄に絞る
はじめて日本株に投資する場合は、できる限り日経平均採用銘柄に絞りましょう。
日本株は、約4,000銘柄ありますが、日経平均採用銘柄であれば225銘柄まで絞り込めます。
ベンチャー株のほうが当たったときの利益は大きいものの、外した際の損失も大きい傾向があります。
株価の上昇率は控えめですが、知名度の高い銘柄が多く事業内容がイメージしやすいため、銘柄選定もしやすいでしょう。
2. 投資目的に応じて絞り込む
株に投資する際は、目的に応じて絞り込みましょう。
投資目的は、大きく分けて3つあります。
- 値上がり益
- 配当
- 株主優待
値上がり益を狙うなら、将来性の高い成長企業や市場トレンドに乗る企業が候補となります。
配当を重視するなら、安定した収益基盤を持つ成熟企業や高配当利回りの企業を選びましょう。
株主優待を目的にするなら、優待内容が魅力的な企業を選ぶのも一つの戦略です。
自身の投資目的を明確にし、企業の財務状況や業績、市場動向などを分析することで、目的に合った銘柄を選ぶことができます。
3. 投資金額に応じて選ぶ
株は、投資信託とは異なり株価以上の金額がないと買えないため、投資金額に応じて選びましょう。
また、株主優待は、保有株数100株未満ではもらえない銘柄が多い傾向です。
特に優待目的で株を買う場合は、100株保有できる金額がいくらなのかを確認しましょう。
SBI証券をはじめとした大手ネット証券であれば手数料はかからないため「株価×100」で必要金額を計算できます。
\日本株の手数料無料/
投資目的別おすすめの日本株
先ほど、投資の目的別で株を選ぶことをおすすめしました。
ここでは、「値上がり益」「配当」「株主優待」の3つの目的別で、おすすめ日本株を紹介します。
1. 値上がり益が目的の場合
値上がり益狙いで日経平均採用銘柄から選ぶ場合、すでに大きく株価が上がってトレンドが過ぎつつある半導体などの銘柄は、短期投資を除いて避けましょう。
- サイバーエージェント<4751>
- 楽天グループ<4755>
サイバーエージェント<4751>
サイバーエージェント<4751>は、インターネット広告事業を基盤とし、メディア事業やゲーム事業など多角的な事業展開を行っています。
特に「AbemaTV」などのメディア事業や、人気ゲームコンテンツの開発・運営において強みを持っています。
『ウマ娘』の大ヒットしましたが、最近はブームが落ち着いたことにより収益が減少し、株価が低迷していました。
2024年は、新規タイトルのヒットによりゲーム事業の収益が回復し、大きく赤字を出していたABEMA関連事業の収益改善も進んでいます。
楽天グループ<4755>
楽天グループは<4755>、1997年に設立された日本のテクノロジー企業で、eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツなど多様なサービスを提供しています。
楽天市場を中心に、金融サービスや通信事業、スポーツ関連事業などを展開し、国内外で広範な顧客基盤を持っています。
特に、楽天ポイント制度は顧客のロイヤリティを高め、経済圏を形成する要因となっています。
楽天は、イノベーションを重視し、持続可能な成長を目指しているため、長期的な投資先として非常に魅力的です。
\日本株の手数料無料/
2. 配当が目的の場合
配当狙いで選ぶ場合は、配当利回りが高い銘柄に飛びつかないようにしましょう。
配当利回り(%)は、「1株あたりの年間配当金÷1株あたりの株価×100」で算出されます。
配当利回りが高い銘柄は、配当金が多いのではなく株価が安い可能性があることも忘れてはいけません。
配当利回りが高いのにもかかわらず株価が安い銘柄は「配当利回りの高さでしか投資家に魅力を訴求できない企業」という見方もできるでしょう。
目安としては、配当利回りが3~4%程度の銘柄が無難です。
配当が目的の場合のおすすめの銘柄は以下になります。
- ソフトバンク<9434>:予想配当利回り4.51%
- アステラス製薬<4503>:予想配当利回り4.28%
ソフトバンク<9434>
ソフトバンクは、日本を代表する通信事業者であり、モバイルサービス、インターネット接続、クラウドサービスなど多岐にわたる事業を展開しています。
特に、PayPayやLINEなどのデジタルサービスを通じて、幅広い顧客基盤を持つことが強みです。
さらに、株主優待としてPayPayポイントがもらえる制度も導入されており、長期保有を促進する施策が整っています。
これらの要素から、ソフトバンクは配当目的の株として非常におすすめです。
アステラス製薬<4503>
アステラス製薬は、医療用医薬品を中心に事業を展開するグローバルな製薬企業で、特にがん治療薬や泌尿器系の薬剤に強みを持っています。
アステラスは、安定した収益基盤を持ち、過去13期連続での増配を実現しており、配当の持続可能性が高いと評価されています。
企業の成長戦略として、研究開発への投資を重視しており、今後の新薬開発による収益増加が期待されます。
また、医薬品市場は景気に左右されにくく、安定した需要が見込まれるため、リスクが低い投資先としても魅力的です。
これらの理由から、アステラス製薬は配当目的の株として非常におすすめです。
安定的に配当をもらいたい場合は、できる限り景気に左右されづらい業種の銘柄を選びましょう。
\日本株の手数料無料/
3. 株主優待が目的の場合
株主優待は、日経平均採用銘柄以外で人気のある銘柄を選ぶことも選択肢の一つです。
ほかにも自分が使うサービスが優待でもらえる銘柄であれば選んでもいいでしょう。
ただし、優待には、改悪や廃止となるリスクがあり、永続するものではありません。
制度が変更されるリスクを承知したうえで購入しましょう。
株主優待が目的の場合におすすめの銘柄は以下になります。
- 吉野家ホールディングス<9861>
- すかいらーくホールディングス<3197>
吉野家ホールディングス<9861>
吉野家ホールディングスは、日本を代表する牛丼チェーン「吉野家」を中心に、うどん店「はなまる」や寿司店「京樽」など多様な飲食ブランドを展開しています。
株主優待として、100株以上保有する株主には、年2回、500円分の優待券が贈呈され、合計で2,000円相当の食事券を受け取ることができます。
これにより、外食をお得に楽しむことができるため、優待目的の投資家にとって魅力的です。
また、吉野家は全国に多くの店舗を持ち、利便性が高いのもポイントです。
さらに、安定した業績を背景に、優待の継続性が期待できるため、長期保有にも適した銘柄といえます。
すかいらーくホールディングス<3197>
すかいらーくホールディングスは、ファミリーレストラン「ガスト」をはじめ、バーミヤンや夢庵など、20以上のブランドを展開する大手外食企業です。
株主優待として、100株以上保有する株主には、年2回、2,000円相当の食事割引カードが贈呈されます。
300株以上では、5,000円相当、500株以上では8,000円相当と、保有株数に応じて優待内容が充実しています。
全国に約3,000店舗を展開しており、利用しやすさも魅力です。
さらに、優待券は500円単位で利用でき、アプリの割引クーポンとの併用も可能です。
安定した業績と高い優待利回りから、すかいらーくホールディングスは株主優待を目的とした投資家にとって非常におすすめの銘柄です。
\日本株の手数料無料/
NISAをはじめるのにおすすめのネット証券5選
ここではNISAをはじめるのにおすすめのネット証券を紹介します。
ネット証券は、手数料が安く、取引ツールや情報が充実しており、時間や場所を選ばずに取引できる点が大きなメリットです。
また、ネット証券は投資情報や企業分析ツールが充実しており、情報収集や分析がしやすい環境が整っています。
初心者はネット証券でNISAをはじめるのがいいでしょう。
初心者におすすめのネット証券は以下の5社になります。
SBI証券

画像引用:SBI証券
SBI証券は、三井住友カードでのクレカ積立やVポイント(またはPontaポイント)によるポイント投資に対応している業界最大手のネット証券です。
三井住友カードの利用金額が年間10万円以上であれば、クレカ積立で0.5%以上のVポイントが還元されます。
三井住友カードやVポイントをよく利用する人は、SBI証券を選びましょう。
SBI証券について詳しく知りたい人はこちら
SBI証券で口座開設するメリットを紹介
【SBI証券の概要】
| 取扱銘柄数 | ||
|---|---|---|
| 投資信託 | 日本株 | 米国株 |
| 2,552 | 全銘柄 | 5,403 |
| 各種サービス | ||
| クレカ積立 | ポイント投資 | 対応ポイント(※) |
| 三井住友カード | 日本株 投資信託 投信積立 |
Vポイント Pontaポイント dポイント JALのマイル PayPayポイント |
(2024年11月19日現在、CRAZY MONEY Plus編集部調べ)
\ニーズに合う商品が選びやすい/
楽天証券

画像引用:楽天証券
楽天証券は、楽天会員が利用すると様々な特典が受けられるネット証券です。
楽天カードでのクレカ積立に対応しており、積立金額に応じて0.5~2.0%の楽天ポイントがもらえます。
楽天銀行に口座があれば、証券口座との連携(マネーブリッジ)により楽天銀行の普通預金金利が最大0.28%(300万円まで)に上がります。さらに楽天ブラックカードでのカード利用の引落しがあると最大プラス年0.06%が加算され0.34%に上がります。(楽天プレミアムカードでのカード利用の引落しでプラス年0.02%、楽天ゴールドカードでのカード利用の引落しでプラス年0.01%)
楽天会員がユーザーの85%以上(2024年6月時点)を占めているため、今後も楽天グループのサービスを使い続けるなら楽天証券を選びましょう。
楽天証券について詳しく知りたい人はこちら
楽天証券でのNISAの始め方!おすすめ銘柄や他社からの変更方法
【楽天証券の概要】
| 取扱銘柄数 | ||
|---|---|---|
| 投資信託 | 日本株 | 米国株 |
| 2,574 | 東証・名証 | 5,125 |
| 各種サービス | ||
| クレカ積立 | ポイント投資 | 対応ポイント |
| 楽天カード | 日本株 米国株 投資信託 投信積立 |
楽天ポイント |
\楽天ポイントでNISAが可能/
マネックス証券

画像引用:マネックス証券
年会費無料カードに限れば、ほかの大手ネット証券より還元率が高く、年会費無料のdカードでも月5万円までなら1.1%のdポイントが還元されます。
月5万円を超えるとdカード GOLD、PLATINUMを除いてクレカ積立の還元率は下がってしまいますが、少額の投信積立ならマネックス証券がお得です。
マネックス証券について詳しく知りたい人はこちら
【マネックス証券で始めるつみたてNISA】特徴や評判、買い方を徹底解説
【マネックス証券の概要】
| 取扱銘柄数 | ||
|---|---|---|
| 投資信託 | 日本株 | 米国株 |
| 1,764 | 全銘柄 | 4,928 |
| 各種サービス | ||
| クレカ積立 | ポイント投資 | 対応ポイント |
| dカード | 投資信託 | dポイント |
\クレカ積立の還元率が1.1%!/
三菱UFJ eスマート証券
三菱UFJ eスマート証券はauユーザーにメリットが多い!おすすめの理由を解説
【三菱UFJ eスマート証券の概要】
| 取扱銘柄数 | ||
|---|---|---|
| 投資信託 | 日本株 | 米国株 |
| 1,837 | 全銘柄 | 1,956 |
| 各種サービス | ||
| クレカ積立 | ポイント投資 | 対応ポイント |
| au PAYカード | 投資信託 単元未満株 (プチ株) |
Pontaポイント |
\MUFGグループの信頼性と使いやすさが魅力/
松井証券

画像引用:松井証券
松井証券は、2025年5月よりJCBカードでのクレカ積立に対応するネット証券です。
2024年11月時点ではクレカ積立ができませんが、手厚い顧客サポートには定評があります。
どのネット証券でも不明点を電話などで問い合わせることはできますが、原則として銘柄相談は受け付けていません。
松井証券では「株の取引相談窓口」を設けており、日本株や米国株でどの銘柄に投資したらいいかわからない人向けに専門家がアドバイスをしてくれます。
株式投資がはじめての人は、松井証券を利用してみましょう。
松井証券について詳しく知りたい人はこちら
松井証券のメリットとデメリットは?松井証券が向いている人まで解説
【松井証券の概要】
| 取扱銘柄数 | ||
|---|---|---|
| 投資信託 | 日本株 | 米国株 |
| 1,883 | 全銘柄 | 4,568 |
| 各種サービス | ||
| クレカ積立(※) | ポイント投資 | 対応ポイント |
| JCBカード | 投資信託 投信積立 (3銘柄) |
松井証券ポイント |
(2024年11月19日現在、CRAZY MONEY Plus編集部調べ)
\サポートが手厚い!/
NISAで銘柄を選ぶ際に避けたほうがいいこと
NISAで銘柄を選ぶ際に避けたほうがいいことが2つあります。
1. SNSで話題になっている株に飛びつく
SNSで話題になっている株は、すでに株価がかなり上がっている可能性があります。
購入後に上がったとしても一気に株価が上がった銘柄は売るタイミングが難しいです。
ハイリスク・ハイリターンを求めるのであれば構いませんが、そうでないなら避けたほうがいいでしょう。
2. 投資銘柄を分散しすぎる
投資銘柄を分散しすぎると管理しきれません。
特に個別株を買う場合、各企業の決算発表で株価が大きく動くことがありますが、決算発表日は企業ごとにバラバラです。
慣れていないうちは、保有銘柄が多すぎると決算発表を見逃してしまい、株価暴落に巻き込まれることがあります。
初心者は、多くても3~5銘柄に絞ったほうが管理しやすいでしょう。
まとめ
2024年から始まった新NISAは、株や投資信託など幅広い商品に投資できます。
取扱商品が多いため、銘柄選びに迷うこともあるかもしれませんが、基本的な選び方を覚えておけば絞り込むことは可能です。
ここで紹介した「投資信託の選び方」や「株の選び方」を参考にして、NISAでの投資を始めてみてはいかがでしょうか。
まだNISA口座がない人は「金融機関の選び方」から自分にあう証券会社を選んで開設しましょう。
マイナンバー(通知)カードや運転免許証があれば、スマホで5~10分程度で申し込めて1~2日後には開設できます。