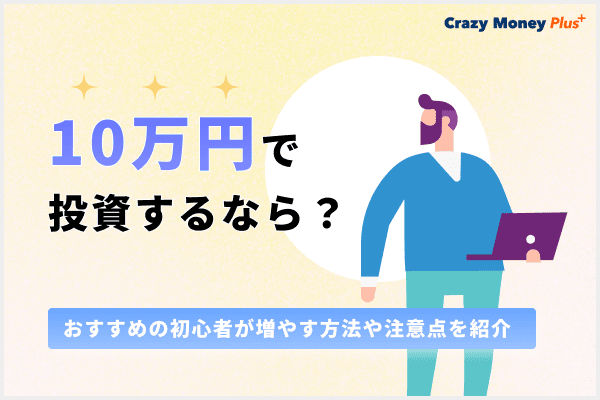投資初心者のなかには、以下のようなことで悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
- 10万円ではじめて投資したいがなにを買えばよいかわからない
- 投資を始めるのにはまとまった資金が必要だから10万円では足りないのでは?
- 投資資金に限りがあるため、効率的に運用したい
10万円もあればさまざまな資産への投資が可能です。この記事では、10万円から投資するときの初心者におすすめの投資方法について紹介します。
あわせて、はじめて投資するときの注意点も解説しているので、これから少額で投資にチャレンジしようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
\新NISA取引の売買手数料がすべて無料!/
- 10万円で投資するのにおすすめの投資先とは
- 1.投資信託|初心者でもチャレンジしやすい
- 2.日本株|配当収入や株主優待が魅力
- 3.米国株|長期で高成長が期待できる
- 4.ETF|リアルタイムで取引ができる投資信託
- 5.ロボアドバイザー|ほったらかし投資が可能
- 6.FX|リスクは高いがリターンも高い
- 7.クラウドファンディング/ソーシャルレンディング|少額で不動産投資が可能
- 8.個人向け国債|安全性の高い投資商品
- 10万円だからこそ知っておきたい!少額投資の魅力
- 10万円で投資するときの注意点4つ
- 10万円で投資するときの投資先の選び方4つ
- 10万円での投資に役立つ2つの制度
- まとめ|10万円で投資するなら少額投資できる投資先を選ぶ
10万円で投資するのにおすすめの投資先とは
10万円から始められる初心者におすすめの主な投資先は次の8つです。
それぞれの投資先は、リスクやリターン、短期〜長期投資に向いているなど、特長があります。
まずは「どんな人におすすめなのか」を最初にざっくりとご紹介します。ご自身の興味や目的に合わせて、気になる投資先を見つけてみてください。
| 投資対象 | こんな人におすすめ |
| 投資信託 | コツコツ時間をかけて分散・積立投資をしたい方、NISAを活用して非課税で運用したい方、専門家にお任せで手間なく運用したい初心者の方 |
| 日本株(単元未満株など) | 応援したい日本の有名企業や成長企業の株主になりたい方、少額から個別株投資を体験してみたい方 |
| 米国株(単元未満株など) | 世界経済をリードする米国企業の成長に期待したい方、AppleやGoogleなど身近なグローバル企業の株を持ちたい方 |
| ETF(上場投資信託) | 投資信託のように分散投資しつつ株式のようにリアルタイムで売買したい方、特定の指数やテーマに手軽に投資したい方 |
| ロボアドバイザー | 何に投資すればいいか全く分からないという方、完全に自動で資産運用をお任せしたい方 |
| FX(外国為替証拠金取引) | 少額の資金で大きなリターンを狙ってみたい方(※ハイリスク・ハイリターンを理解している方向け!)、為替の動きを予測するのが得意または興味がある方 |
| クラウドファンディング / ソーシャルレンディング | 特定の事業やプロジェクトを応援しながらリターンも期待したい方、新しい形の投資に挑戦したい方(※事業者リスクや仕組みの理解が重要!) |
| 個人向け国債 | とにかく元本割れリスクを避けたい方、安全性を最優先に預金よりは少しでも有利に運用したい方 |
1.投資信託|初心者でもチャレンジしやすい

投資信託は、2024年から始まった新NISAを活用できる主要な投資先の一つです。
ネット証券を活用すれば100円からの少額投資が可能で、リスク分散も効くため初心者でもチャレンジしやすい投資先といえます。
投資信託の特徴
投資信託は、不特定多数の投資家から集めた資金を運用会社などの投資の専門家が株式や債券などへ投資・運用してもらえる商品です。
銘柄ごとに投資先や投資資産のルールが定められているため、投資家はファンドの投資先をもとに投資銘柄を選びます。
株や債券などの投資資産や日本・米国・新興国といった投資する地域・国などを軸に自分に合った銘柄を購入しましょう。
1本買うだけで実質的にファンドの投資先となる多数の資産に投資できるため、投資家自身が具体的な投資先を選ばずとも分散投資しやすいのが特徴です。
投資信託のメリット
投資信託の主なメリットは、次の3つです。
【投資信託の主なメリット】
1. 新NISA(非課税投資枠)が活用できる
2. 専門家による運用とリスク分散
3. 100円程度の少額から投資できる
1. 新NISA制度の活用が可能
投資信託は、新NISAの「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の双方で購入可能であり、特に「つみたて投資枠」の対象商品の大部分は、長期・積立・分散投資に適格とされた投資信託が占めています。
新NISAの非課税投資枠を最大限に活用する上で、投資信託は重要な選択肢となります。
2. 専門家による運用とリスク分散
投資信託は、ファンドマネージャーという金融の専門家が投資判断と実際の運用を行います。
また、一つの投資信託に投資するだけで、その投資対象は数十から数千の多様な銘柄に分散されるため、特定銘柄の価格変動リスクが直接的に全体の投資成果に及ぼす影響を低減させる効果(リスク分散効果)が期待できます。
3. 100円程度の少額から投資できる
多くのオンライン証券会社(ネット証券)では、投資信託を100円単位の少額から購入できるサービスを提供しています。
これにより、まとまった資金がない場合でも、無理のない範囲で積立投資を開始しやすく、投資経験を積む機会を得やすく、例えば、10万円程度の資金でも、複数の異なる特性を持つ投資信託に分散して投資することも可能です。
投資信託のデメリット
投資信託の主なデメリットは以下の3つです。
【投資信託の主なデメリット】
1. 運用に手数料がかかる
2. 売買価格がわからない(ブラインド方式)まま取引する
3. 元本割れのリスクがある
1. 運用に手数料がかかる
投資信託の運用・管理にはコスト(手数料)が発生します。主なものとして、購入時にかかる「購入時手数料」(無料のファンドも多数存在する)、保有期間中に運用資産から日々差し引かれる「信託報酬(運用管理費用)」、そして解約時にかかる場合がある「信託財産留保額」があります。
これらのコスト、特に信託報酬は長期的なリターンに影響を与えるため、ファンド選択時の重要な比較検討項目となります。
2. 売買価格がわからない(ブラインド方式)まま取引する
投資信託の売買は、株式取引のように取引時間中に刻々と変動する市場価格を見て行うものではなく、原則として1日に1回算出される「基準価額」に基づいて行われれます。
注文発注時点では適用される基準価額が未確定であるため、投資家は正確な約定価格を知らずに取引を行うことになります(ブラインド方式)。このため、株式売買で見られる特定の価格を指定して売買する「指値注文」は行えません。
3. 元本割れのリスクがある
投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されている金融商品ではありません。市場環境や運用状況によっては、基準価額が投資元本を下回り、損失が生じる可能性があります。
一般的に、高いリターンが期待される投資信託は、それに伴い価格変動リスクも高くなる傾向があります(ハイリスク・ハイリターン)。
自身の資産状況やリスク許容度を十分に勘案し、投資対象ファンドの特性(投資対象、リスクの度合いなど)を理解した上で選択することが肝要です。
投資信託におすすめの証券会社はSBI証券
投資信託を売買する場合は、SBI証券がおすすめです。証券会社を選ぶ際に重要となるのは、下記の通り。
- 投資信託の取扱銘柄数
- 各種手数料
- システムの利便性やサービスの充実度
- ポイントプログラムなどの付加価値
SBI証券は、2024年9月25日時点で2,604銘柄もの投資信託を取引でき、新NISAのつみたて投資枠の対象銘柄も248銘柄と業界最多の水準です。
さらに最低投資金額は100円からと少額投資が可能で、積立頻度も毎日・毎週・毎月など柔軟に選択が可能です。クレジットカード決済で積立投資をするクレカ積立がお得なことも魅力の一つといえます。
たとえば、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託のクレカ積立をおこなうと、最大で積立額の3%のVポイントが付与されます。
| クレジットカード(代表例) | ポイント還元率 |
|---|---|
| 三井住友カード | 0.5% |
| 三井住友カード ゴールド | 1.0% |
| 三井住友カード プラチナ | 2.0% |
| 三井住友プラチナプリファード | 3.0% |
投資信託への投資が向いている人
上記の特徴を踏まえると、投資信託は特に以下の方におすすめです。
・多忙で個別銘柄の分析・選定に時間を割けない方
・少額から積立投資を始めたい方
・リスク分散を重視する方
・中長期的な視点で資産形成を目指す方
・新NISA制度を効果的に活用したい方
10万円をどう配分?一括投資 vs 積立投資 おすすめプランを解説!
10万円を投資信託で運用する際、「一括で買うべきか、毎月積み立てるか」は悩ましい点です。どちらにもメリットはありますが、特に投資初心者の方には、購入タイミングを分散でき、少額から無理なく始められる「積立投資」をおすすめします。
積立投資の大きなメリットは、「ドルコスト平均法」の効果が期待できること。これは、価格が高いときには少なく、安いときには多く買うことで、平均購入単価を抑え、高値掴みのリスクを軽減する手法です。
また、毎月コツコツ続けることで、投資のタイミングに悩むことなく、自然と投資習慣が身につきます。
10万円での積立プランとしては、例えば毎月5,000円や1万円など、無理のない金額で積立をスタートし、その原資として10万円を少しずつ充当していくのが良いでしょう。
NISAのつみたて投資枠を活用すれば、非課税で運用できるメリットも大きいです。この方法は、長期的な資産形成の第一歩として非常に適しています。
一方、一括投資は購入タイミングが良ければ大きなリターンも期待できますが、高値掴みのリスクもあり、初心者にはタイミング判断が難しい面があります。
最終的にはご自身の考え方やリスク許容度に合わせて選ぶことが大切ですが、10万円で投資を始めるなら、まずはリスクを抑えつつ経験を積める積立投資から検討してみてください。
2.日本株|配当収入や株主優待が魅力

株式投資は、株の値上がり益や配当収入、株主優待などを得ることが期待できます。
日本株であれば、日常生活で接点のあるなじみの企業も多く投資しやすいのが特徴です。
なお、新NISAの成長投資枠は、日本株へも投資できます。
日本株の特徴
株式とは、企業が出資金を募る目的で発行する証券のことです。日本株であれば、日本企業が発行した証券を指します。
株式を一定数以上保有していると、投資家は株式総会などで経営に参加ができるほか、配当の受益権が発生します。
単に「株」といった場合は、証券取引所で売買できる「上場株」と、そうではない「未上場株」に分かれます。個人投資家が売買できて投資しやすいのは上場株です。
日本株のメリット
日本株の主なメリットは、次の3つです。
【日本株の主なメリット】
1. 株価上昇の売却益のほか配当・株主優待が期待できる
2. なじみのある日本企業に投資できる
3. 単元未満株制度で少額投資が可能
1. 株価上昇の売却益のほか配当・株主優待が期待できる
株式投資から得られる収益の代表的なものに、購入した株式の価格が上昇した際に売却することで得られる「売却益(キャピタルゲイン)」があります。
例えば、1株1,000円で購入した株式が1,500円に値上がりした時点で売却すれば、差額の500円(手数料等を除く)が利益となります。
さらに、企業によっては、事業活動から得られた利益の一部を株主に対して分配する「配当金(インカムゲイン)」を、年に1回または2回程度受け取ることが可能です。
また、日本独自の制度として「株主優待」を実施している企業が多数存在します。株主優待制度では、企業が自社製品やサービス利用券、金券などを株主に提供するため、投資の経済的リターンに加え、実生活における便益も享受できる場合があります。
2.なじみのある企業に投資できる
日本国内で生活する中で、トヨタ自動車株式会社、ソニーグループ株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、任天堂株式会社など、製品やサービスを通じて日常的に接点のある企業は多数存在します。
これらの事業内容や経営状況について比較的情報を得やすい、なじみのある企業に投資できる点は、日本株式投資のメリットの一つといえるでしょう。投資対象企業の選定にあたり、自身の知識や関心に基づいて企業分析を行いやすく、投資後もその企業の活動や業績に関心を持ちやすいという側面があります。
3.単元未満株制度で少額投資が可能
通常、日本の証券取引所における株式取引は、100株を1単元として行われるため、株価によっては最低投資金額が高額になる場合があります(例:1株5,000円の銘柄であれば、最低50万円の資金が必要)。
しかしながら、近年では多くのネット証券会社(例:SBI証券の「S株」、楽天証券の「かぶミニ®」)が、1株から株式を購入できる「単元未満株」取引サービスを提供しています。
この制度を利用することにより、数千円から数万円程度の資金でも、著名な企業の株式を取得することが可能になります。
このため、投資初心者の方が少額から試行的に投資を始めたい場合や、限られた資金で複数の銘柄に分散投資を行いたい場合に有用な手段となります。
日本株のデメリット
日本株式投資にはメリットがある一方で、事前に認識しておくべき留意点(デメリット)も存在します。
【日本株の主なデメリット】
1. 株主優待は1単元(100株)以上持たないともらえない場合が多い
2. 株価は常に変動するため、リスクも高い
3. 投資先が倒産すると無価値化するおそれもある
1. 株主優待は1単元(100株)以上持たないともらえない場合が多い
日本株式投資の魅力の一つとされる株主優待ですが、全ての企業がこの制度を導入しているわけではありません。
また、株主優待を受けるための条件として、多くの企業が「1単元(通常100株)以上の株式を保有していること」を定めています。
したがって、単元未満株制度を利用して少額の株式を保有している場合、株主優待の対象外となるケースが一般的です。
特定の企業の株主優待を目的として投資を検討する際には、その企業の株主優待制度の適用条件(必要保有株式数、権利確定日など)を事前に綿密に確認する必要があります。
株価が1000円以下の銘柄は「低位株」とも呼ばれ、「規模が小さい」「事業のリスクが高い」などの理由で株価変動が大きいリスクの高い銘柄もあります。
2. 株価は常に変動するため、リスクも高い
株式の価格(株価)は、投資対象企業の業績や財務状況、金利や為替といったマクロ経済指標、国内外の政治情勢、市場全体の需給動向など、多岐にわたる要因の影響を受けて常に変動します。
このため、株式購入時の価格よりも株価が下落し、売却時に損失を計上する可能性は常に存在します。
特に、高い成長性が期待される一方で事業基盤が確立していない新興企業の株式や、外部環境の変化に敏感な特定の業種に属する企業の株式は、株価の変動幅が相対的に大きくなる(ボラティリティが高い)傾向が見られます。
いかなる銘柄に投資する場合においても、株価変動リスクは不可避であることを認識しておくことが重要です。
3. 投資先が倒産すると無価値化するおそれもある
確率は低いものの、投資対象とした企業が深刻な経営不振に陥り、最終的に経営破綻(倒産)に至るリスクも考慮しなければなりません。
企業が倒産し、その株式が証券取引所での取引資格を失う(上場廃止)場合、当該株式の資産価値は著しく減少し、多くの場合は実質的にゼロになる可能性があります。
このような事態を回避するための一つの策として、投資資金を一つの企業に集中させるのではなく、複数の異なる企業や業種に分散して投資する「分散投資」を心がけることが、リスク管理の観点から推奨されます。
また、投資判断に際しては、対象企業の財務健全性や収益性、将来性などを十分に調査・分析することも、リスク低減のために不可欠なプロセスです。
【10万円以内で購入できる実質利回りが高いおすすめ銘柄】
| コード | 会社名 | 株価 (円) | 最低投資額 (円) | 年間配当金 (円/単元) | 配当利回り (%) | 優待価値 (円/年) | 優待利回り (%) | 実質利回り (%) | 株主優待詳細 (100株保有基準) | 権利確定月 | 備考 (長期保有等) |
| 7602 | レダックス | 129 | 12,900 | 300 | 2.33 | 30,000 | 232.56 | 234.88 | 車購入・売却時利用券3万円相当 | 3月 | 利用条件あり |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 640 | 64,000 | 0 | 0 | 55,300 | 86.41 | 86.41 | 株式新聞Web版1年無料(52,800円相当)、XRP2,500円相当 | 3月 | |
| 4755 | 楽天グループ | 804 | 80,400 | 0 | 0 | 39,336 | 48.93 | 48.93 | 楽天モバイル音声+データ30GB/月 1年間無料 | 12月 | 要申込 |
| 2928 | RIZAPグループ | 204 | 20,400 | 0 | 0 | 9,834 | 48.21 | 48.21 | chocoZAP6ヶ月半額優待券 | 3月 | |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 234 | 23,400 | 50 | 0.21 | 3,500 | 14.96 | 15.17 | オンラインストア優待券3,500円相当 | 6月 | 3年以上保有で4,500円分 |
| 8908 | 毎日コムネット | 753 | 75,300 | 3,200 | 4.25 | 7,000 | 9.3 | 13.55 | ベネフィット・ステーション利用権(ダイジェストコース) | 5月 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 283 | 28,300 | 0 | 0 | 3,800 | 13.43 | 13.43 | カタログギフト3,800円相当、Club Off利用権 | 9月 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 155.9 | 15,590 | 530 | 3.4 | 1,500 | 9.62 | 13.02 | dポイント1,500ポイント | 3月 | 2年以上保有。5年以上で3,000ポイント |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 966 | 96,600 | 10,000 | 10.35 | N/A | 0 | 10.35 | ECサイト20%割引券等 | 3月 | 優待価値評価困難、配当利回り主体 |
| 5884 | クラダシ | 393 | 39,300 | 0 | 0 | 4,000 | 10.18 | 10.18 | 自社オンラインストアク ーポン4,000円相当 | 6月 | |
| 9434 | ソフトバンク | 223 | 22,300 | 860 | 3.86 | 1,000 | 4.48 | 8.34 | PayPayポイント1,000円相当 | 3月 | 1年以上保有 |
| 2722 | IKホールディングス | 382 | 38,200 | 800 | 2.09 | 2,000 | 5.24 | 7.33 | 自社製品(鰹昆亭の和風だし等)2,000円相当 | 5月 | 1年以上保有 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 488 | 48,800 | 0 | 0 | 3,000 | 6.15 | 6.15 | 優待食事券3,000円相当またはギフト | 8月 | |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 790 | 79,000 | 2,404 | 3.04 | 2,200 | 2.78 | 5.83 | 特選菓子2,200円相当、レストラン優待券3枚 | 4月 | 1年以上保有。優待券価値含まず |
| 8016 | オンワードホールディングス | 562 | 56,200 | 3,000 | 5.34 | N/A | 0 | 5.34 | ECサイト20%割引券 | 2月 | 優待価値評価困難(100株)、配当利回り主体 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 386 | 38,600 | 0 | 0 | 2,000 | 5.18 | 5.18 | QUOカード2,000円相当 | 5月 | 2025年5月限定の70周年記念優待 |
| 7196 | Casa | 810 | 81,000 | 3,200 | 3.95 | 1,000 | 1.23 | 5.18 | QUOカード1,000円相当 | 7月 | |
| 7277 | TBK | 284 | 28,400 | 800 | 2.82 | 500 | 1.76 | 4.58 | QUOカード500円相当 | 3月 | 1年以上保有 |
| 8508 | Jトラスト | 407 | 40,700 | 1,700 | 4.18 | N/A | 0 | 4.18 | クリニック等20%割引券 | 6月 | 優待価値評価困難、配当利回り主体 |
| 3645 | メディカルネット | 323 | 32,300 | 300 | 0.93 | 1,000 | 3.1 | 4.02 | QUOカード1,000円相当 | 5月 | 1年以上保有 |
実質利回りは、年間配当金に株主優待の金銭的価値を加えて、1単元(100株)の金額で割り、100をかけた数値で計算しています。
このように10万円以内でも魅力的な銘柄は多く存在するため、自身の生活スタイルに合わせて選択することで、金銭的リターンに加えて企業製品やサービスをお得に体験することが可能です。
10万円で買える有名企業株の一例(単元未満株の場合)
| 企業名(例) | 1株あたりの株価(目安) | 10万円で買える株数(目安) | どんな会社? |
| トヨタ自動車 | 2,626円 | 約38株 | 日本を代表する世界的な自動車メーカー |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,944円 | 約51株 | 日本最大の金融グループ |
| ソニーグループ | 3,685円 | 約27株 | エレクトロニクスからエンタメまで幅広く展開 |
| オリエンタルランド | 3,099円 | 約32株 | 東京ディズニーリゾート®を運営 |
| ファーストリテイリング | 48,940円 | 2株 | ユニクロやGUなどのアパレル事業を展開 |
この表からもわかるように、10万円の予算でも、1株数千円程度の株なら複数株、あるいは数百円の株ならかなりの株数を購入できる可能性があります。
例えば、10万円の予算で、
・トヨタ自動車の株を10株(約26,260円)
・NTTの株を200株(約30,000円)
・三菱UFJフィナンシャル・グループの株を15株(約29,160円)
といった形で、合計3社の株主になることも夢ではありません(別途手数料がかかります)。もちろん、1つの企業に集中して投資することも可能です。
このように単元未満株を利用すれば、手が届かないと思っていた有名企業の株にも少額から投資でき、その企業の成長を応援したり、経済ニュースをより身近に感じられたりするのが大きな魅力です。
日本株におすすめの3社を比較
10万円から単元未満株(1株単位)で日本株投資を始めるなら、手数料の安さと取扱銘柄の豊富さが証券会社選びの重要なポイントになります。
ここでは、初心者にも人気の主要ネット証券3社を比較してみましょう。
| 証券会社 | サービス名 | 売買手数料(税込) | 特徴 |
| マネックス証券 | ワン株® | 買付:無料
売却:約定代金の0.55%(最低52円) |
買付手数料が無料なので、コツコツ買い増していくのに向いています。 |
| SBI証券 | S株® | 買付・売却ともに無料(ゼロ革命対象 ※1) | 売買手数料が完全無料なので、コストを最も抑えられます。単元未満株でもリアルタイム取引が可能になるサービスも(※要申込)。 |
| 楽天証券 | かぶミニ® | 買付・売却ともに無料(※ただし、リアルタイム取引(寄付取引以外)ではスプレッド(取引コスト)あり) | 楽天ポイントでの購入も可能。リアルタイムで売買できるのが魅力ですが、その際はスプレッド(買値と売値の差)が実質的なコストになる点に注意が必要です。 |
※1:SBI証券の国内株式手数料無料(ゼロ革命)には、取引報告書等の電子交付設定などの適用条件があります。
「S株®」は売買手数料が完全無料なので、10万円の資金を有効に活用できます。コストを気にせず、様々な銘柄を試してみたい方に最適です。
\「S株®」なら日本株の手数料無料/
「ワン株®」は買付手数料が無料です。一度買ったら長期で保有し、リアルタイムの値動きを追わずにじっくり投資したいスタイルであれば、有力な選択肢となります。
\コツコツ買い増ししたいならマネックス証券/
「かぶミニ®」なら、市場が開いている時間帯にリアルタイムで売買できるのが大きな魅力です。ただし、スプレッドというコストがかかる点には注意。楽天ポイントを使って株を買いたい方にもおすすめです。
\リアルタイムで売買したいなら楽天証券/
日本株への投資が向いている人
日本株の投資が向いているのは、日本市場や企業の成長に関心があり、比較的リスク許容度が高い人です。
日本株は情報を日本語で収集しやすく、国内経済や政策の影響を理解しやすい点が魅力です。
また、配当金や株主優待を重視する人にも適しています。
短期的な値動きに対応できる人や、中長期で企業の成長を見込む人に適した選択肢です。
ただし、特定の企業や業界への集中投資はリスクが高いため、分散投資の工夫が必要です。
3.米国株|長期で高成長が期待できる

米国株も株式の一種で、企業が発行する株式に投資する点は日本株と変わりません。違いは、文字どおり米国証券取引所に上場している企業の株式を売買する点です。
米国株の特徴
米国株式は、グローバルな一流企業が集まる世界最大の市場であるニューヨーク証券取引所(NYSE)やAppleやMicrosoft、Amazon、エヌディビア、テスラなどハイテク企業が多いナスダック(NASDAQ)など高成長が期待できます。
基本的に株式は、米ドル建てで発行されていますが、証券会社が為替変換することで日本円から購入できる円貨決済に対応しているネット証券会社もあります。
米国株のメリット
米国株の主なメリットは、次の3つです。
【米国株の主なメリット】
1. 1株から売買できるため少額投資に適している
2. 長期で成長が進む市場に投資可能
3. 分配金が年4回受取れる
米国株は、1株単位で売買できるため、10万円の元手でも多くの銘柄が投資先の候補となります。
米国市場は、この30年間で株価が12倍に成長するなど、日本と比べて長期で高成長が期待できる市場です。
また米国株は、分配金が4回受け取れる銘柄が多い傾向のため、米ドルでの配当を重視する投資先としても適しています。
なお、新NISAの成長投資枠であれば米国株への投資も可能です。
米国株のデメリット
米国株の主なデメリットは、次の3つです。
【米国株の主なデメリット】
1. 企業情報が英語なので銘柄分析が難しい
2. 為替変動リスクがある
3. 為替手数料がかかる証券会社も
米国を本拠地とする企業が多いため、企業の事業説明や決算開示資料などは、ほとんどが英語です。
英語を読めなければ正確に銘柄分析をするのは難しいでしょう。
また、米ドルに交換して株を売買するため、為替リスクが発生します。
たとえば購入時の為替レートよりも円高になった場合は、米ドルベースでの株価は上昇していても円ベースでは為替差損が発生するケースもあるのです。
円から米ドルに交換する際は、多くの企業で為替手数料がかかります。
マネックス証券は、米国株の買付時に売買手数料はかかりませんが、売却時に米ドル→円に戻すと1米ドルあたり25銭の手数料がかかります。
また三菱UFJeスマート証券は、円→米ドルと米ドル→円それぞれに交換の都度20銭かかる仕組みです。
米国株におすすめの証券会社3社を比較!
| 証券会社 | 1株から購入 | 取引手数料(NISA口座) | 為替手数料(米ドル)の工夫 | 特徴(ツールなど) |
| 楽天証券 | 不可 | 無料 | 楽天銀行との連携「マネーブリッジ」で外貨普通預金金利優遇あり(※為替手数料自体が優遇されるわけではない点に注意) | ・PCツール「マーケットスピードII」は情報量が豊富
・楽天ポイントで購入可能 |
| SBI証券 | 可能(S株®) | 無料 | 住信SBIネット銀行との連携で、為替コストを1ドルあたり数銭レベルに大幅に抑えることが可能。 | ・PCツール「HYPER SBI 2」は国内株と共通で使いやすい
・多様なポイントで購入可能 |
| マネックス証券 | 可能(ワン株®) | 実質無料(キャッシュバック) | 買付時の為替手数料がキャンペーン等で無料(0銭)になることが多く、コストを抑えやすい。 | ・「銘柄スカウター米国株」はプロレベルの分析が無料でできる神ツール
・取扱銘柄数が業界トップクラス |
「S株®」で1株から手数料無料で始められ、住信SBIネット銀行との連携を使いこなせば為替コストを最も安く抑えられます。10万円という資金を最大限効率よく使いたい堅実派の方におすすめです。
\「S株®」なら米国株の手数料無料/
無料で使える分析ツール「銘柄スカウター」は非常に強力で、初心者から経験者まで銘柄選びの大きな武器になります。取扱銘柄数も圧倒的なので、有名企業だけでなく、将来の成長株を発掘したい方にも最適です。買付時の為替手数料無料キャンペーンも魅力的。
\銘柄分析をしっかりしたいならマネックス証券/
楽天ポイントを使いたい、国内株と同じツールで取引したいなら「楽天証券」
1株からの購入はできませんが、10万円の予算で数千円程度の米国株ETFなどを購入することは可能です。楽天ポイントを投資に回したい方や、高機能ツール「マーケットスピードII」を使い慣れている方には良い選択肢です。
\楽天ポイントを貯めたいなら楽天証券/
米国株への投資が向いている人
米国株への投資が向いているのは、世界最大の市場である米国の成長やグローバル企業の活躍に期待する人です。
長期的に高い成長を遂げてきた米国市場では、テクノロジーやヘルスケアなどの革新分野が豊富で、投資機会が多い点が魅力です。
ドル資産を保有することで通貨分散を図りたい人や、英語を使って情報収集ができる人にも適しています。
ただし、為替リスクや税制の違いを理解し、十分に調査を行うことが重要です。中長期的な資産形成を目指す人に特に向いています。
4.ETF|リアルタイムで取引ができる投資信託

ETFは、証券取引所が営業している時間帯にリアルタイムで売買できる投資信託です。
株を売買するように証券会社を介して発注すれば取引ができます。
ETFの特徴
ETFは、Exchange Traded Fundsの略で和訳すると「上場投資信託」と呼び、証券取引所に上場した投資信託のことをいいます。
日本の場合は、東京証券取引所に上場していますが、海外の証券取引所に上場した海外ETFもあり証券会社によっては取引可能です。
上場しているため、証券取引所が営業している時間帯はリアルタイムで売買ができます。
株のように指値(価格を指定)で売買することも可能です。
価格は、1口あたりで表現されていますが、最低購入単位は銘柄によって異なります。
1口で売買できる銘柄であれば、購入手数料を考慮しない場合、そのときの1口の金額が最低投資価格です。
ETFのメリット
ETFの主なメリットは、以下の3つです。
【ETFの主なメリット】
1. 投資信託なのにリアルタイムで取引できる
2. 世界中のさまざまな資産に分散投資ができる
3. 新NISAの成長投資枠がつかえる
ETFは、株と投資信託の特徴を合わせたような商品です。
投資信託は、多くの商品が1営業日に1度しか基準価額が変わらず、さらにブラインド方式を採用しているため、発注した後日にならなければ具体的な取引価格がわかりません。
ETFであれば実際に取引される価格を見ながら発注でき指値注文も可能です。
また、投資信託と同様に世界中のさまざまな資産に分散投資もできます。
ETFは、新NISAの成長投資枠で投資が可能です。
最大1,200万円(成長投資枠の限度額)までは非課税で取引できるため、効率よく資産運用ができます。
ETFのデメリット
ETFの主なデメリットは、次の3つです。
【ETFの主なデメリット】
1. 株や投資信託より最低投資金額が高い場合も
2. 投資期間中はコストがかかる
3. リスクが高い銘柄もある
ETFの最低投資口数は、銘柄によって異なります。
1口から投資できる銘柄でそのときの価格が最低投資金額となります。
そのため、銘柄および市場環境によって最低投資金額は異なり、おおむね数千円~数万円の投資金額が必要です。
10万円あれば購入可能ですが、投資信託がネット証券によっては100円程度で購入できることをふまえると、それよりは最低投資金額が大きいといえます。
また投資期間中は、信託報酬などのコストがファンド資産から間接的に徴収されます。
ETFの保有期間中のコストは「経費率」という数値で表現されているため、投資前に確認しておきましょう。
ETFのなかには、株式市場の数倍の値動きになるように設定された商品など、ハイリスクな商品もあります。
銘柄選びを慎重におこない、自分にあった投資先を厳選してください。
ETFにおすすめの証券会社は三菱UFJeスマート証券
新NISAを活用してETFへ投資したい場合は、三菱UFJeスマート証券がおすすめです。
三菱UFJeスマート証券(旧社名:auカブコム証券)では、新NISAでの日本株やETFの売買手数料が無料となります。
さらに「フリーETF」の銘柄群は、課税口座の取引でも手数料無料です。
三菱UFJeスマート証券は、スマートフォンアプリの機能が充実しています。
ETFを含むさまざまな資産の情報収集から発注まで、スマートフォン上で完結させることができ外出先からでも手軽にETF投資ができます。
ETFへの投資が向いている人
ETF(上場投資信託)の投資が向いているのは、低コストで分散投資を実現したい人です。
ETFは株式と同様に市場で取引できるため、流動性が高く、リアルタイムの価格で売買が可能です。
個別株を選ぶ手間を省きながら、特定の指数やテーマに連動する運用が可能で、初心者から経験者まで幅広く利用されています。
また、手数料を抑えつつ長期的な資産形成を目指す人や、特定の国やセクターに関心がある人にも適しています。
ただし、短期的な市場変動リスクは伴うため、目的に応じた選択が重要です。
5.ロボアドバイザー|ほったらかし投資が可能

ロボアドバイザーを活用することで、少額から世界中の資産に分散投資が可能です。
自動でリバランスもしてくれるため、一度発注したあとは売却までなにもしない「ほったらかし投資」を実践しやすい投資先の一つといえます。
ロボアドバイザーの特徴
ロボアドバイザーは、証券会社などが提供しているAIを活用して投資家の資産運用をサポートしてくれるサービスです。
大別すると「アドバイス型」「投資一任型」の2つがあります。アドバイス型は、投資診断してくれるだけなので、投資先の決定は自分でおこなわなければなりません。
一方、投資一任型はロボアドバイザーが世界中の資産へ自動で投資してくれるため、手間なく資産運用をするうえでの有効な選択肢の一つとなるでしょう。
ロボアドバイザーのメリット
投資一任型のロボアドバイザーの主なメリットは、以下の3つです。
【ロボアドバイザーの主なメリット】
1. 少額で世界中の資産に分散投資できる
2. 自動でリバランスしてくれるため手間いらず
3. 新NISAを使える会社もある
投資一任型のロボアドバイザーサービスは、多数の投資家から集めた資金を、AIなどを活用して世界中のさまざまな資産へ分散投資しています。
10万円でもリスクを分散しながら資産運用が可能です。
また投資開始後は、システムが自動でリバランスしてもらえます。
自分で市場環境に応じて売買する必要がないため、手間がかからず「ほったらかし投資」が可能です。
2024年3月時点でウェルスナビなど一部のロボアドバイザーは、新NISAに対応しており、上手に活用すれば投資信託や株の売買と同様に投資収益が課税されずに投資ができます。
ロボアドバイザーのデメリット
投資一任型のロボアドバイザーの主なデメリットは、以下の3つです。
【ロボアドバイザーの主なデメリット】
1. 自分で投資先を選べない
2. ロボアドバイザーで新NISAを利用すると他社では新NISAを使えない
3. 運用コストがかかる
ロボアドバイザーは、システムで預かり資産を世界中の資産に分散するサービスです。
そのため、自分で投資信託や株などを選んで投資することができません。
また新NISAは、すべての金融機関のなかで一人1口座しか開設できないため、ロボアドバイザーで新NISAを利用すると他社での投資信託や株などの売買に新NISAは使えなくなります。
さらにロボアドバイザーは、運用コストがかかります。
たとえばウェルスナビでは、預かり資産から間接的に手数料が徴収される仕組みです。
投資資金と別に現金を徴収されることはありませんが、手数料はパフォーマンスの低下要因となりかねません。
おすすめのロボアドバイザーはウェルスナビ
投資一任型のロボアドバイザーをはじめて利用する場合は、ウェルスナビがおすすめです。
ウェルスナビは、1万円という少額から約50ヵ国、1万2,000銘柄への分散投資ができます。
いくつかの質問に答えるだけで、自分に合ったリスク水準の運用が実行できる点も魅力といえるでしょう。
2016年の運用開始以来、着実な運用実績を残しているのも特徴です。
また「おまかせNISA」を活用すれば、新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の双方を活用して投資ができます。
ロボアドバイザーが向いている人
ロボアドバイザーが向いているのは、投資に関する知識や時間が限られている人や、手軽に資産運用を始めたい初心者です。
ロボアドバイザーは、質問に答えるだけでリスク許容度に応じた最適なポートフォリオを提案し、自動で運用・管理してくれるため、専門知識がなくても始めやすいのが特徴です。
また、分散投資やリバランスを自動で行うため、手間をかけず効率的な運用を目指す人に適しています。
ただし、手数料や運用内容を確認し、自分の目標に合ったサービスを選ぶことが大切です。
6.FX|リスクは高いがリターンも高い

FXは、ハイリスク・ハイリターンな投資方法の一つです。
証拠金を預けると、その金額以上の規模での為替売買が可能です。
短期間で大きな収益を上げるチャンスがある反面、元本以上の損失を被るリスクがある点には注意しましょう。
FXの特徴
FXは、Foreign Exchangeの略で和訳すると「外国為替証拠金取引」となります。
証拠金をFX運営業者に預けると、証拠金よりも大きな金額で為替売買ができる投資です。
たとえば米ドル対円の買いの取引をすれば、購入時の為替レートよりも円安になったときに収益が発生します。
証拠金に対するポジション量を「レバレッジ」といい、レバレッジが高いほどハイリスク・ハイリターンとなるのが特徴です。
証拠金10万円に対してレバレッジ1倍と25倍で米ドル対円を売買したときの損益のイメージは、以下のようになります(手数料やスワップ収入などを加味しない)
| 為替レート | レバレッジ1倍 | レバレッジ25倍 |
|---|---|---|
| 1米ドル=100円→1米ドル=101円 | 1,000円の収益 | 2万5,000円の収益 |
| 1米ドル=100円→1米ドル=99円 | 1,000円の損失 | 2万5,000円の損失 |
FXのメリット
FXで10万円に投資する主なメリットは、以下の3つです。
【FXで10万円に投資する主なメリット】
1. 短期間で大きな為替収益を獲得するチャンスもある
2. ポジションによってはスワップ金利が得られる
3. 上昇・下落両方の場面で収益を追求できる
FXは、レバレッジを高めれば少額でも大きなポジションを形成できます。
そのため自分の想定どおりに為替が動けば、短期間で大きな利益を獲得できるチャンスがある点は魅力的です。
また高金利通貨を買い、低い金利の通貨を売ると「スワップ収入」という金利収入が手に入ります。
たとえ為替が動かなくても時間とともに収益を増やせる点はメリットです。
またFXは、買い(ロング)売り(ショート)のポジションを柔軟にとることが可能です。
たとえば米ドル対円で考えた場合、円安方向・円高方向の双方の取引ができます。
FXのデメリット
FXで10万円に投資する主なデメリットは以下の3つです。
【FXで10万円に投資する主なデメリット】
1. 元本以上の損失を被るリスクがあるハイリスクな投資先である
2. 相場を逐一チェックする必要がある
3. 投資のコストがわかりにくい
FXは、ハイリスクな投資手法で、ときには元本にあたる証拠金が全損して、さらに追加の差し入れを求められるリスクもあります。
また、為替相場は休日を除いてほぼ24時間動いており、損益も目まぐるしく変わるため、逐一相場をチェックしなければならない点はデメリットです。
FXでは、しばしば買い(Bid)と売り(Ask)のレートに差があり、この差を「スプレッド」と呼びます。
仮に為替相場が動かない場合、両者の差は投資家の含み損となるため、スプレッドは投資家にとって利益を圧迫するコストとなります。
また金利の低い通貨を買い、高い通貨を売った場合は、スワップ金利分が日々損失として積み重なっていきます。
スプレッドもスワップ金利も一定ではないため、投資コストが分かりにくいこともデメリットといえるでしょう。
おすすめのFX業者はSBI FXトレード
少額からFX取引をおこなううえでおすすめな業者の一つが、SBI FXトレードです。
この業者は、1通貨単位から取引ができるため、少額で投資がしやすく複数通貨への分散投資もしやすいです。
また通貨ペアは、34種類もあり世界の多様な通貨のなかから投資先するポジションを選べます。
さらに取引手数料やロスカット手数料、出金手数料などがかからないことも魅力です。
FXでの投資が向いている人
FX(外国為替証拠金取引)が向いているのは、短期的な値動きを活用して利益を狙いたい人や、為替市場に興味がある人です。
少額から始められ、レバレッジを利用することで資金効率を高められる点が魅力です。
また、24時間取引が可能なため、ライフスタイルに合わせて柔軟に取引できます。
ただし、価格変動が大きくリスクも高いため、相場の分析力やリスク管理が求められます。
迅速な意思決定ができる人や、リスク許容度が高い中・上級者に特に適しています。
7.クラウドファンディング/ソーシャルレンディング|少額で不動産投資が可能

クラウドファンディング/ソーシャルレンディングは、少額から不動産やローンなど本来個人投資家が投資しづらい資産へ間接的に投資できるファンドです。
運用期間中や償還時に得られる分配金が主な収益源となります。
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングの特徴
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングは、インターネットを通じて不特定多数の投資家から小口の資金を集めて特定の事業や企業へ投資するファンドです。
寄付型・購入型など投資商品とはいえないファンドがある一方、投資型の商品なら分配金収入を中心とした収益獲得を追求できます。
ファンドにもよりますが、1万~10万円程度の少額から投資できるものが多いことが特徴です。
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングのメリット
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングの主なメリットは、次の3つです。
【クラウドファンディング/ソーシャルレンディングのメリット】
1. 少額で有価証券以外に実質的な投資ができる
2. 利回りが国債などと比べると高い
3. 元本紹介実績100%の事業者なら信頼できる
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングは、1万円程度から投資できるファンドもあるため、少額投資に適している点がメリットです。
ファンドの投資先は不動産や事業者向けローン、富裕層向けファンドへの投資などさまざまで有価証券ではない多様な先に投資できます。
利回りは、ファンドによりさまざまですが、なかには年率5%を超えるファンドも少なくありません。
またいくつかの事業者は、これまで投資家に100%元本を返済していて損失を引き起こしていません。
このように実績充分な事業者であれば、安心して投資できるでしょう。
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングのデメリット
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングの主なデメリットは、以下の3つです。
【クラウドファンディング/ソーシャルレンディングのデメリット】
1. 投資に失敗すれば元本が毀損するおそれも
2. 償還まで換金ができない
3. ファンドを購入できるタイミングが限られている
投資型のクラウドファンディング/ソーシャルレンディングは、特定の事業・企業などに出資や融資をおこなっています。
もし投資先の事業運営が失敗に終わった場合、投資家の元本が毀損するリスクもゼロではありません。
また多くのファンドは、運用期間が決まっていて期間中は換金ができない点もデメリットの一つです。
証券市場に上場している商品ではないため、ファンドの募集タイミングに限りがあります。
投資資金があっても、募集ファンドがなければ投資はできません。
おすすめのクラウドファンディング/ソーシャルレンディングはオルタナバンク
初心者におすすめのクラウドファンディング/ソーシャルレンディング業者の一つが、オルタナバンクです。
オルタナバンクでは、国内外のさまざま事業に対する融資をファンドに組成しており、多くのファンドが最低投資金額1万円から購入できます。
そのため少額での投資がしやすい事業者といえるでしょう。
2024年3月7日時点で183本のファンドを償還済みで、すべてのファンドで100%元本償還の実績があります。
1ヵ月程度の短期運用のファンド~数年におよぶものまで多様な運用期間のファンドがあるため、適度な年数のファンドを柔軟に選べることも特徴です。
クラウドファンディング/ソーシャルレンディングへの投資が向いている人
クラウドファンディングやソーシャルレンディングへの投資が向いているのは、少額から分散投資を行いたい人や、新しいビジネスや社会貢献活動を支援したい人です。
これらは株式や債券とは異なるリターンを得られるため、投資ポートフォリオを多様化したい人にも適しています。
特に、プロジェクトの内容や社会的意義に共感し、長期的な目線でリターンを待てる人に適しています。
ただし、プロジェクトの失敗リスクや流動性の低さがあるため、信頼できるプラットフォームの選択やリスク分散が重要です。
8.個人向け国債|安全性の高い投資商品

個人向け国債は、発行体が日本国となるため、安全性の高い投資先の一つです。
利回りは低いものの、日本の財政が極度に悪化して元利金支払いが滞らない限り、償還日まで持ち続ければ額面で返済されます。
個人向け国債の特徴
個人向け国債は、個人を主な顧客と想定して発行されている国債です。
国債は、世界各国で発行されていますが、日本で単に個人向け国債というと日本国が発行する国債を指します。
変動金利10年と固定金利5年・3年があり、そのときの国債の金利水準をもとに利率が決定する仕組みです。
また、すべての国債で最低金利が0.05%に設定されています。
個人向け国債のメリット
個人向け国債の主なメリットは、次の3つです。
【個人向け国債の主なメリット】
1. 日本が発行しているため元本毀損リスクが低い
2. 1万円の少額から投資できる
3. 預金より高い金利を追求できる場合も
国が発行しているため、企業が発行する株や債券よりも低リスクです。
保有期間中は、価格が変動する可能性はありますが、償還まで持ち続ければ、デフォルトしない限りは額面で返済されます。
また各年限とも1万円の少額から投資が可能です。10万円あれば、ほかの投資先と組み合わせてポートフォリオを形成できます。
2024年3月(第156回)の発行銘柄の金利は、固定5年で0.33%です。
市場環境にもよりますが、預金より高い金利で募集する可能性もあります。
なお2024年3月7日時点の三菱UFJ銀行の5年定期預金は、スーパー定期の300万円未満で0.07%です。
個人向け国債のデメリット
個人向け国債のデメリットは、次の2つです。
【個人向け国債の主なデメリット】
1. 株や投資信託と比べると収益が出にくい
2. 途中換金するとコストがかかる
国債はリスクが低い反面、リターンも低いことがデメリットです。
基本的に安全性重視の投資に適した商品といえるでしょう。
また個人向け国債は、途中で換金するとコストがかかります。
具体的には、3回目の利払い以降の換金ケースで、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が割り引かれて換金されます。
そのため、基本的には償還まで持ち切るのに適した商品といえるでしょう。
個人向け国債への投資が向いている人
個人向け国債が向いているのは、安全性を重視し、元本を減らさずに運用したい人です。
国が発行するため信用リスクが極めて低く、固定金利型や変動金利型など、自分のニーズに合ったタイプを選べる点が特徴です。
また、最低1万円から購入可能で、満期まで保有すれば元本が保証されるため、初心者やリスクを抑えた資産運用をしたい人に適しています。
ただし、金利は低めに設定されているため、高いリターンを求める人には不向きです。
安定した資産形成を目指す人におすすめです。
10万円だからこそ知っておきたい!少額投資の魅力
10万円という資金で投資を始めることは、あなたの資産形成において非常に価値のある、そして現実的な第一歩です。
「少額だから意味がないかも…」なんて思わずに、10万円だからこそのメリットを活かし、知っておくべき注意点を押さえて、賢いスタートを切りましょう。
精神的なハードルが低く、始めやすい
「投資は怖い」「損したらどうしよう…」という不安は誰にでもあります。でも、10万円なら「まずは試してみようかな」と、一歩を踏み出しやすいのではないでしょうか。
万が一、投資額が減ってしまっても、生活に大きな支障が出にくい範囲で始められる安心感は、少額投資ならではの大きなメリットです。
「経験」というお金で買えない価値が得られる
実際に自分のお金で株や投資信託を買ってみることで、経済ニュースが身近になったり、企業の業績に関心を持ったりと、お金や社会に対する視野が広がります。
この「実践経験」は、どんな本を読むよりも深く学べる貴重な財産となり、将来のより大きな資産運用に必ず役立ちます。
失敗から学べる「授業料」と捉えられる
特に初心者のうちは、うまくいかないこともあります。しかし、10万円という規模であれば、もし失敗しても損失額は限定的です。
その経験から「なぜうまくいかなかったのか」「次はどう改善しよう」と具体的に学ぶことができれば、それは将来への「賢い授業料」と考えることができます。
「投資習慣」を無理なくスタートできる
少額でも投資を始めることで、「毎月少しずつ積み立ててみよう」「もっと勉強してみよう」という意欲が湧き、自然と資産形成への関心が高まります。
これは、長期的な目標達成に不可欠な「投資を続ける習慣」を無理なく身につける絶好のチャンスです。
10万円で投資するときの注意点4つ

10万円の少額から投資する際は、主に以下の4つの注意点を押さえておきましょう。
1.怪しい投資話に注意
基本的に損失リスクのない投資はありません。
高いリターンが見込める投資は、リスクも高いのが一般的です。
短期間で大きな利益を稼ごうとすると、つい怪しい投資話に乗ってみたくなるかもしれません。
しかし「高いリターンを確実に稼げる」といった商品は、詐欺かそれに近い商品の可能性があるため、甘い話にだまされてしまわないように注意しましょう。
2.ハイリターンを無理に狙わない
ハイリターンを無理に追求することは、おすすめできません。
元手が少ない場合は「短期間で資金を増やしたい」と考えてしまいがちです。
あせりから、ハイリスクな投資をして相場が思わぬ方向に動けば、大きな損失を被る可能性があります。
初心者の場合は、基本的に中長期で着実に資産を増やすスタンスが望ましいでしょう。
どうしてもハイリスクな投資にチャレンジしたい場合は、元本の10万円が大幅に毀損しても問題がないかを慎重に確認してください。
3.生活資金は残しておく
生活資金を残したうえで、10万円を捻出できることをあらかじめ確認しましょう。
10万円以外にまとまった預貯金がないにもかかわらず、10万円を投資に回すことはおすすめできません。
想定外の支出増や、ちょっとしたケガ・病気による休業などに対応できるよう、10万円のほかに一定の資金は残しておくことが基本です。
生活資金がない方は、焦らず投資を始める前に預貯金を増やしましょう。
4.「お試し感覚」で終わらせない
少額だからと安易に考え、すぐにやめてしまっては、せっかくの経験も活かせません。
「なぜ投資をするのか」という自分なりの目的意識を持ち、少額でも真剣に取り組む姿勢が大切です。
10万円で投資するときの投資先の選び方4つ

10万円で投資するときの投資先の主な選び方は、以下の4つです。
1.少額投資ができるかどうか
少額から投資ができる資産を選ぶのが第一です。
そもそも最低投資金額が10万円を超える商品には、10万円では投資ができません。
また投資対象となる最低投資金額が小さければ、それだけ複数の銘柄を売買できるため、10万円からの投資先として適しています。
もしくは、ロボアドバイザーのように商品のなかで分散投資される仕組みとなっているものを選ぶことも一案です。
2.どのくらいのリスクをとるか
許容するリスクの水準を明確にしたうえで、リスクの高さに見合った商品へ投資しましょう。
10万円で投資できる資産は複数あり、国債のようにローリスク・ローリターンな投資先からFXのようにハイリスク・ハイリターンな投資先などさまざまです。
投資商品のリスクの高さを分析したうえで、自分に合ったリスクの商品へ投資しましょう。
3.売買しやすいか
売買のしやすい商品を選好するという考え方もあります。
投資資金および預貯金が少額しかない場合、想定外に換金の必要性が高まる可能性も出てくるかもしれません。
上場株式やETFのようにスピーディに売却できる商品であれば、いざというときにすぐ換金することが可能です。
一方、クラウドファンディングや国債のようにすぐ換金しにくかったり、換金コストがかかったりする商品もあります。
そのため投資する場合は、10万円がすぐに必要とならない余裕資金で始めることが大切です。
4.長期投資か短期投資か
長期投資もしくは短期投資など、おおよその目安を持ったうえで投資先を選別しましょう。
投資先によっては長期投資に適した商品と、短期投資も可能な商品があります。
たとえば、国債は長期投資に適していますが、株やFXは比較的短期でも利益を出せる可能性がある金融商品です。
自分が考える投資期間に合った投資商品を選ぶようにしましょう。
10万円での投資に役立つ2つの制度

10万円から投資を始めるうえでは、次の2つの制度を有効活用しましょう。
いずれの制度も非課税や所得控除などで、効率よく資産運用ができます。
1. iDeCo|拠出額は全額所得控除
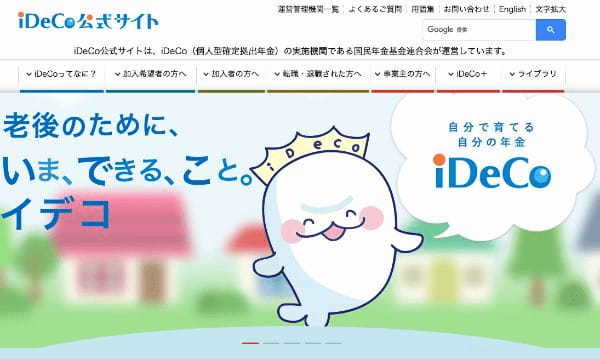
iDeCoは、年金に上乗せする形で老後資産形成のために設けられた制度です。
iDeCoは、自分で拠出額を決め、金融機関が設定するラインナップから投資先を選んで運用します。
毎月の拠出額は、企業年金がない会社員で月額2万3,000円が上限です。
10万円を元手にする場合は、数ヵ月かけることができます。
運用期間中は、月額171円(税込)などの手数料がかかる点はデメリットですが、拠出額は全額所得控除となるため、節税効果が期待できる点はメリットです。
一方、投資資金は原則60歳まで引き出せないため、注意しましょう。
2.新NISA|得た収益が非課税となる

新NISAは年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、総額1,800万円(成長投資枠は上限1,200万円)までの有価証券投資で得た収益が非課税となる制度です。
金融庁が選定した投資信託へ投資できる「つみたて投資枠」と、投資信託や株・ETFなどに投資できる「成長投資枠」の2つの制度を利用できます。
今回紹介した資産のなかでは、以下の資産で新NISAが活用できます。
- 投資信託
- ETF
- 日本株
- 米国株
- ロボアドバイザー(一部の会社のみ)
本来投資の収益にかかる20.315%(復興特別所得税を含む)の税金分が非課税となるため、効率よく資産を増やすことが期待できます。
10万円からの投資であれば枠は充分にあるため、投資資金ができたら徐々に積み増していくこともおすすめです。
・つみたて投資枠を活用して少額で積立投資を始めることも有効
新NISAのうち、つみたて投資枠は投資信託(一部ETF)の長期積立投資に特化した制度です。
今後少しでも投資資金が継続的に発生する見込みの方は、つみたて投資枠での積立投資を始めるのもよいでしょう。
ネット証券であれば、月100円から積立投資が可能な証券会社もあります。
まとめ|10万円で投資するなら少額投資できる投資先を選ぶ

少額投資できる資産は、たくさんあるため、10万円もあれば投資にチャレンジすることは可能です。
さまざまな投資先の選択肢のなかから、自分にあった商品を選んで購入しましょう。
1万円以下など、少額で投資できる商品を複数保有して分散投資することも選択肢の一つです。
初心者の場合は、過度なリスクをとらずに中長期的に着実に増やしていくことが望ましいといえます。
どうしても短期でハイリターンを狙いたい場合は、資金に余裕があることをあらかじめ確認したうえでチャレンジしてください。