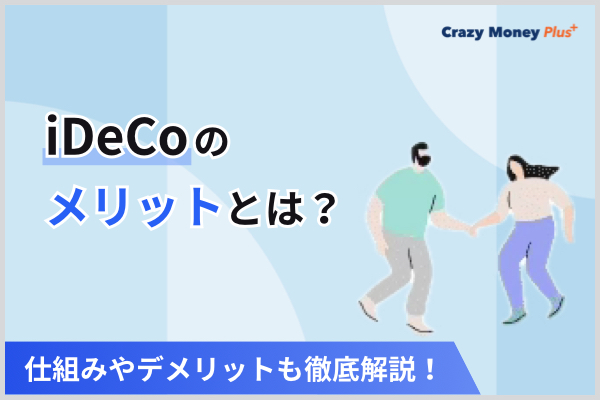「iDeCoに興味があるけれど、どのようなメリットがあるのか知りたい」という人のための解説記事です。
iDeCoのデメリットをSNSなどで見て始めるのが不安な人向けに、制度のデメリットや向いていない人も紹介するので、悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
結論からいうとiDeCoは「自分で備える老後資金」なので、リタイア後の生活に備えたい人はなるべく早く始めたほうがよいでしょう。なぜならiDeCoは「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税」など税制優遇が受けられてお得だからです。
できればNISAとiDeCoを併用して、なるべく早く資産運用を始めることをおすすめします。
人によっては「iDeCoよりNISAのほうが向いている」という人もいるので参考にしてください。
iDeCoは自分で準備する老後資金!早めに始めて節税効果を実感しよう
iDeCoは「自分で準備する老後資金」とイメージするとわかりやすいでしょう。そのため「老後資金に不安を感じている」「自分で備えておきたい」という人は、なるべく早めにiDeCoを始めるのがおすすめです。
2024年度末時点で60~64歳の国民年金平均年金額は「4万4,836円」、厚生年金は「7万5,945円」となっています。現在自営業の人、専業主婦(主夫)の人は、国民年金が受け取れます。会社員の人は、国民年金と厚生年金が受け取れる仕組みです。
とはいえ、これはあくまで2024年度末時点での平均額なので将来絶対にこの金額が受け取れるわけではありません。つまり私たちが年金を受け取る際は、もっと金額が減っている可能性もあるわけです。
また現代は「人生100年時代」といわれています。仮に60歳でリタイアしたとすると30~40年ほど年金で暮らさないといけないわけですから、自分で資金を備えるに越したことはありません。
iDeCoは、公的年金ではなく私的年金です。公的年金にプラスして自分自身で退職金や年金として資産を形成できるお得な制度となっています。
iDeCoの仕組み
iDeCoは、自分自身で毎月資金を出して運用し、その成果を優遇された税制で60歳以降に受け取れる仕組みです。「自分で作る老後資金」というイメージなので原則60歳までは引き出せません。
「国から年金が支給されるのにiDeCoをやる必要はあるの?」と疑問を感じる人もいるかもしれません。ここでは、年金制度についておさらいしておきましょう。日本の年金制度は「2階建て」になっています。
【年金制度のイメージ】
| なし | 厚生年金 | なし |
| 国民年金 | ||
| 自営業 (第1号被保険者) |
会社員・公務員 (第2号被保険者) |
専業主婦(主夫) (第3号被保険者) |
1階の国民年金と2階の厚生年金は「公的年金」です。老後に安心して生活できるように国が運用している制度です。
企業によっては「企業型確定拠出年金」「企業年金」など3階部分にあたる年金が出るところもあります。これは、国とは関係なく企業が従業員のために運用している制度です。
自営業の人や専業主婦(主夫)の人は、1階部分の国民年金しか受け取れません。(ずっと自営業や専業主婦だった場合)また会社員や公務員が受け取れる厚生年金も現役時代の月収によって受け取れる金額が個人ごとに異なります。
この年金制度の3階部分に自分で「私的年金」として年金を作るのがiDeCoです。国民年金や厚生年金に加えて自分で運用した成果が非課税で一時金、もしくは年金として受取が可能になるため、老後の備えとして活用できます。
2024年12月からの改正点
iDeCoは、2024年12月から以下の2点の改正を受け、より活用しやすい制度になりました。
- 企業年金・共済加入者のiDeCo掛金の上限が引き上げになった
- iDeCo加入の手続きが簡単になった
従前は、企業年金や共済などほかの制度に加入している人の場合、月の上限が1万2,000円まででしたが、月額2万円までに引き上げられて節税効果が得やすくなりました。
iDeCoは、職業によって月にいくら積み立て(拠出)できるかの金額が異なるので確認しておきましょう。
【iDeCoの拠出上限額】
| 職種 | 月の拠出上限額 | |
|---|---|---|
| 自営業 (第1号被保険者) |
6万8,000円 | |
| 会社員・公務員 (第2号被保険者) |
会社に企業年金がない人 | 2万3,000円 |
| 企業型確定拠出年金にのみ加入している人 | 2万円 | |
| 企業型確定拠出年金と、共済などほかの制度に加入している人 | ||
| 共済などほかの制度にのみ加入している人 | ||
| 専業主婦 (主夫) |
2万3,000円 |
加えてiDeCoの加入手続き時に必要であった「事業主証明書」が不要になりました。これまで会社員や公務員の人がiDeCoに加入するには、掛金の上限額を確認するために「事業主証明書」を発行してもらわなければなりませんでした。
しかし今回の改正で個人口座から積み立てする場合は、勤務先への申請せずにこの制度に加入できるようになりました。申し込みが簡単になるので今までためらっていた人は、ぜひiDeCoを始めてみてください。
iDeCoを始めるべき5つのメリット
iDeCoを始めるべきメリットを5つ紹介します。
1.iDeCoに積み立てた金額はすべて所得控除
iDeCoに積み立てた額は、全額所得控除の対象です。日本は、累進課税制度が導入されており所得が多ければ多いほど税金が重くなります。
なかには、給与明細を見て「ずいぶん税金が引かれるな」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか。全額所得控除の対象のiDeCoに加入すれば、拠出額がすべて所得から差し引かれるので、所得税や住民税を抑えることが期待できます。
例えば30歳の会社員の人が毎月2万円を積み立てした場合、どのくらい節税になるか以下の表で見てみましょう。
【30歳の会社員が月2万円を積み立てた場合の節税効果】
| 年収 | 400万円 | 500万円 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 1年間の軽減税額 (所得税+住民税) |
約3万 6,000円 |
約4万 8,000円 |
約7万 2,000円 |
「節税に興味がある」「自身にかかる税金を少しでも抑えたい」という人は、ぜひiDeCoを始めてみてください。
2.運用益が非課税
iDeCoの運用益は、非課税になるためお得に資産運用できます。通常、株式投資などの資産運用で利益を得た場合は、20.315%(復興特別所得税)が税金として差し引かれます。
例えば10万円で購入した株が値上がりして20万円で売却した場合、手もとに戻るのは20万円ではありません。10万円の利益を得たので2万315円(10万円×20.315%)が税金として引かれ、手もとに戻るのは17万9,685円ということになります。
一方、iDeCoの運用益はすべて非課税です。先ほどの例でいえば20万円がそのまま受け取れます。以下の表で30年間iDeCoに2万3,000円積み立てた場合の資産運用シミュレーションを確認してみましょう。
【30~60歳まで毎月2万3,000円拠出した場合の予想資産額】
※条件
年収:500万円
扶養配偶者:なし
扶養している親族:0人
| 運用利回り | 3% | 5% | 7% |
|---|---|---|---|
| 投資元本 | 828万円 | ||
| 予想資産額 | 約1,331万 399円 |
約1,875万 3,645円 |
約2,689万 7,409円 |
iDeCoは、最低金額が5,000円から始められます。「最初は5,000円から開始し慣れてきたら拠出上限額にする」といった金額変更もできるので少額でも長期間続けてみてください。
将来の自分自身を助けることにつながるはずです。
3.受取時にも優遇税制が受けられる可能性がある
iDeCoは、運用を続けながら毎年年金として受け取ることもできますが退職金のように一度に受け取ることも可能です。
どちらの方法で受け取る場合も税制優遇措置が受けられる可能性があるのでお得です。受取方法による優遇措置の違いを確認しておきましょう。
【iDeCoの受け取り方と優遇措置】
| 受け取り方 | 税制優遇措置 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一時金受取 | 退職所得控除の対象 | ・会社から退職金が出る人は「通常の退職金+iDeCoの一時金」で課税対象が増えてしまうので注意 |
| 年金受取 | 公的年金等控除の対象 | ・公的年金、厚生年金、iDeCoと年金額が多いと課税の対象となる点に注意 ・公的年金等控除額は、65歳未満と65歳以上で異なる ・65歳以上で受け取るほうが控除額としては大きい |
個人の状況でどちらの受け取り方が有利ということはありません。自分にとってどちらが有利になるかを検討したうえで受取方法を選択することが大切です。
4.一度設定すれば自動積立される
iDeCoは、一度設定すれば自動積立になるので運用の手間がいりません。iDeCoは、運用先を自分で選んで積立額を設定すればあとは自動で毎月積み立てされる仕組みです。
そのため「日中忙しくて株式市場を見ている時間がない」「投資に関する知識があまりない」という人でも簡単に始められます。株式投資と異なり積み立てを継続することで資産形成する仕組みのため、売買のタイミングを自分で見る必要はありません。
極論、積み立てを開始後20年、30年と継続している間は放置しておいても問題ありません。「将来に備えて自分で何か始めたいが運用している時間や知識はない」と考えている人は、iDeCoを始めてみましょう。
5.60歳までは原則引き出せないので浪費の心配がない
iDeCoは、原則60歳になるまでは引き出せないので使ってしまう心配がありません。なぜならこの制度の目的は、老後資金や私的年金という特性があるからです。
そのため拠出している人が60歳になるまでは原則資金が引き出せないので「資金があると使ってしまう」「油断してしまう」といった人に最適でしょう。とはいえ60歳で引き出すためには、通算加入者等期間10年以上が条件です。
10年に満たない場合は、受給可能年齢が繰り下げられるので覚えておいてください。
もちろん受け取る年齢を自分で繰り下げることも可能です。20年間、年金形式でiDeCoを受け取った場合のシミュレーションを確認してみましょう。(30歳から毎月2万3,000円を拠出して、5%で運用したものとして計算)
【20年間年金として受け取った場合のシミュレーション)】
| 受取開始年齢 | 60~80歳 | 65~85歳 | 70~90歳 |
|---|---|---|---|
| 毎年の年金額 | 約91万2,356円 | 約126万1,628円 | 約158万7,399円 |
| 毎月の受取額 | 約7万6,029円 | 約10万5,135円 | 約13万2,283円 |
内閣府の「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」のなかで何歳までの就労を希望するかという質問があり、その結果は以下のとおりです。
- 65歳くらいまで:25.6%
- 70歳くらいまで:21.7%
- 働けるうちはいつまでも:20.6%
自身の状況に合わせてiDeCoを受け取る年齢を繰り下げても良いでしょう。
iDeCoを始める前に知っておきたい3つのデメリット
iDeCoには、以下のような3つのデメリットもあるので解説します。
とはいえ、なかには一概にデメリットといえないものもあるので、自分にとってはどうかについてよく確認しましょう。
1.途中で解約できない
iDeCoは、原則60歳までは引き出せず途中解約ができません。資金があるとつい油断して使ってしまう人にとってはメリットになりますが、「すぐに資金が必要になる」「貯金がない」という人にとってはデメリットといえます。
なおiDeCoの拠出金を払うのが厳しくなったときは、減額したり拠出を休止したりするなどの対処が可能です。休止にすると積み立てを停止して今まで払い込んだ分の運用を継続することになります。
iDeCoの拠出最低金額は5,000円なので、拠出額を減らして継続することを検討しましょう。
2.価格変動リスクがある
iDeCoは、運用する商品なので価格変動リスクがあります。とはいえ長期的に積立投資を行うことで元本割れのリスクは抑えられるでしょう。
金融庁の資料で積み立ておよび分散投資をした場合に元本割れする確率を調査したものがあります。
保有期間が5年と短い場合は、10%程の確率で元本割れする一方で、保有期間を20年と長くした場合は元本割れしたケースはありませんでした。
これからiDeCoを始める人も最初の5年間は元本割れして心配になったり不安を感じたりすることがあるかもしれません。しかし「20年間は保有する」「65歳までは継続する」と長期的な視点を持って運用するようにしてください。
3.手数料がかかる
iDeCoは、加入時と加入中、受取時に手数料がかかります。とはいえ手数料は、加入時に2,829円が1回のみと加入中は金融機関によっても異なりますが毎月171円程度かかるだけです。「デメリットというほどに多額か?」と考えると疑問を感じる数字でしょう。
iDeCoを始めることで受けられる「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税」「受取時も税制優遇措置がある」といったメリットと比較すると、手数料がかかるデメリットは気にしなくてよいと捉えて良いと思います。
シミュレーションで年収500万円の人が30~65歳まで毎月2万円拠出して5%で運用したケースのメリットとデメリットを確認してみましょう。
【年収500万円の人が毎月2万円の積み立てを35年間継続した場合に得られる恩恵とコスト】
| 35年間で受けられた税制優遇 | 所得税・住民税の優遇 | 約168万 6,500円 |
|---|---|---|
| 運用益の税制優遇 | 約275万 3,851円 |
|
| 20年間年金受取した想定額 | (年額) 約110万 7,828円 |
|
| 35年間運用した場合の予想資産額 | 約2,216万 9,259円 |
|
| 35年間でかかったコスト | 加入時の手数料 | 2,829円 |
| 運用時の手数料 | (毎月171円の場合)7万1,820円 |
受けられる恩恵のほうが、はるかに大きいことがわかります。手数料が気になっている人は、メリットの内容も見て本当にデメリットとなるかも考えてみてください。
iDeCoにおすすめの金融機関は?
iDeCoでおすすめの金融機関は、口座管理料や運用中のコストの低いところがおすすめです。加入時手数料は、国民年金基金連合会へ支払うものなので一律2,829円と金融機関によって違いはありません。
一方、運用期間中にかかる費用は金融機関で異なります。最も低い手数料は、毎月171円の金融機関なので一例を紹介します。
【運用期間中の手数料が171円の金融機関一例】
| 金融機関 | 運用中の費用 (毎月) |
積立休止時 (毎月) |
移換時 |
| SBI証券 (セレクト・プラン) |
171円 | 66円 | 4,400円 |
| 楽天証券 | 171円 | 66円 | 4,400円 |
| マネックス証券 | 171円 | 66円 | 4,400円 |
| 三菱UFJ eスマート証券 |
171円 | 66円 | 4,400円 |
| auアセット マネジメント |
171円 | 66円 | 4,400円 |
| 松井証券 | 171円 | 66円 | 4,400円 |
| 野村証券 | 171円 | 66円 | - |
| 大和証券 | 171円 | 66円 | 4,400円 |
| SMBC日興証券 | 171円 | 66円 | - |
| イオン銀行 | 171円 | 66円 | - |
| りそな銀行 | 171円 | 66円 | - |
| 日本生命保険 | 171円 | 66円 | - |
金融機関によっては、就職などで移換する際の手数料がかからないところもあるので事前に確認すると良いでしょう。
例えばauアセットマネジメントでは、auの投資信託を選ぶとPontaポイントが付与される独自のサービスを導入しています。自身が利用している銀行や証券会社、貯めているポイントなどと照らし合わせて自分に合った金融機関を選ぶようにしてください。
iDeCoでおすすめの金融商品
iDeCoのおすすめの運用先となる金融商品を紹介します。各金融機関で扱っている金融商品が異なります。運用先や信託報酬の比較など参考にしてください。
iDeCoでは、複数の商品を併用して運用することもできるので「株式型50%」「債券型50%」など、いくつかに分散投資するのもおすすめです。
株式型の商品
リスクをとって高いリターンを狙いたい人には、株式型の商品がおすすめです。
【iDeCoでおすすめの株式型商品】
| 銘柄名 | 投資先 | リターン | 信託報酬 |
| 三菱UFJeMAXIS Slim米国株式 (S&P500) |
米国株式 (S&P500) |
(3年)+23.93% (5年)+22.78% |
0.08140%以内 |
| iFree NY ダウ・インデックス |
米国株式 (ダウ平均) |
(3年)+21.89% (5年)+18.90% |
0.2475% |
| 三菱UFJeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 日本を含む先進国、新興国の株式 | (3年)+20.33% (5年)+18.88% |
0.05775%以内 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 日本を除く先進国の株式 | (3年)+21.99% (5年)+20.51% |
0.09889%以内 |
| eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 日本株式(TOPIX) | (3年)+16.45% (5年)+13.15% |
0.143%以内 |
※リターンは、2025年1月末時点の数字
株式型で迷った場合は、世界経済の中心ともいえる米国に投資をするものを選ぶとよいでしょう。米国だけに集中投資することに不安がある人は「世界中の株式市場をカバーするファンド」、為替が変動するリスクをとりたくない人は「日本株式に投資するファンド」がおすすめです。
投資先が同じでも信託報酬が異なっていることがあるので、事前の確認を忘れないでください。
バランス型の商品
「リターンとリスクはほどほどがよい」という人は、バランス型を選ぶと良いでしょう。バランス型は、株式と債券など数種類の資産に分散投資することで株式型よりもリスクを抑えた運用をしている点が特徴です。
【バランス型商品のおすすめ】
| 銘柄名 | 投資先 | リターン | 信託報酬 |
| eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) |
1. 国内株式 2. 国内債券 3. 先進国株式 4. 先進国債券 5. 先進国リート 6. 新興国株式 7. 新興国債券 8. 新興国リート |
(3年)+8.96% (5年)+7.92% |
0.143%以内 |
| セゾン・グローバルバランスファンド |
1. 国内株式 2. 国内債券 3. 米国株式 4. 欧州株式 5. 太平洋(日本除く)株式 6. 新興国株式 7. 米国債券 8. 欧州債券 |
(3年)+12.29% (5年)+11.20% |
0.56%±0.02%程度 (※信託財産留保額0.1%) |
| マイバランス70 |
1. 国内株式 2. 外国株式 3. 国内債券 4. 外国債券 (※株式の配分が約70%) |
(3年)+11.28% (5年)+11.09% |
0.154% |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2060 (※受取時の西暦に合わせた年数を選ぶ仕組み) |
1. 国内株式 2. 先進国海外株式 3. 新興国株式 4. 世界債券 5. 国内短期債券 |
(3年)+19.01% (5年)+17.28% |
0.36~0.38%程度 |
※リターンは、2025年1月末時点の数字
同じバランス型であっても均等に分散させているものもあれば、株式が多めの配分のものもあります。
また「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド」は、運用期間があらかじめ決まっている点が特徴の商品です。例えば「フィデリティ・ターゲットファンド2060」であれば、2060年に運用が終わります。2060年で60歳、65歳を迎えて運用を終わらせる人に最適です。
さらに運用が終盤になると株式ではなく債券の比率を多くして安定的な運用へ自動でシフトしていくよう運用されています。2060以外にも2030~2070までそろっているので、ぜひ検討してみてください。
債券や金で運用する商品
リスクをとりたくない人は、債券や金で運用する商品がおすすめです。とはいえ日本の債券だけに投資するファンドや元本確保型の商品は、利率が低すぎて手数料のほうが高くなる危険性もあるので気をつけましょう。
【債券や金で運用する商品】
| 銘柄名 | 投資先 | リターン | 信託報酬 |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 先進国債券 | (3年)+5.74% (5年)+4.65% |
0.154%以内 |
| たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり) | 先進国債券 (為替変動リスクを抑える、為替ヘッジあり) |
(3年)-6.93% (5年)-4.53% |
0.22% |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 先進国債券 | (3年)+5.82% (5年)+4.72% |
0.154% |
| 三菱UFJ純金ファンド | 金 | (3年)+26.37% (5年)+18.85% |
0.99%程度 |
※リターンは、2025年1月末時点の数字
債券で運用するものは、利率の高い外国債券で運用するものが多い傾向です。為替ヘッジありの商品は、為替変動リスクが抑えられる一方で、円安になっても恩恵が受けられないので覚えておいてください。
「株式投資は不安だけど債券ではリターンが小さくて不満」という場合は、金価格に連動する商品がおすすめです。
SBIベネフィットの人気商品
SBI証券が運営している「SBIベネフィット・システムズ」で拠出額が上位の商品を紹介します。運用先の参考にしてください。
【SBIベネフィット・システムズで拠出額が上位の商品】
| 銘柄名 | 投資先 | 3年リターン | 5年リターン |
| DCニッセイ外国株式インデックス | 日本を除く先進国株式 | +21.96% | +20.47% |
| iFree NYダウ・インデックス | 米国株式(NYダウ) | +21.89% | +18.90% |
| 三菱UFJ純金ファンド | 金価格 | +26.37% | +18.85% |
| EXE-i 先進国株式ファンド |
日本を除く先進国株式 | +20.95% | +20.13% |
| iFree8資産バランス | 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 国内リート 海外リート |
+9.08% | +7.86% |
先進国株式と米国株式、金に投資するものが上位に入っています。iDeCoで取り扱っている商品は、金融機関によって異なるので投資先の参考にしてください。
iDeCoとNISAの違いをおさらい
iDeCoを始める前にNISA制度との違いをおさらいしておきましょう。結論からいうとiDeCoとNISAは併用できるのでどちらも始めるのがおすすめです。
全額所得控除になって節税できるiDeCoのほうが優先度は高いといえますが、個人の性格や年収、年齢などによっては、NISAのほうが適しているケースもあります。NISAとiDeCoの違いを知って、自分に合っているのはどちらかを確認しましょう。
こちらの記事でもNISAとiDeCoの違いを解説しているので、合わせて読んでみてください。
「NISAとiDeCoの違いと目的別にどっちがいいのかを解説」
iDeCoとNISAの違いを比較
iDeCoとNISAの違いを表にまとめてみました。
【iDeCoとNISAの違い】
| NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 目的 | 個人投資の活性化 | 老後資金への備え |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 原則20歳以上60歳未満の国民年金加入者 (※条件付きで65歳未満も可) |
| 最低金額 | 100円~ (※金融機関によって異なる) |
5,000円~ |
| 運用上限額 | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | 年間14万4,000円~81万6,000円 (※職業や企業年金の有無で異なる) |
| 投資対象 商品 |
<つみたて投資枠> 長期・積立・分散投資に適していると金融庁が認めた投資信託 <成長投資枠> |
投資信託、定期預金、保険商品 |
| 資金の引き出し | いつでも可能 | 原則60歳までは引き出し不可 |
| 手数料 | 口座管理料0円 (※別途売買手数料がかかる場合もあり) |
加入時:2,829円 運用時:171円程度~(金融機関によって異なる) |
| 税制優遇 | 運用益が非課税 | ・運用益が非課税 ・掛金が全額所得控除 ・受取時にも退職所得控除や公的年金等控除の対象 |
| メリット | ・投資対象商品が多い ・最小購入単位が100円~ ・非課税期間が無期限 ・いつもで引き出し可能 |
・元本確保型商品がある ・税制優遇が多い ・受け取り方が選べる ・原則60歳まで引き出し不可のため浪費の心配がない |
| デメリット | ・元本保証ではない ・課税口座との損益通算ができない |
・手数料がかかる ・原則60歳まで解約できない |
| こんな人におすすめ | ・預貯金が少なく運用資金をいつでも引き出せるようにしたい人 ・少額で運用を始めたい人 ・クレジットカードによる投信積立でポイントを貯めたい人 ・リタイア世代のため運用する期間が限られている人 |
・少しでも節税したい人 ・老後のために備えたい人 ・企業年金がない人 ・自営業、専業主婦(主夫)で受け取れる年金が少ない人 |
NISAとiDeCoの両方始めることをおすすめしますが、1つだけを選ぶなら、節税効果の高いiDeCoの優先度が高めです。とはいえ「数年後に使う予定のある資金で始める」「少額で資産運用をしたい」という人は、NISAのほうが向いているといえます。
NISAとiDeCoの使い分けについては、こちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。
「【NISAとiDeCo】使い分けのポイントを徹底解説!あなたに合う制度はどっち?」
iDeCoに向いている人・向いていない人は
iDeCoとNISAの違いを把握したうえでiDeCoに向いている人と向いていない人のケースを確認してみましょう。iDeCoとNISAのどちらを始めるべきか悩んでいる人は、参考にしてください。
専業主婦(主夫)の人
専業主婦(主夫)の人は、iDeCoでもNISAでも良いので、とにかく老後に備えておくことが大切です。専業主婦(主夫)の場合、年金は国民年金のみとなります。(ずっと自営業や専業主婦だった場合)
厚生労働省の調査によると2023年度末の国民年金の平均額は毎月5万7,584円でした。厚生年金の平均額が14万6,429円なので、夫婦合わせると20万4,013円が毎月受け取れる年金となります。(参照:令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況)
一方、政府統計によると2024年におけるリタイアしている2人以上世帯(全国)の消費支出の合計は30万243円でした。毎月9万6,230円不足する計算なので60~85歳までの25年間で2,800万円ほど不足することになります。
運用して2,800万円を用意する場合、年利から計算して必要な積立額は以下のとおりです。
【30年間の運用で2,800万円形成する場合の必要積立額】
| 年率 | 3% | 5% | 8% |
|---|---|---|---|
| 毎月の積立額 (20年運用) |
8万5,288円 | 6万8,121円 | 4万7,537円 |
| 毎月の積立額 (30年運用) |
4万8,050円 | 3万3,644円 | 1万8,788円 |
運用年数が長いほど毎月の積立額が少なくても目標額を達成できます。まずは、できる範囲でなるべく早めにiDeCoかNISAで積み立てをして資産を作っておくことをおすすめします。
年収が低い人
年収が低い人は、節税効果を得にくいため、NISAのほうが向いています。iDeCoの最大のメリットは、拠出額が全額所得控除の対象となる点です。所得からiDeCoへ積み立てた金額を差し引くことで自分にかかる税金を抑えられてお得です。
とはいえ、そもそもかかる税金が少ない場合はiDeCoの節税効果も大きくは期待できません。月に2万3,000円積み立てした場合の節税効果を比較してみましょう。
【iDeCoで毎月2万3,000円積み立てした場合の年収別節税効果】
| 年収 | 1年間の節税効果 |
|---|---|
| 300万円 | 約4万1,400円 |
| 400万円 | |
| 600万円 | 約5万5,200円 |
| 800万円 | 約8万2,800円 |
・開始年齢:30歳
・配偶者:なし
・扶養の親族:なし
年収の低い人にとっては、NISAとiDeCoのどちらか一方を選ぶとしたら、より少額から始められてコストがかからないNISAのほうがよりおすすめといえます。
50~60代の人
50~60代の人には、NISAのほうが向いています。iDeCoの場合、運用できる期間が短くなってしまうためです。
60歳から年金を受け取るためには、iDeCoに加入していた期間が10年以上必要です。10年に満たない場合は、受給可能な年齢が繰り下げられます。
こうした点からもiDeCoより加入期間や引き出しに期限がなく、自由度の高いNISAのほうがおすすめです。ただiDeCoは、2022年の改正で国民年金に任意加入している65歳未満の人が加入できるようになっています。
年金として受け取る際も60~75歳まで選べるようになっているので「55歳から掛け込み65歳から年金を受け取る」「64歳まで掛け込み70歳から受け取る」という選択も可能です。
自営業の人
自営業の人であれば、NISAよりもiDeCoへの加入をおすすめします。なぜなら自営業は「厚生年金が出ないため年金額が少ない」「拠出の上限額が大きく節税効果を得やすい」といった点があるからです。
また自営業の人は、定年がないため退職金が出ないという点にも注意が必要です。iDeCoは、一時金として受け取ることで退職金の代わりにもなるので、ぜひ検討してみてください。
iDeCoは、拠出額によって1年間の節税効果が異なります。課税所得600万円の自営業者と仮定して節税効果を見てみましょう。
【拠出額による節税効果の違い】
※前提条件
・年齢:30歳
・受け取り開始:60歳
・運用想定利回り:3%
・配偶者:なし
・扶養親族:なし
| 毎月の拠出額 | 1年間の節税効果 |
|---|---|
| 5,000円 | 約1万8,200円 |
| 2万円 | 約7万3,000円 |
| 4万円 | 約14万6,000円 |
| 6万8,000円(上限) | 約24万8,200円 |
毎月6万8,000円を積み立てした場合、年間では81万6,000円となり、その分が所得から差し引かれます。節税効果が大きく将来の退職金や年金として利用できるのでメリットが大きいです。
自営業の人でiDeCoを始めていない人は、なるべく早く始めることをおすすめします。
所得が多い人
所得が多い人は、節税効果が期待できるためiDeCoの優先度が高くなります。日本は、所得が多いほど税率が高くなる累進課税制度を導入しています。そのため所得が多くなるほど社会保険料が増え控除額が減るため、払わなければならない税金も大きくなります。
東京都に住んでいる30歳を例にして、年収別にどのくらい税金がかかっているのかについて目安を確認してみましょう。
【額面年収・手取りと税金の目安】
| 額面収入 | 手取り年収 | 手取り月収 | 税金(※) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約237万円 | 約19万円 | 約62万円 |
| 600万円 | 約461万円 | 約38万円 | 約138万円 |
| 900万円 | 約661万円 | 約55万円 | 約238万円 |
| 1,200万円 | 約857万円 | 約71万円 | 約342万円 |
額面での収入が2倍、3倍になっても手取りはそう上がっていないことがわかります。なかには「年収が高くなったのに自由に使えるお金が増えた気がしない」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
「税負担を少しでも抑えたい」「節税効果のある制度を検討している」という人は、iDeCoを始めてみてください。
貯金が苦手な人
貯金が苦手な人は、iDeCoがおすすめです。原則60歳までは引き出せないので浪費してしまう心配がありません。iDeCoは「私的年金」「自分で作る老後資金」という特性があるため、個人が自由に引き出せないようになっています。
原則60歳になるまでは引き出せないため、貯金が苦手な人におすすめです。
反対に、NISAは引き出し自由でいつでもやめられるため、貯金が苦手な人は積立額がまとまった額になったら引き出して浪費してしまう危険度が高まります。
「貯金が苦手」「残高があるとすぐに使ってしまう」という人は、引き出しに制限のあるiDeCoを優先して始めてください。
iDeCoのメリットに関するQ&A
iDeCoのメリットに関するQ&Aをまとめました。iDeCoを始めようか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
iDeCoは確定申告が必要?
iDeCoは、年末調整もしくは確定申告が必要です。拠出額が全額所得控除の対象となるため、その年の所得からiDeCoへ積み立てた金額を差し引いて税額を計算する必要があります。
基本的に会社員であれば所得控除を受ける場合、確定申告は不要です。毎年10月ごろ、国民年金基金連合会から圧着式ハガキで郵送される「小規模企業共済等払込証明書」に、その年に払い込んだ合計金額が記載されています。
それを職場で配布される年末調整の「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に記入してください。これで年末調整は完了です。
自営業の場合は、確定申告時にiDeCoで拠出した金額を記入します。国民年金基金連合会から郵送される「小規模企業共済等払込証明書」に記載されている金額を確定申告書第一表の「小規模企業共済等掛金控除⑭」に記入してください。
確定申告のソフトによっては「iDeCoをしている場合は合計額を記入してください」と所定の欄に記入するよう指示されることがあるので従ってください。
スイッチングと割合変更の違いは?
iDeCoのスイッチング(移行)とは、すでに運用中の商品を解約して、その資金でほかの商品へ乗り換えることです。一方、配分変更は現在購入している運用商品の種類と配分を変更することを意味しています。
スイッチングの例を解説します。
運用初期は、初めての資産運用のためバランス型ファンドを選択し「iFree8資産バランス型」に毎月積み立てしたとしましょう。何年か運用を続けるうちに慣れてきたため、もっとリスクの高い投資先「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」へスイッチングしました。
【スイッチングの例】
| 時系列 | 銘柄 | 残高・スイッチング前 | 残高・スイッチング後 |
|---|---|---|---|
| 運用初期 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 100万円 | – |
| 運用中期~後期 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | – | 100万円 |
この場合は「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」を売却して利益を確定させ、売却した資金で今度は「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」で運用を続けることになります。資産をほかの商品に「移す=スイッチング」とイメージするとわかりやすいかもしれません。
続いて配分変更の例を見てみましょう。
スイッチングと同様に運用初期は安定運用をしており、運用に慣れてきたらリスクの高いファンドへシフトしていきますが、運用する投資先の配分を変更しています。
【配分変更の例】
| 銘柄名 | 配分・運用初期 | 配分・運用中期 | 配分・運用後期 |
|---|---|---|---|
| あおぞらDC定期 | 50% | 0% | 0% |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 50% | 50% | 0% |
| 三菱UFJ純金ファンド | 0% | 50% | 50% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0% | 0% | 50% |
配分を0%にしたものは、売却してスイッチングも可能ですが、拠出をやめるだけでそのまま運用を継続することも可能です。
「iDeCoを始めたいけど運用は不安」という人は、まずリスクの低い運用先から始めてみて、少しずつリスクが高いファンドへ少しずつスイッチングしたり、配分を変更したりしてもよいでしょう。
iDeCoはどうやって受け取るの?
iDeCoは、以下の3つの受け取る方法があります。
- 退職金のように一時金として一括で受け取る
- 年金のように5年以上20年以下の期間で分割して受け取る
- 一部を一時金として受け取り残りを年金として受け取る
一括で受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の対象になり、どちらで受け取っても税制優遇が受けられる可能性があります。
ただし退職金が会社から出る人は、iDeCoを一時金として受け取ると控除額を超えてしまったり、受け取る年金額が多い人は年金で受け取ると控除額を超えてしまったりする可能性があるため、注意しましょう。また、受け取る際には手数料が都度かかる点にも注意が必要です。
自身の状況に合わせて何歳から何年間受け取るのか、一括で受け取るのかを確認しておきましょう。