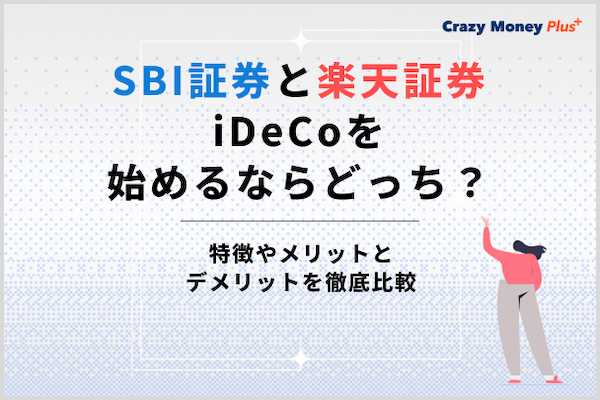SBI証券と楽天証券、どちらも非常に人気の高いネット証券です。
iDeCoを始めようと思ったとき、SBI証券や楽天証券のどちらを選べばよいのか悩んでしまう方もいることでしょう。
本記事では、SBI証券と楽天証券のどちらでiDeCoを始めたほうがいいのか悩んでいる方のために、2社を徹底的に比較して説明します。
ぜひ、この機会にiDeCoを始めてみてください。
\SBI証券でiDeCoを始める!/
\iDeCoの手数料の安さが魅力!/
SBI証券と楽天証券をiDeCoで徹底比較

まずは最初に、SBI証券と楽天証券のiDeCoについて比較していきます。
以下は、SBI証券と楽天証券のiDeCoに関する比較表です。
| SBI証券 | 楽天証券 | |
|---|---|---|
| 口座開設 手数料 |
2,829円(税込) | 2,829円(税込) |
| 口座管理 手数料 (掛金拠出がある場合) |
171円(税込) 運営管理手数料は0円 |
171円(税込) 運営管理手数料は0円 |
| iDeCo 対応銘柄数 (元本変動銘柄) |
37銘柄 | 35銘柄 |
| iDeCo 対応銘柄数 (元本確保銘柄) |
1銘柄 | 1銘柄 |
| 投資支援 サービス |
・「DC Doctor」の商品選びサポート ・投資情報メディア ・iDeCoお役立ちコンテンツ |
・iDeCoの動画セミナー ・トウシルでの情報発信 |
| サポート 体制 |
・iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスク 対応時間は制限なし 平日および土曜日、日曜日 (年末年始・祝日を除く) |
・フリーダイヤルでの専用コールセンター 対応時間 平日:10~19時 土曜日:9~17時 |
以下では、その違いを詳しく解説します。
\SBI証券でiDeCoを始める!/
1.SBI証券と楽天証券で手数料は変わらない
手数料については、SBI証券と楽天証券で変わりません。
まず加入時の手数料は税込で2,829円ですが、これはすべての金融機関で共通です。
次に口座管理手数料は、運用期間中に毎月発生するものとなります。
このうち加入者手数料105円(税込)と事務委託先金融機関の66円(税込)についても各金融機関で共通です。
なお金融機関によっては、このほかに運用管理手数料を徴収する場合がありますが、SBI証券と楽天証券はいずれも運用管理手数料0円となっています。
そのため資金を拠出している「加入者」の月額の手数料はどちらも月額171円(税込)です。(資金拠出がない場合は66円(税込))
最後に給付を受けるときには、振り込みのたびに440円(税込)がかかります。こちらも各金融機関共通です。
2.iDeCoの商品数はSBI証券のほうが多い
SBI証券と楽天証券の取扱銘柄数は、以下の通りです。
各カテゴリにおいて取扱銘柄数の合計はSBI証券のほうが多くなっています。
| SBI証券 | 楽天証券 | |
|---|---|---|
| 合計 | 38銘柄 | 32銘柄 |
| 国内株式 | 5銘柄 | 6銘柄 |
| 国内債券 | 1銘柄 | 2銘柄 |
| 国内REIT | 1銘柄 | 2銘柄 |
| 外国株式/国内外株式/国際株式 | 16銘柄 | 7銘柄 |
| 海外債券/国際債券 | 4銘柄 | 4銘柄 |
| 海外REIT/国際REIT | 1銘柄 | 1銘柄 |
| バランス型/ターゲットイヤー型 | 8銘柄 | 8銘柄 |
| コモディティ | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 元本確保型 | 1銘柄 | 1銘柄 |
それぞれのカテゴリで見ると、特に外国株式についてはSBI証券のほうがラインナップが充実している傾向です。
楽天証券の場合、全世界株、先進国、米国、新興国と主要カテゴリのインデックスファンド、アクティブファンドが3銘柄です。
SBI証券では、海外株式に投資するインデックスファンドだけで8銘柄あり、米国や先進国株式などは複数のインデックスファンドを取りそろえています。
また、海外株式へ投資するアクティブファンドも8銘柄とラインナップ豊富です。
特に、外国株式の銘柄ラインナップを重視するならSBI証券を選ぶのがおすすめといえます。
一方で、国内の株式や債券、REITに投資するファンドは、若干ながら楽天証券の方がそれぞれ多くなっています。
国内資産へ投資するファンドの選択肢の豊富さを優先するなら、楽天証券を利用するのも一案です。
\豊富な投資先から銘柄を選ぶなら!/
3.iDeCoのその他サービスは両方充実
iDeCoに関連するその他サービスは、SBI証券と楽天証券どちらも魅力的です。
例えばSBI証券では「DC Doctor」と呼ばれるロボアドバイザー機能があります。
このサービスは、基本情報を入力しいくつかの質問に答えるとその人に最適なiDeCoのポートフォリオを見ることができる機能です。
SBI証券は、取扱銘柄数が多いため、投資先に悩んでしまう場合もありますが、このシステムを使えば初心者でも投資先を決めやすいでしょう。
楽天証券は、情報コンテンツが豊富なのが魅力的です。
独自のiDeCoスタートガイドの配布やiDeCoの動画セミナーをおこなっているため、情報コンテンツを参考にすればスムーズにiDeCoでの運用を進められます。
\iDeCoの情報コンテンツが豊富!/
SBI証券でiDeCoをはじめるメリット

SBI証券でiDeCoをはじめるメリットは主に以下の3つです。
1.銘柄豊富で投資先を柔軟に選べる
SBI証券のiDeCoの大きな強みは、38銘柄の豊富な銘柄ラインナップです。
投資する国や株、債券といった資産クラスを、自分の投資意向に沿って柔軟に選べます。
2.DC Doctorで簡単に投資先を決められる
またDC DoctorというiDeCo専用のロボアドも便利です。
リスク許容度や運用目標をもとに、最適なポートフォリオを提案してもらえます。
さらに運用期間中は、リバランスの提案までおこなってくれる便利な機能です。
3.信託報酬の低いインデックスファンドを複数扱っている
最後に信託報酬が低いインデックスファンドを複数扱っているのも特徴です。
例えば信託報酬が年間0.10%以下のファンドとして、次の銘柄があります。
| 銘柄 | 信託報酬(税込) | 投資先 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) |
0.05775%以内 | 国際株式/グローバル |
| eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) |
0.09372%以内 | 国際株式/北米 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド |
0.09889%以内 | 国際株式/グローバル |
| eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス |
0.09889%以内 | 国際株式/グローバル |
コストを抑えて運用するうえでも、SBI証券のiDeCoはおすすめです。
\iDeCoを低コストで運用するなら!/
SBI証券で始めるiDeCoの注意点
SBI証券でiDeCoを始める場合、次の点には注意が必要です。
1. 給付の自由度が低い
SBI証券のiDeCo固有の注意点としては、給付時の自由度が低いことがあげられます。
SBI証券の場合は受給期間を5年、10年、15年、20年、年間の支給回数を1回・2回・4回・6回のなかから選択する仕組みです。
証券会社によっては、1年刻みで支給期間を指定するなど、より柔軟に選べる先もあります。
2. 手数料がかかる
2点目の注意点は、iDeCoに共通するものですが、手数料については、証券会社が水準を決められる運営管理手数料が0円なだけで、すべての手数料が無料ではありません。
その点に注意しましょう。
3. 60歳まで引き出せない
また、他の金融機関を利用しても同様ですが、原則として60歳まで引き出せない点も忘れてはいけません。
楽天証券のiDeCoにおけるメリット

続いては、楽天証券のiDeCoのメリットを解説します。
楽天証券でiDeCoを始めるメリットは、次の3つです。
1. 動画での情報コンテンツが豊富
楽天証券では、iDeCoに関してさまざまなセミナー動画を発信しています。
動画を参考にすれば、初めてiDeCoにチャレンジする人でも、戸惑うことなく運用できるでしょう。
2. 資産管理がしやすい管理画面
また一目で資産残高やポートフォリオなどが確認できる見やすい管理画面も特徴です。

楽天証券は、証券IDとiDeCoのIDが同一です。
証券口座のWebサイトのなかでiDeCoの管理ができるので、普段の証券投資と同じ感覚でiDeCoの口座管理ができます。
3. 楽天銀行との連携で引き落としがスムーズ
楽天銀行に口座を解説し楽天証券と連携をすれば、口座からiDeCoの掛金を自動引き落としすることが可能です。
また、これはiDeCoには直接的には関係ありませんが、楽天銀行に口座を開設し、楽天市場、楽天books、楽天ペイなどの楽天グループのサービスを利用することで、楽天ポイントが貯まります。
その楽天ポイントは、楽天証券で投資に使うことができるので、より効率よく資産運用をおこなうことができます。
\初心者でもわかりやすい!/
楽天証券で始めるiDeCoの注意点
楽天証券でiDeCoを始める場合の注意点は、以下の2つです。
1.残高や拠出額では楽天ポイントが貯まらない
楽天ユーザーが注意したいのは、iDeCoの運用で楽天ポイントを貯める手段は限定的であることです。
毎月の拠出額や残高などに応じてポイントが付与される制度はありません。
楽天銀行を引き落とし口座にすれば1回の取引回数とカウントされて毎月1~3ポイントがつきますが、証券口座と比べるとインパクトは小さいでしょう。
2.選べる銘柄の選択肢が少ない
またSBI証券などと比較したときに投資先の選択肢が少ない点にも注意が必要です。
その他の注意点は、iDeCoに共通するものですが、楽天証券でiDeCoを始める際にも押さえておいてください。
SBI証券と楽天証券でiDeCoをやっている人の口コミ・評判
ここからは、SBI証券と楽天証券の口コミを紹介します。
実際に利用している人の口コミを知ることも、口座を開設する大きな判断材料になることでしょう。
SBI証券でiDeCoをやっている人の口コミ・評判
SBI証券証券を実際に利用している人の口コミには以下のようなものがあります。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ/提供情報の充実度/取引のしやすさ/システムの安定性
評価:5
年齢:45歳~49歳
性別:男性
イートレードの頃から使用していることもあって、とても使いやすい。
過去にマネックス、松井証券、株ドットコム、楽天証券などのネット証券を利用してきたが、手数料、投信数、ポイント付与など、全ての点で最高レベルであるため、ここにして損はない。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ
評価:4
年齢:55歳~59歳
性別:女性
高配当株投資、積立NISA、iDeCo、たまにIPO購入を行なっています。
単元未満株も購入できるので助かっています。
操作はPCからなので、特に使いにくさは感じません。
今後の希望としては、ポートフォリオの表示項目をカスタマイズしたい、単元未満株も指し値で注文したい、以上2点が改善されれば言うことなしです。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ/取引のしやすさ
評価:4
年齢:35歳~39歳
性別:男性
日本株については概ね満足しており、時間外取引についても操作は分かりやすい。積立購入等についてもクレジットカード支払いやポイントでの購入等も徐々に充実し、今後とも期待している。
一方で米国株について、良くシステム障害が発生し取引ができなくなることがある印象がある。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ/利用特典の魅力/取引のしやすさ
評価:5
年齢:30歳~34歳
性別: 女性
少額でも始められることがとても良い。
アプリも初心者にも使いやすく、見やすい。
アプリの通知機能の種類がやや少ない、Androidの場合、変動などの通知が鳴らないときがあることがやや残念。
色んな投資に挑戦できるのも良い。
\iDeCoのDC Doctorが好評!/
楽天証券でiDeCoをやっている人の口コミ・評判
楽天証券を実際に利用している人の口コミには、以下のようなものがあります。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ
評価:5
年齢:35歳~39歳
性別:女性
NISA口座と特定口座で使用しています。
メインは投資信託と日本株、すこし海外ETFですが、興味がある商品(最近は高配当ETFを探しています)でも問題なく取引できるので助かっています。
アプリは株しか使っていませんが、投資信託が一番投資金額が大きいのでそれも一つのアプリで使えるようになって欲しいです。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ/利用特典の魅力/取引のしやすさ
評価:5
年齢:45歳~49歳
性別: 男性
楽天証券一番の魅力はマネーブリッチ(楽天銀行との連携)だと思います。普段資金は銀行にあり、タイミングよく増資でき、譲渡益を支出にまわすことも簡単になりました。証券口座に資金を準備することや振込手続きが不要になったことは大きいです。
この証券会社を選んだ理由:取引のしやすさ
評価:4
年齢:50歳~54歳
性別: 女性
初めて開設した証券会社でしたが、初めてでも、安心して手続きができました。特に、困ったような事もありません。やはり楽天のクレジットカードで投資出来るのが魅力的です。クレジットカードのポイントも稼げるのが良いですよね。
この証券会社を選んだ理由:手数料の安さ
評価:4
年齢:35歳~39歳
性別: 男性
投資をスタートした時、最初に選んだ証券会社が楽天証券でした。
楽天と紐づいた各種ポイントサービスもさることながら、5年ほど利用していますがシステム障害等もなく、スムースに取引ができています。
取扱商品も多く、私は国内株式の他に米国株式、アジア株式、投資信託等にも投資しています。
ウェブページの作りがシンプルで、ウェブ上で操作に迷う事も少ないかと思います。
\スマホでiDeCoを管理するなら!/
SBI証券と楽天証券、iDeCoをはじめるならどっち?
SBI証券と楽天証券では、どちらでiDeCoを始めるのがよいでしょうか。
この記事の結論を先にお伝えしますが、各社でおすすめなのは以下のような人です。
| SBI証券が おすすめな人 |
・投資の中級者でポートフォリオにこだわりたい人 ・自分で最適な投資先を選ぶのが困難な人 ・運用コストをできるだけ抑えたい人 |
|---|---|
| 楽天証券が おすすめな人 |
・iDeCoや投資について勉強しながら投資していきたい人 ・わかりやすい操作画面で管理したい人 ・スマホでiDeCoの資産管理したい人 |
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
SBI証券がおすすめな人
SBI証券のiDeCoを利用するのがおすすめな人は次の通りです。
以下で詳しく解説します。
・1.投資の中級者でポートフォリオにこだわりたい人
SBI証券は投資できる銘柄が豊富なので、自分の投資意向に応じて柔軟にポートフォリオ構築が可能です。
アジア株式のファンドや、コモディティ全般に投資するファンドまでそろっているのはSBI証券ならではといえるでしょう。
またDC Doctorを活用すれば投資家の属性や資産状況、リスク許容などに応じて最適なポートフォリオを組んでもらえます。
・2.自分で最適な投資先を選ぶのが困難な人
自分にとって最適な投資ファンドがわからない人でも、SBI証券はおすすめです。
DC Doctorとは、SBI証券が用意しているWebアプリケーションでiDeCoでの資産形成のサポートをしてくれます。
ニーズに合ったポートフォリオ提案、運用商品選びのサポートなど複数の機能があり、簡単な質問に回答していくとあなたに合わせた運用の提案をしてくれるアプリケーションです。
・3.運用コストをできるだけ抑えたい人
iDeCo自体の手数料が低く、さらにiDeCoにおいて信託報酬0.10%未満のファンドを4つも取り扱うSBI証券は、コストを最小化して運用したい人にも適しています。
\DC DoctorでiDeCoの銘柄選びも簡単!/
楽天証券がおすすめな人
楽天証券がおすすめな人は下記に当てはまる人です。
以下で詳しく解説します。
・1.iDeCoや投資について勉強しながら投資していきたい人
楽天証券は、iDeCoオリジナルの動画や、楽天の投資情報メディアである「トウシル」など、金融市場や投資に関する情報コンテンツが豊富です。
動画を参考にすれば、投資やiDeCoについて学びながら運用を始められるでしょう。
・2.わかりやすい操作画面で管理したい人
また複雑な操作画面を苦手とする人にも楽天証券がおすすめです。
管理画面がシンプルでわかりやすいため、操作に困ることは少ないでしょう。
・3.スマホでiDeCoの資産管理したい人
最後に楽天証券では、スマホオリジナルのiDeCo管理画面があることも特徴です。

普段パソコンを開く頻度が少なくスマホで管理を完結させたい人にもおすすめです。
\スマホでiDeCoを管理するなら!/
SBI証券と楽天証券のiDeCoについてよくある質問
最後に、SBI証券や楽天証券のiDeCoに関するよくある質問を4つ紹介します。
Q1. SBI証券のイデコは口座引き落としできますか?
証券口座からiDeCoの掛金を引き落とすことはできないため、掛金引落金融機関を指定しなければいけません。
Q2. SBI証券のiDeCoの受け取り手数料はいくらですか?
60歳以降に給付金を受け取る場合、1回の振り込みにつき440円の手数料が発生します。
一時金で受け取った場合、手数料は1度だけですが、年金で受け取る場合は都度手数料がかかるため、押さえておきましょう。
Q3. SBI証券の投信マイレージはiDeCoの対象ですか?
SBI証券の投信マイレージは、所定の投資信託の保有残高に応じて毎月ポイントが貯まるサービスですが、iDeCoでの運用資産は対象外です。
投信マイレージを活用したい人は、証券口座のほうで投資信託を購入しましょう。
Q4. iDeCoの引き落とし口座はどこでもいいですか?
引落金融機関には、例えば以下のような先が選べます。
- 都市銀行
- 地方銀行
- ゆうちょ銀行
- 一部の信託銀行
- 信用金庫
- 労働金庫
- 信用組合
- 農業協同組合など
一部のネット銀行および信託銀行は引き落としに対応していない場合があるで注意してください。
まとめ
SBI証券、楽天証券ともに、どちらも魅力的なネット証券です。
iDeCoをはじめるにあたっては、ネット証券の特性と自分が何をネット証券に求めているかが重要になってきます。
それが本記事を読み、理解できたのではないでしょうか。
この機会にSBI証券、楽天証券を利用し、iDeCoをはじめてみてはいかがでしょう。
\楽天証券でiDeCoを始める!/
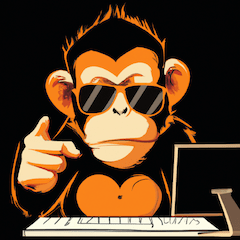
株式投資、FX、ノックアウトオプションを15年以上継続している現役トレーダー
株式投資、FX、ノックアウトオプションを15年以上継続している現役トレーダー。年間数百万の利益を7年間継続している。
多くの証券会社やFX会社で実際に口座開設し、取引してきた経験から業者比較やトレードノウハウなどの執筆を行うライターとしても活動中。