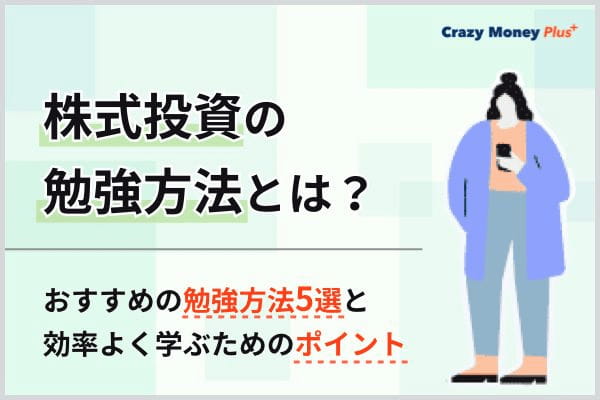株式投資において大きな損失を避けて着実な収益獲得を目指すためには、勉強をすることが大切です。
ひとくちに株式投資の勉強といっても本やWebサイト、動画などさまざまな株式投資に関するコンテンツがあります。
この記事では、株式投資の勉強方法のポイントやおすすめの勉強方法を紹介します。
紹介した方法で勉強を始めて自身の株式投資に役立ててください。
- 書籍や動画、Webサイト、セミナーやアプリなど多様な勉強方法がある
- それぞれのコンテンツの特徴をふまえて、自分に合った方法で勉強するのが大切
- 勉強をしっかりと行えば、損失を抑えながら効率よく投資ができるようになる
初心者におすすめ投資の勉強方法5選
「投資に興味はあるけれど、何から始めていいかわからない」そんな初心者の方に向けて、無理なく学べるおすすめの勉強法を5つご紹介します。
書籍で基礎を固める方法から、YouTubeやアプリを活用した手軽な学習まで、ライフスタイルに合わせて選べる手段は豊富です。
まずは自分に合った方法で、楽しみながら一歩を踏み出してみましょう。
知識を身につければ、投資はもっと身近で心強い味方になります。
1. 本・雑誌で学ぶ|体系的な知識をじっくりインプット
投資初心者にとって、基礎から順を追って学べる「本」や「雑誌」は心強い教材です。
投資の仕組みや資産運用の基本、リスク管理まで体系的に解説されているため、全体像をしっかり理解できます。
特に書籍は情報の信頼性が高く、自分のペースで何度も読み返せるのも魅力です。
まずは以下の本からスタートし、知識を段階的に深めていくとよいでしょう。
世界一やさしい 株の教科書1年生
「世界一やさしい 株の教科書 1年生」は、個人投資家が利益を得るためのポイントを3つにまとめて解説しています。
「5秒で選び、5分で取引、5銘柄だけ保有」をおすすめする株式投資入門書として人気です。
堅苦しくない文体で楽しく読み進められるにもかかわらず、株式投資に必要な理論をしっかりと理解できる内容となっています。
「世界一やさしい 株の教科書 1年生」は、発売から10年以上経ちますが今も読み続けられる名著で、Amazonでの評価は4.2(2025年6月25日現在)と高いです。
読むことで、株式投資において実践すべきルールを手軽に身につけられるでしょう。
年率10%を達成する! プロの「株」勉強法
「年率10%を達成する! プロの「株」勉強法」は、株式投資で安定的な成果を目指す個人投資家に向けた実践的な指南書です。
著者の栫井駿介氏が東京大学で学んだ金融理論と、投資顧問会社を経営するなかで身につけた投資スキルを組み合わせて、金融のプロが実際に行っている手法をわ 分かりやすく体系的に解説しています。
投資スキルをさらに高めて、年利回り10%を目指すうえの知識やスキルを学べるのが特徴です。
Amazonでは投資関連の書籍の中でも高い評価が高く4.0(2025年6月25日現在)です。
短期的なテクニックではなく、長期で資産を築くための確かな視点が身につく一冊といえるでしょう。
>>Amazon 年率10%を達成する! プロの「株」勉強法
ダイヤモンドZAi(ザイ)
初心者でも読みやすい平易な文章と図表・イラストを駆使し、株式・投信・FX・節税・優待まで幅広く網羅しています。
「ダイヤモンドZAi(ザイ)」は、投資情報に加えて新しい制度の説明や投資理論、テクニックの解説記事なども豊富なため、勉強するツールとしても有効です。
プロの分析や個人投資家の実例、最新の日本株・米国株診断、チャート講座、優待・高配当ランキング、NISA・金投信などの実践情報が盛り込まれています。
専門書と組み合わせて勉強すれば、本の知識を補いさらに最新情報にアップデートすることもできます。
自分のレベル感や勉強目的をふまえて、自分に合った本・雑誌で勉強を進めましょう。
2. YouTubeで学ぶ|無料で楽しく、隙間時間を活用
YouTubeには、投資の基礎から具体的な銘柄分析まで学べる動画が豊富にあります。
映像と音声で解説されるため理解しやすく、スマホひとつで通勤中や休憩時間など隙間時間を活用できるのが特徴です。
なかには、元銀行員や投資歴の長い個人投資家が運営する信頼性の高いチャンネルもあります。
視覚的に学びたい人にとって、YouTubeは強力な学習ツールといえるでしょう。
株式投資の勉強には、次の3つのYouTube動画がおすすめです。
バフェット太郎の投資チャンネル
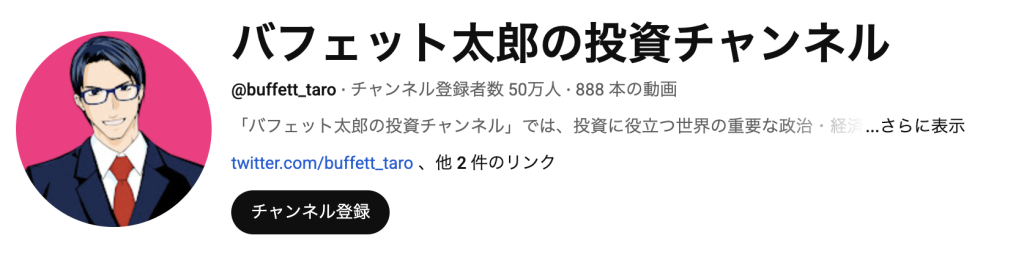
「バフェット太郎の投資チャンネル」は、登録者約50万人・総再生数9,400万回超の人気YouTubeチャンネルです。
投資家バフェット太郎氏が運営しており、米国株を軸とした高配当戦略を中心に、世界の経済とマーケット動向を厳選し、平易な言葉とグラフ・チャートでわかりやすく解説しています。
チャンネルでは毎週月・水・土の18時に動画を公開し、最新では「米国株売るタイミング」や「次の投資ブーム」など、実践的で視聴者の関心を刺激するテーマをカバーしています。
バフェット太郎氏自身は20代から投資を開始し、米国株高配当投資に学び、数年間で数億円の金融資産を築いた実績を持つインフルエンサーです。
冷静かつ実践的なアドバイスで、「お金がお金を生む」自律的な資産形成を目指す人に最適な学びの場となっています。
たぱぞう投資大学
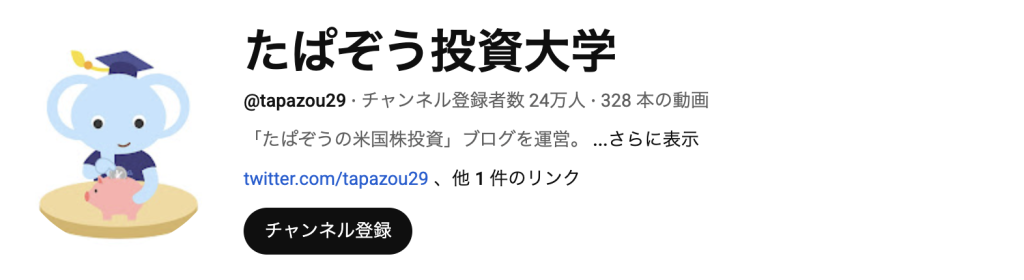
画像引用:YouTube たぱぞう投資大学
「たぱぞう投資大学」は、月間100万PV超の人気ブログ「たぱぞうの米国株投資」を運営するたぱぞう氏が発信する、登録者約24万人のYouTubeチャンネルです。
米国株やETFを中心に、「誰もができる投資術」をアニメーションや図解でわかりやすく解説しています。
iDeCo、NISAなど制度の活用法から、SCHD・VYM・HDV・IVVなど人気高配当ETFの比較・組み合わせ術、FXでのお得な米ドルの買い方など、幅広くカバーしています。
「たぱぞう投資大学」は、初心者〜中級者が体系的に投資を学び、実践に活かせるコンテンツが揃っています。
初心者から資産拡大を目指す人まで、理論と実践をバランスよく学べる貴重な学び場です。
BANK ACADEMY / バンクアカデミー
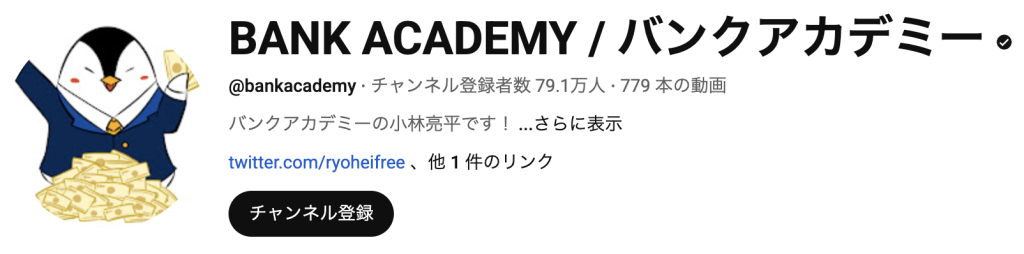
画像引用:YouTube BANK ACADEMY / バンクアカデミー
「BANK ACADEMY/バンクアカデミー」は、三菱UFJ銀行出身の元銀行員でYouTubeチャンネルを運営する小林亮平氏が運営する、資産形成・投資入門チャンネルです。
チャンネル登録は約79万超で、動画では、iDeCo・NISA・全世界株式・高配当ETF・年金・社会保険・楽天経済圏など、制度運用からポートフォリオ構築まで、イラスト・図解を駆使しながら初心者にもわかりやすく丁寧に解説しています。
わかりやすさと視覚的な説明に重きを置くスタイルと、SNS経由での視聴者対応を通じた双方向性が魅力です。
小林氏の銀行員時代の専門知識と金融教育への強い思いを背景に、超初心者から中高年層まで幅広い層に支持されている「やさしいお金の学校」といえるでしょう。
>>YouTube BANK ACADEMY / バンクアカデミー
3. Webサイトで学ぶ|最新情報や経験談に触れる
投資情報をタイムリーにキャッチしたいなら、Webメディアがいいでしょう。
証券会社が運営する公式サイトでは、経済ニュースや相場分析などの専門的な情報や経験談を無料で公開しています。
実践的な視点を学べるのは大きなメリットです。
株の勉強の勉強をするなら、次の3つのWebサイトがおすすめです。
トウシル

画像引用:トウシル
楽天証券が運営する「トウシル」は、個人投資家向けに株式、投資信託、FX、iDeCo、NISAなど幅広い金融リテラシーを、アナリストや専門家による記事・動画でわかりやすく届けるメディアです。
初心者向けに「指値・成行注文の基本」から、最新の「ソニー決算分析」などの実践的な業界解説まで網羅しています。
記事には図表・動画リンクが豊富に組み込まれており、視覚的にも理解しやすい構成が魅力です。
また、週刊レポートやテーマ別特集、専門家インタビューなど旬のトピックも定期発信しており、楽天証券の分析力と幅広いテーマカバレッジにより、初心者から上級者まで資産形成に役立つでしょう。
毎日複数本の記事が更新されるなど、更新頻度が高く豊富な最新情報を入手できるのも魅力といえます。
楽天証券について詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
楽天証券のメリットやデメリットは?つみたてNISAにおすすめな理由や口コミ・評判も
>>トウシル公式サイト
>>トウシル YouTube公式チャンネル
\トウシルを運営している楽天証券で株式投資しよう!/
SBI証券 投資情報メディア

画像引用:SBI証券 投資情報メディア
ネット証券最大手のSBI証券が運営する公式投資情報メディアは、これから資産形成を始める初心者から経験豊富な投資家まで勉強になる情報が揃っています。
NISAやiDeCoの制度解説、国内外の株式・投資信託の情報はもちろん、プロのアナリストによる市況分析レポートや今後の見通し、日々のマーケット速報も網羅しています。
専門家のコラムや動画セミナーといった多様な形式で、複雑な投資の知識や経済ニュースをタイムリーに、かつ図解を交え分かりやすく解説しています。
SBI証券が運営する公式投資情報メディアは信頼性の高い情報源として活用できることでしょう。
SBI証券について詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
SBI証券で口座開設する手順を解説|メリットや利用者の口コミも紹介
>>SBI証券 投資情報メディア
>>SBI証券公式チャンネル
\SBI証券はネット証券最大手/
マネクリ

画像引用:マネクリ
マネクリはマネックス証券が運営する投資情報メディアです。
投資初心者から上級者まで、あらゆる投資家の資産形成を強力にサポートするコンテンツが豊富です。
最大の特徴は、マネックス証券の創業者である松本大氏やイェスパー・コール氏をはじめとする、社内外の著名な専門家・ストラテジストによる豪華な執筆陣です。
金融市場の動向や今後の見通し、さらには資産運用やライフプランニングの考え方まで、タイムリーかつ先見性のある情報を、信頼性の高い専門的な視点から得られるメディアです。
マネックス証券について詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
マネックス証券のメリットとは?ドコモとの提携によるメリットも解説
>>マネクリ公式サイト
>>マネックス証券YouTube公式チャンネル
\マネックス証券はクレカ積立の還元率が1.1%!/
4.セミナーで学ぶ|専門家から直接学び、疑問を解消
投資セミナーでは、証券会社のプロやファイナンシャルプランナーから直接学ぶことができます。
基礎講座からNISAやiDeCoなど制度活用の実践講座まで、幅広いテーマが揃っています。
対面やオンライン形式があり、自分に合ったスタイルで参加可能。その場で質問できるため、疑問点をすぐに解消できるのも大きな魅力です。
短期間で集中して学びたい人に向いています。
松井証券の投資セミナー
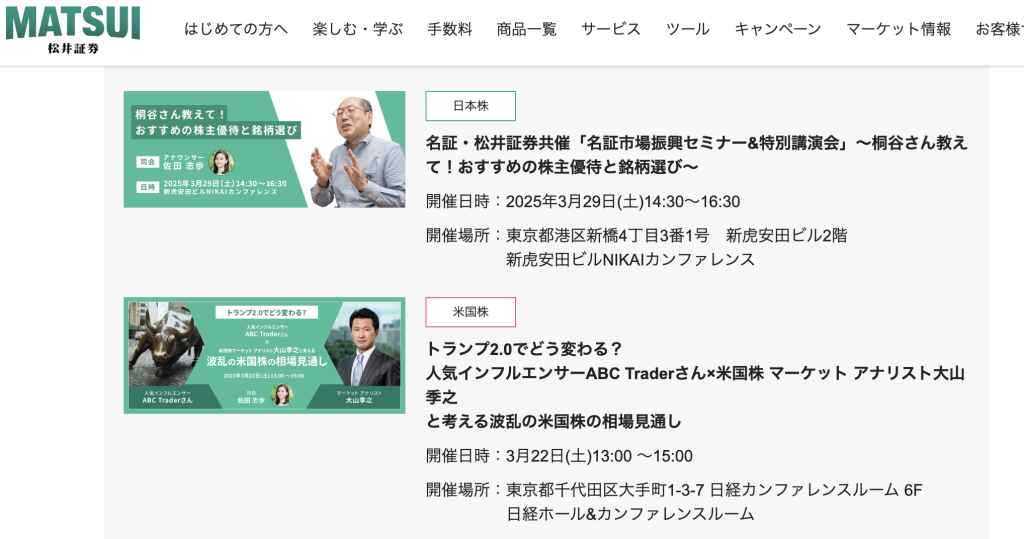
画像引用:松井証券 セミナー情報
松井証券のセミナーは、投資初心者から経験者まで幅広い層を対象にしています。
株式投資や為替、経済指標の読み解き方など、多様なテーマを専門家がわかりやすく解説します。
オンライン配信を中心に、誰でも自宅から参加できるのが特徴で、実践的な知識を深められる内容となっています。
すべて無料で提供されており、投資力を高めたい方にとって非常に有益な学びの場といえるでしょう。
松井証券について詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
松井証券のメリットとデメリットは?松井証券が向いている人まで解説
>>松井証券セミナー情報
>>松井証券YouTube公式チャンネル
\松井証券のセミナーは有料級の情報が万歳/
マネックス証券の投資セミナー

画像引用:マネックス全国投資セミナー
マネックス証券のセミナーは、投資家の知識向上を目的とした無料の学習イベントです。
オンライン配信と全国各地での対面開催を通じて、最新のマーケット情報や投資戦略をわかりやすく解説します。
専門家による実践的な内容が特徴で、初心者から上級者まで幅広い層に対応しています。
口座保有者向けのサービスとして提供されており、自宅や現地で気軽に参加できるのも魅力です。
\全国でセミナーを開催/
TAPPの投資セミナー
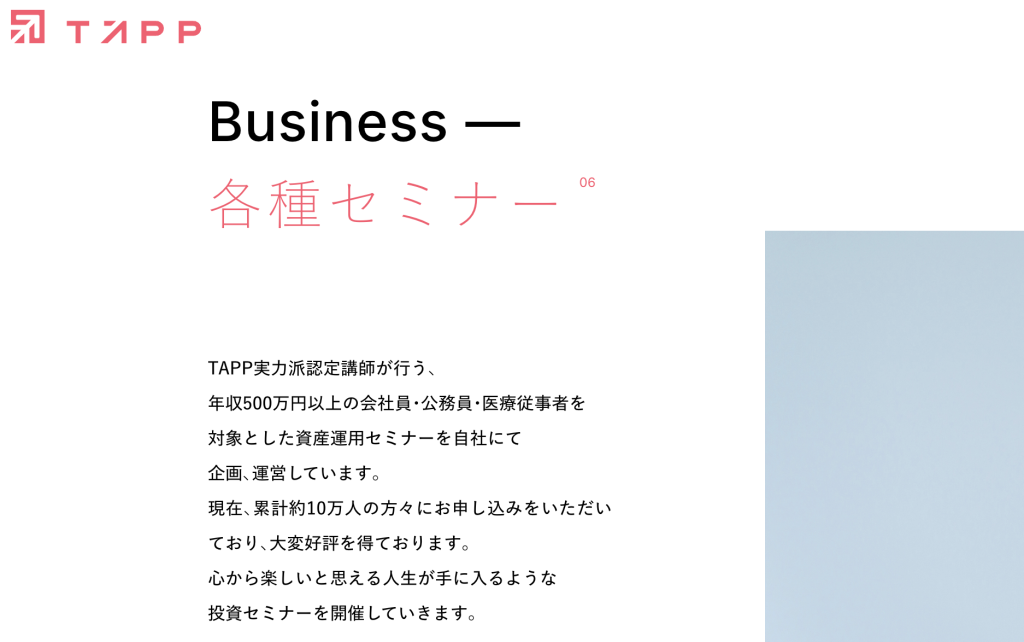
画像引用:TAPP Business 各種セミナー
株の勉強には、TAPPの投資セミナーがおすすめです。
株式会社TAPPは、株式投資や不動産投資を軸に投資関連の豊富な情報発信を行っています。
その一環として年収500万円以上の会社員・公務員・医療従事者をターゲットとした資産運用セミナーを継続的に実施しています。
FPによる経済動向や市況の説明、投資銘柄選びなど、株式投資や資産運用全般に役立つ知識を習得可能です。
累計で10万人以上が受講している実績のあるセミナーで、受講者からも高い評価を得ています。
TAPPのセミナーラインナップや今後の予定については、以下のページを参考にしてください。
5. アプリで学ぶ|ゲーム感覚で実践力を養う
最近は、投資を楽しく学べるスマホアプリも充実しています。
クイズ形式で金融知識を身につけたり、仮想の株取引を体験したりと、ゲーム感覚で実践的なスキルが養えます。
初心者向けに設計されているため、難しい用語や操作も自然と覚えられるのが魅力です。
日常のスキマ時間を使って気軽に取り組めるため、忙しい人や飽きっぽい人にもぴったりの学習方法です。
株の勉強には、次の3つのアプリがおすすめです。
moomoo

画像引用:moomoo証券
「moomoo」はmoomoo証券(ムームー証券)が運営する投資アプリです。
moomoo証券は、香港に拠点を置くフートゥー・ホールディングス傘下で、日本国内では2022年に旧ひびき証券を改称しサービス提供を開始しています。
moomoo証券のアプリである「moomoo」は、チャート機能やテクニカル分析の機能が充実しています。
デモトレード機能もあるため、チャート分析の使い方を習得しながら、株式投資を練習するのに適したアプリです。
日本株のほか米国株の売買も可能なので、日米双方の株式投資を検討している方に向いています。
スマホはAndroid、iPhone、PCはWindows、iOSに対応しています。
トウシカ

画像引用:グリーンモンスター株式会社 トウシカ
トウシカは長期積立投資による老後の資産形成をテーマとした投資勉強用のアプリです。
アプリの軸は、投資シミュレーションやゲーム機能で、実際のお金を消費することなく投資の練習をして投資のテクニックを学べます。
また老後の必要資産額の分析・診断機能やNISA・iDeCoなど、株式をはじめとした資産運用に関するコラムなど、豊富な機能が備わっています。
>>App Store トウシカ
>>Google play トウシカ
Yahoo!ファイナンス

画像引用:Yahoo!ファイナンス
Yahoo!ファイナンスは国内最大級の金融情報サイトで、初心者から上級者まで幅広いユーザーに株式投資の情報収集ツールとして活用されています。
株に関するさまざまな情報が得られるほか、証券会社と連携して保有資産情報や取引履歴を連携・確認できる機能があります。
さらには、お気に入り銘柄を登録して簡単にチェックする機能など、投資に役立つ豊富な機能を兼ね備えているのが特徴です。
株式投資の知識に関する記事による情報発信も豊富で、勉強と投資分析を一つのアプリで進められます。
>>App Store Yahoo!ファイナンス
>>Google play Yahoo!ファイナンス
株式投資の勉強をするメリット
株式投資の勉強をすると、次のようなメリットが期待できます。
これらのメリットについて詳しく紹介していきます。
1. 効率よく株式投資を進められる
株式投資の勉強をすれば、効率よく投資を進められるようになります。
ここでいう「効率よい投資」とは、過度なリスクを取ることなく投資目的に合ったリターンを追求できるようになることです。
株式市場は、多くの要因で変動し、その動きを完璧に予測するのは困難です。
しかし基礎的な知識を持っていることで、市場の動向を理解して自分の投資目的に合った投資銘柄の選別や資産構成の構築が可能になります。
経済や市場の仕組みを理解しておけば、相場が下落する局面でも焦って非合理な行動を取らずに済むでしょう。
また相場下落時の損失を抑制しつつ、長期で着実なリターンの追求が可能になります。
さらに市場のトレンドを理解したり、集めた情報をもとに市場を分析したりして最適な投資戦略を立てられるようになるでしょう。
2. 大きな損失を避けながら投資できるようになる
株式投資の専門知識やノウハウを習得することで、損失リスクを抑えた投資が可能になります。
株式投資には、損失リスクがつきものです。想定外の市場変動が起これば、大きな損失を被る場合もあります。
損失を完全に避けることはできませんが、株式投資に関して適切な知識を培っておけば、損失をできるだけ抑制する適切な行動を取ることが可能になるでしょう。
例えば一時的な相場変動に動揺して、不必要な売買を繰り返す心配がなくなります。
銘柄について分析する能力を身につければ、株価下落のリスクが高い銘柄を避けられる可能性が高くなるでしょう。
保有銘柄におけるリスク分散の重要性や仕組みを理解すれば、ポートフォリオ全体で損失を抑制する投資戦略をとれるようになります。
相場悪化時の損失を抑制できれば、その後の市場回復局面でより早くパフォーマンスを改善できるでしょう。
銘柄選別や分散投資のスキルを身につけることで、大きな損失を避けつつ、長期的に安定した利益を得られるようになるのです。
3. 経済や金融商品への理解が深まる
株式投資に関する勉強を通じて、経済全般や金融商品に対する理解を深めることが可能です。
企業の業績や経済の動向、世界情勢の変化などが株式市場の主たる変動要因となります。
ときには、債券やコモディティなど、ほかの資産の市場動向が影響を与える場合もあるのです。
そのため株式投資の知識を深めれば、その過程で経済情勢やほかの金融商品の情報収集、トレンドの知識も習得できます。
また経済と金融市場が、どのように結びついているのかも理解できるでしょう。
経済や金融商品に対する知識は、投資だけでなく家計管理やキャリア形成など、さまざまな場面で役立ちます。
株式投資の勉強をするときの注意点
株式投資の勉強を進める際には、次のような点に注意しましょう。
それぞれの注意点を理解して、効率よく知識やノウハウを習得してください。
1. 知識の習得に時間がかかる
株式投資の知識を習得するには、一定の時間がかかるので、地道に勉強をしていく努力が必要です。
焦らずじっくりと基礎を固めることで、自分に合った銘柄を選び、適切なタイミングで売買する判断力が身につきます。
高リスクな投資や不要な取引による損失を避け、安定した成果を目指すためにも、短期的な利益を追わず中長期的な視点で学習を続けることが大切です。
2. 誤った知識を習得するリスクがある
書籍を購入したり、インターネット検索をすれば投資情報は簡単に手に入ります。
しかし、なかには誤った内容や偏った意見、悪質な勧誘も紛れています。
知識が不十分なまま鵜呑みにすると、大きな損失や詐欺被害に繋がるリスクがあります。
極端な高リターンをうたう情報や、自身のレベルに合わない上級者向けの内容は避け、金融分野で確かな実績と評価を持つ、信頼できる情報源を見極めて活用することが大切です。
3. レベルが合った方法で勉強する
株式投資の勉強は、自分の知識レベルに合った方法を選ぶことが大切です。
初心者がいきなり高度な内容に挑むと挫折しやすく、経験者が基礎ばかりでは成長が止まってしまいます。
まずは投資の仕組みや用語を理解し、次に分析手法や戦略を学ぶなど、段階的にレベルアップすることが重要です。
書籍やセミナー等を組み合わせると、より効率的に知識を深められます。
投資初心者が知っておくべき基本
投資を始めるにあたって、いきなり複雑な知識を詰め込む必要はありません。
大切なのは、「長期」「分散」「積立」という3つの基本を理解し、実践することです。
これらはプロの投資家も重視する王道の考え方であり、初心者にとっても資産を安定的に育てるための土台となります。
ここでは、それぞれの考え方をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 長期投資
長期投資とは、数年から十数年という長い期間にわたり資産を運用する方法です。
相場の上下に一喜一憂せず、企業や経済の成長による利益をじっくりと享受するのが特徴です。
短期的な価格変動に左右されにくく、複利効果も期待できるため、資産が効率的に増えやすい点が魅力です。
特に初心者にとって、頻繁な売買を避けることで手数料負担も減り、精神的なストレスも少なくて済みます。
着実に資産を育てたい人には、長期投資は理想的なスタイルといえるでしょう。
2. 分散投資
分散投資とは、資産を複数の銘柄や地域、資産クラス(株式・債券・不動産など)に分けて投資することで、リスクを抑える手法です。
たとえば一つの銘柄が値下がりしても、他の資産が値上がりしていれば、全体のダメージを軽減できます。
投資対象が偏ると、大きな損失を受けやすくなるため、安定的な運用には分散が欠かせません。
初心者は特に、インデックスファンドやバランス型ファンドなどを利用することで、簡単に分散投資を実現できます。
リスクとリターンのバランスを整える基本的な考え方です。
3. 積立投資
積立投資は、毎月一定額をコツコツと投資していく方法で、時間を味方につけた資産形成に適しています。
相場が高いときは少なく、安いときは多く買える「ドルコスト平均法」により、購入価格を平準化できるのが大きな特徴です。
これにより、高値掴みのリスクを減らしながら長期的な資産の増加を目指すことができます。
初心者でも始めやすく、自動積立設定で無理なく継続できるのもメリットです。
証券会社によってはクレジットカードでの積み立てができ、ポイントが貯まります。
そのポイントを利用しての再投資も可能なので、効率的に資産を増やすことができるでしょう。
投資を習慣化し、将来のために安定的に資産を築く第一歩としておすすめの方法です。
初心者はNISAのつみたて投資枠で投資信託を始めるのがおすすめ
投資を始めたいけれど、「何を選べばいいのか分からない」「損をしたら怖い」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな初心者には、NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」で投資信託を始めるのがおすすめです。
運用益が非課税のうえ、少額からコツコツ積み立てできるので、リスクを抑えながら投資に慣れることができます。
まずは制度の基本と、投資信託の特徴をわかりやすく解説していきます。
1. NISAとは

画像引用:金融庁 NISA公式サイト
NISA(ニーサ)とは、「少額投資非課税制度」のことです。
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAを使えばその税金がかからず、利益をそのまま受け取ることができます。
つまり、資産を効率よく増やすための心強い制度です。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、それぞれ使い方や対象商品が異なります。
年間の投資上限額が決まっているものの、誰でも無料で利用できる制度で、特に投資初心者には最初の一歩として活用しやすい選択肢です。
関連記事
NISAのメリット・デメリットとは|5年以上利用する個人投資家が解説
2. つみたて投資枠と成長投資枠の違い
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があります。
つみたて投資枠は、年間120万円まで、一定の基準を満たした長期積立向けの投資信託などに投資できる枠です。
少額から毎月コツコツ積み立てていくスタイルで、初心者にも扱いやすく、リスクを抑えながら資産を増やすことが可能です。
一方、成長投資枠は年間240万円まで使え、株式や幅広い投資信託などにも投資できます。
自由度は高いものの、リスクも大きくなりやすいため、経験を積んでから活用するのがおすすめです。
関連記事
NISAのつみたて投資枠で購入する銘柄は1つだけいい理由を解説
3. 投資信託とは
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金を一つの大きな資金として、運用のプロが株や債券などに分散投資してくれる金融商品です。
つまり、自分で個別の株を選ばなくても、少額からさまざまな資産に投資できるのが特徴です。
分散投資ができることでリスクを抑える効果があり、投資初心者にとっては安心して始めやすい選択肢といえます。
また、毎月一定額を積み立てることで、相場の上下に一喜一憂せず、安定した運用が可能になります。
まさに「おまかせ投資」の第一歩です。
関連記事
投資信託と株はどう違う?メリット・デメリットや選び方を完全比較
4 .NISAのつみたて投資枠で投資信託を始めるのがおすすめな理由
初心者にNISAのつみたて投資枠をおすすめする最大の理由は、「少額から非課税でコツコツ投資ができる」点にあります。
対象となる投資信託は、金融庁が定めた基準をクリアした長期・分散・低コストの商品に限られているため、リスクを抑えた運用がしやすくなっています。
加えて、利益が出ても税金がかからないので、資産形成を効率的に進めることができます。
毎月自動で積み立てられる仕組みもあるため、投資の知識が少なくても無理なく継続できるのも大きな魅力です。
関連記事
NISAに年齢制限はある?18歳以上におすすめの理由や年齢別の運用方法
投資初心者におすすめのネット証券5選
投資を始めるなら、まずは自分に合った証券会社選びが重要です。特にネット証券は、スマホ一つで手軽に口座開設・運用ができ、手数料も比較的安いため初心者に最適です。
さらに、各社とも新NISAに対応した便利なサービスを提供しており、非課税で効率的な資産形成が可能になります。
ここでは、投資初心者におすすめのネット証券5社を厳選し、それぞれの特徴やNISAにおける強みをわかりやすく紹介します。
SBI証券

画像引用:SBI証券
SBI証券は、国内最大級の口座数を誇るネット証券で、初心者から上級者まで幅広く支持されています。
手数料の安さや取扱商品の豊富さに加え、NISA関連サービスが非常に充実している点も特徴です。
特につみたて投資枠では、三井住友カードと連携したクレカ積立が可能で、毎月の積立額に対してVポイントが貯まるのが魅力です。
さらに「SBI・V・S&P500」など人気の低コストファンドも揃っており、初心者でも安心して投資を始められます。
またSBI証券のスマホアプリの操作性は高く、学びながら実践できる環境が整っています。
SBI証券についてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
SBI証券で口座開設する手順を解説|メリットや利用者の口コミも紹介
\ニーズに合う商品が選びやすい/
楽天証券

楽天証券
画像引用:楽天証券
楽天証券は、楽天グループの強みを活かしたポイント連携が魅力のネット証券です。
楽天カードでのクレカ積立により、楽天ポイントが還元されるためNISAとの相性も抜群です。
楽天ポイントをそのまま投資に利用できる仕組みもあり、初心者でも気軽に資産運用をスタートできます。
また、スマホアプリ「iSPEED」は直感的な操作で使いやすく、投資情報やチャートも豊富です。
楽天証券についてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
楽天証券でのNISAの始め方!おすすめ銘柄や他社からの変更方法
\楽天ポイントでNISAが可能/
マネックス証券

画像引用:マネックス証券
マネックス証券は、独自の投資情報やツールが充実している点が魅力のネット証券です。
特に米国株に強みを持ち、外国株でNISAを活用したい人にも向いています。
NISA口座では、マネックスカードによるクレカ積立が可能で、1.1%の高還元率でマネックスポイントを貯められるのが特徴です。
投資信託のラインナップも豊富で、長期・低コストの商品が揃っており、NISAにも最適です。
また「銘柄スカウター」などの情報分析ツールも無料で使えるため、初心者でも本格的な投資分析に挑戦できます。
マネックス証券についてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
マネックス証券のメリットとは?ドコモとの提携によるメリットも解説
\クレカ積立の還元率が1.1%!/
三菱UFJeスマート証券(旧:auカブコム証券)

画像引用:三菱UFJ eスマート証券
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)は、三菱UFJフィナンシャル・グループの一員として、信頼性の高いサービスを提供するネット証券です。
NISAでは、au PAYカードによるクレカ積立が利用でき、最大1%のPontaポイントが還元される点が魅力です。
また、スマホに最適化されたシンプルな操作画面や、初心者向けの解説コンテンツも充実しており、投資をこれから始める方でも迷わず使える設計になっています。
三菱グループの安心感と、手軽さを兼ね備えたサービス内容が初心者にも好評です。
三菱UFJ eスマート証券についてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)で口座開設してNISAを始めるなら今!メリットやおすすめ銘柄を解説します
\MUFGグループの信頼性と使いやすさが魅力/
松井証券

松井証券
画像引用:松井証券
松井証券は、1998年に日本初の本格的なインターネット取引を開始した老舗のネット証券会社です。
特に、1日の約定代金が50万円以下の場合、売買手数料が無料というシンプルな手数料体系が魅力です。
松井証券は、豊富な取引ツールや投資情報を提供しており、特に無料の「相談窓口」が充実しています。
これにより、初心者でも安心して取引を始めることができます。
また、IPO(新規公開株)の取り扱いも増えています。
さらに、松井証券は、投資信託の自社利益の上限を0.3%に抑えるなど、顧客の利便性を重視したサービスを展開しています。
これらの特徴から、松井証券は多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
松井証券についてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
松井証券のメリットとデメリットは?松井証券が向いている人まで解説
\サポートが手厚い!/
投資の勉強法に関するよくある質問
投資を勉強する際、初心者が抱えやすい疑問とその回答をQ&A形式で紹介します。
Q1. そもそも投資って、なぜ勉強が必要なの?
投資はお金を増やす手段ですが、リスクも伴います。
勉強せずに始めると、大切な資金を思わぬ損失につなげる可能性もあります。
基本的な仕組みやリスクの捉え方を学んでおくことで、自分に合った投資スタイルを見つけられ、冷静な判断ができるようになります。
書籍やセミナー、YouTubeなど、自分に合った方法で基礎から学ぶのがおすすめです。
Q2. 書籍やネット、動画、どの勉強方法が一番いいの?
それぞれの勉強法にメリットがあります。
書籍は体系的に学べるのが魅力、WEBメディアは最新情報が得られ、YouTubeは視覚的にわかりやすく、セミナーは双方向の学びが可能です。
最初は自分が理解しやすい方法から始め、複数の手段を組み合わせると、より効果的に知識を身につけられます。
Q3. どのくらい勉強すれば投資を始めても大丈夫?
投資に「これだけ勉強すれば完璧」という基準はありませんが、まずは基礎的な知識(株や投資信託の仕組み、リスク分散、NISA制度など)を理解してから始めるのが理想です。
勉強と実践を並行して少額から始め、経験を積みながら知識を深めていくのが現実的でおすすめです。
Q4. 投資の情報って多すぎて、何を信じればいいの?
ネット上にはさまざまな投資情報がありますが、なかには信頼性に欠けるものもあります。
まずは金融機関や証券会社が発信する情報、実績のある専門家の著書や解説など、信頼性の高いメディアの内容を中心に学ぶのが安心です。
情報源を複数持ち、鵜呑みにせず比較・検証する姿勢が大切です。
Q5. 忙しくても投資の勉強は続けられる?
忙しい方でも、スキマ時間を使えば無理なく学べます。
YouTube動画や投資アプリ、短めの記事など、スマホで手軽に学べるコンテンツが豊富にあります。
毎日少しずつでも触れることで、自然と知識が身につきます。焦らず自分のペースで続けることが、長く投資と付き合うコツです。