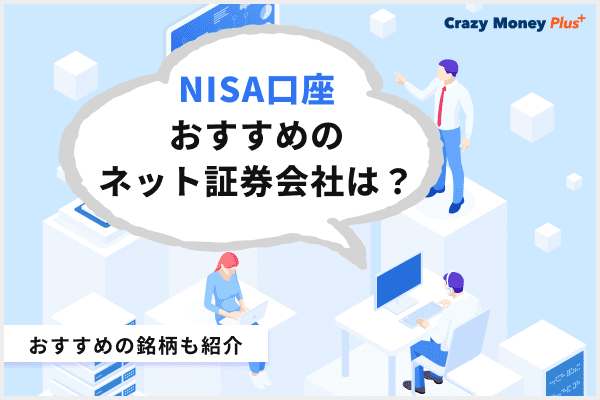■NISA口座おすすめのネット証券会社早見表
| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式、投資信託買付手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 投資信託銘柄数 | 2,652 | 2,604 | 1,407 | 1,708 |
| つみたて投資枠取扱銘柄数 | 205 | 194 | 177 | 197 |
| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 積立頻度 | 毎日・毎週・毎月 | 毎日・毎月 (※投資枠のみ毎日積立対応) |
毎日・毎月 | 毎日・毎月 |
| 対応ポイント | Vポイント Tポイント Pintaポイント dポイント JALマイレージ |
楽天ポイント | マネックスポイント | 松井証券ポイント |
SBI証券
SBI証券は国内で初めて総合証券口座数が1,000万口座を達成したネット証券会社の大手です。
マルチポイント戦略で国内初の1,000万口座を達成
| 国内株式、投資信託買付手数料 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託銘柄数 | 2,652本 |
| つみたて投資枠取扱銘柄数 | 205本 |
| IPO(2022年実績) | 89社 |
| 外国株式 | 米国、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ロシア、ベトナム、インドネシア |
| ポイント | Vポイント Tポイント Pintaポイント dポイント JALマイレージ |
楽天証券
楽天証券は楽天カード決済で楽天ポイントが貯まるので、楽天経済圏ユーザーにおすすめの証券会社です。
口座開設者の6割は30代以下と若い年齢層から支持されている
| 国内株式、投資信託買付手数料 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託銘柄数 | 2,604本 |
| つみたて投資枠取扱銘柄数 | 194本 |
| IPO(2022年実績) | 65社 |
| 外国株式 | 米国、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア |
| ポイント | 楽天ポイント |
マネックス証券
米国株の取扱い銘柄数が5,000以上ありポイントで手数料をお得にできる
| 国内株式、投資信託買付手数料 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託銘柄数 | 1,407本 |
| つみたて投資枠取扱銘柄数 | 177本 |
| IPO(2022年実績) | 62社 |
| 外国株式 | 米国、中国 |
| ポイント | マネックスポイント |
松井証券
松井証券はサポート体制が充実しているネット証券会社です。第三者機関による問合せ窓口格付けで、最高評価の三つ星を12年連続で受賞しています。
専門家のサポートを受けながら投資を始められる
| 国内株式、投資信託買付手数料 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託銘柄数 | 1,708本 |
| つみたて投資枠取扱銘柄数 | 197本 |
| IPO(2022年実績) | 55社 |
| 外国株式 | 米国 |
| ポイント | 松井証券ポイント |
NISA口座におすすめの証券会社は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券です。
これから投資を始めようと考える人のなかには、NISA口座の開設を検討している人も多いのではないでしょうか。毎年一定の非課税投資枠を活用できるNISA口座であれば、将来の資産形成を効率的におこなうことが可能です。
この記事では、NISA口座におすすめの証券会社を詳しく解説するとともに、NISA口座におすすめの銘柄を紹介します。
NISA口座でおすすめの証券会社ランキング
1位:SBI証券

NISA口座を開設する証券会社に悩んでいるなら、まず候補に挙がるのがSBI証券です。
SBI証券の特徴は以下の通りです。
- 手数料が安い
- 取扱銘柄数が多い
- IPO実績が豊富
- 外国株の銘柄が充実
- 対応しているポイントが5種類から選べる
SBI証券は手数料が割安な点が魅力の証券会社です。NISA口座の場合、国内株式、投資信託の買付と売却がともに無料です。海外ETFも、買付手数料が無料に設定されています。
取扱銘柄数が多いため、成長投資枠でもつみたて投資枠においても、幅広い選択肢から自分に合った銘柄が見つけやすい点が特徴です。また、IPO(新規公開株・新規上場株式)の実績も豊富であるため、NISAでIPOに挑戦したい人にも適しています。
米国株の他に中国株なども扱っているので、外国株へ投資したい人にもおすすめです。
SBI証券は、Tポイント、Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALマイレージに対応しています。国内株式や投資信託といった商品を取引することでポイントが貯められる仕組みとなっており、貯めたポイントは100円から投資信託の買付に利用可能です。
投資初心者で証券会社選びに悩んでいる場合は、SBI証券を検討してみてください。
2位:楽天証券
楽天経済圏を利用している人には、楽天証券がおすすめです。楽天証券のメリットは以下の4点です。
- 日経新聞が読める
- 楽天ポイントを獲得、利用できる
- 投資信託の取扱い数が豊富
- 手数料が安い
楽天証券の魅力は、日本経済新聞の記事が無料で読める点にあります。日本経済新聞を紙面で購読すると月間5,500円(税込)かかるところ、楽天証券に口座があれば、朝刊、夕刊の記事が無料で閲覧可能です。
経済ニュースを知りたい、企業情報を詳しく知りたいという人には、非常に有益なサービスといえるでしょう。
また、投資取引によって楽天ポイントを獲得でき、貯めたポイントを投資に利用できる点も楽天証券ならではの特長です。楽天証券のNISAの場合、投信積立時だけでなく、投資信託の保有残高によってもポイントが貯まります。
楽天カードを利用したクレカ積立にも対応しているため、楽天カードを所持している人はクレカ積立とNISA口座を組み合わせてみるとよいでしょう。
楽天証券は、楽天経済圏を利用している人や、日経新聞で投資知識を身につけたい人におすすめの証券会社といえます。
3位:マネックス証券
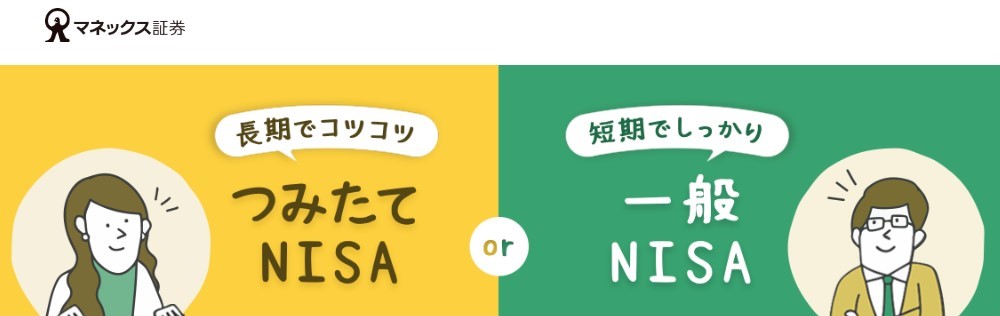
マネックス証券はポイント還元率にこだわりたい人におすすめの証券会社です。
- ポイント還元率が最大1.1%と高い
- 銘柄検索ツールや資産管理ツールが豊富
- IPOが完全平等抽選
マネックス証券では、マネックスポイントが貯まります。投資信託の保有残価に応じてポイントが還元されるだけでなく、マネックスカードを利用した投信積立決済で最大1.1%のポイント還元が可能です。
貯まったマネックスポイントは、株式取引時の手数料への充当や投資信託の購入に利用できます。また、以下の他社ポイントなどとの交換も可能です。
- dポイント
- Tポイント
- Pontaポイント
- nanacoポイント
- WAONポイント
- ANAマイレージ
- JALマイレージ
- Amazonギフトカード
マネックス証券はツールが豊富な点も魅力です。過去10期以上の長期業績をグラフ表示できる「銘柄スカウター」、チャートの形から個別銘柄を絞り込める「チャートフォリオ」といった検索ツールは、初心者にも使いやすくおすすめです。
マネックス証券はIPO実績が豊富なことに加えて、完全平等抽選となっています。運用資産額に関係なく誰にでも当選の可能性があることから、口座開設直後の人でもチャンスがあります。IPOにチャレンジしたい人におすすめの証券会社といえるでしょう。
\銘柄検索ツールが充実、IPOに興味があるならマネックス証券へ/
4位:松井証券
松井証券は、専門家のサポートを受けながら株式投資を始められるネット証券会社です。主な特徴は以下の通りです。
- サポート体制が手厚い
- 投資情報を多く発信
- 資産管理・アドバイスツールが豊富
- 信託報酬が還元される
松井証券の一番の特色は、取引相談窓口がある点です。株取引相談窓口は専門のスタッフが対応し、予約も可能。銘柄の探し方や売買のタイミングなど、アドバイスを受けながら投資にチャレンジできます。
なお、松井証券のサポートは、問合せ窓口格付けで最高評価の三つ星を12年連続で獲得しています。専門スタッフのサポートを受けながら投資を始めたい人に最適な証券会社といえるでしょう。
投資初心者におすすめなのが「松井FP」という資産管理ツールです。このツールを活用すれば、ファイナンシャルプランナーがおこなうライフプランシミュレーションをWeb上で実現できます。将来の資産形成がイメージしにくい人にとって、本ツールは大きな助けとなるでしょう。
ほかにも、松井証券では保有している投資信託の信託報酬を最大0.85%還元するサービスを提供しています。信託報酬とは、投資信託の運用期間中に投資家が払う手数料のことです。松井証券では徹底したコスト削減によって、投資家へ信託報酬を還元しています。対象となる投資信託は、2023年9月7日時点で1,261本あります。
\専門家のサポートあり!信託報酬還元に興味がある方は松井証券へ/
つみたて投資枠のおすすめ銘柄
Q「つみたて投資枠のおすすめ銘柄が知りたい。」
A「初心者におすすめなのはインデックスファンドです。高い運用成果を目指す場合は、アクティブファンドも検討してみるとよいでしょう。」
市場全体の値動き(インデックス)に連動するように運用されている投資信託のこと。代表的なインデックスとしては、日経平均株価、東証株価指数、ダウ平均株価、S&P500指数などが挙げられる。
特定の指数を上回るように運用されている投資信託のこと。運用会社やファンドマネージャーが、独自の調査や分析によって組み入れる銘柄を決める。運用コストが高い反面、高いリターンが期待できる。
ここでは、つみたて投資枠におすすめの銘柄を7つ紹介します。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
| ファンドの種類 | インデックスファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス |
| 信託報酬 | 0.1133%以内 |
| 投資地域(上位10カ国) | アメリカ、日本、イギリス、フランス、カナダ、スイス、ドイツ、ケイマン諸島、オーストラリア、台湾 |
| 投資対象 | 国内株式、先進国株式、新興国株式 |
| トータルリターン(3年) | 19.63% ※2023年8月31日時点 |
「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」は、日本を含む全世界の株式市場に投資している投資信託です。ベンチマークとしている「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」は、MSCI
Inc.が開発した株価指数で、先進国と新興国の大型および中型株で構成されています。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | アップル | 2 | マイクロソフト |
|---|---|---|---|
| 3 | アマゾン | 4 | エヌビディア |
| 5 | アルファベットA | 6 | テスラ |
| 7 | メタ・プラットフォームズ | 8 | アルファベットC |
| 9 | ユナイテッドヘルスグループ | 10 | JPモルガン |
アルファベットAとCは聞きなれない人もいるかもしれません。これはGoogleを運営している親会社です。Aは議決権が付与されており、Cにはありません。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)は、全世界の大型および中型株で構成されているため、投資先がすでに分散されています。インデックスファンドで運用したい人や、世界中の株式に分散投資したい人におすすめの投資信託です。
SBI・V・S&P500インデックスファンド
| ファンドの種類 | インデックスファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | S&P500株価指数 |
| 信託報酬 | 0.0938%程度 |
| 投資地域 | 米国 |
| 投資対象 | 米国株式 |
| トータルリターン(3年) | 22.74% ※2023年8月31日時点 |
SBI・V・S&P500インデックスファンドは、その名の通り米国のS&P500に連動するよう運用されています。S&P500とは、米国市場で時価総額の大きい主要500社で構成されている指数です。米国株式市場全体の80%を占めているため、米国市場全体の動きを概ね反映しています。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | アップル | 2 | マイクロソフト |
|---|---|---|---|
| 3 | アルファベット | 4 | アマゾン |
| 5 | エヌビディア | 6 | テスラ |
| 7 | メタ・プラットフォームズ | 8 | バークシャーハサウェイ |
| 9 | ユナイテッドヘルスグループ | 10 | JPモルガン |
いくつかの銘柄は、eMAXIS Slim全世界株式と被っていることがわかります。ただし、SBI・V・S&P500インデックスファンドではバークシャーハサウェイが組み入れられており、銘柄の構成比率も若干異なります。
米国市場に分散投資をしたい人や、米国株の個別銘柄を購入するのはハードルが高いと感じている人におすすめの投資信託です。
ニッセイ日経225インデックスファンド
| ファンドの種類 | インデックスファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | 日経平均株価 |
| 信託報酬 | 0.275% |
| 投資地域 | 日本 |
| 投資対象 | 日本株式 |
| トータルリターン(3年) | 13.94% ※2023年8月31日時点 |
ニッセイ日経225インデックスファンドは、日経平均株価に連動するよう運用されている投資信託です。日経平均株価は、東証プライム市場に上場している代表的な225銘柄をもとに算出される平均株価を意味します。日本の株式市場を把握する代表的な指標です。
ニッセイ日経225インデックスファンドの組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | ファーストリテイリング | 2 | 東京エレクトロン |
|---|---|---|---|
| 3 | ソフトバンクグループ | 4 | アドバンテスト |
| 5 | ダイキン工業 | 6 | KDDI |
| 7 | 信越化学工業 | 8 | ファナック |
| 9 | テルモ | 10 | TDK |
まさに日本を代表する銘柄が並んでいます。インデックスファンドの買付を検討している人で、日本株に投資したい人や外国株に抵抗があるという人におすすめです。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
| ファンドの種類 | インデックスファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | 東証株価指数(TOPIX) MSCIコクサイ・インデックス MSCIエマージング・マーケット・インデックス NOMURA-BPI総合 FTSE世界国債インデックス JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド 東証REIT指数 S&P先進国REITインデックス |
| 信託報酬 | 0.143%以内 |
| 投資地域 | 日本、先進国、新興国 |
| 投資対象 | 日本株、先進国株、新興国株、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート |
| トータルリターン(3年) | 10.21% ※2023年8月31日時点 |
ここまでは株式に投資をおこなう投資信託を紹介してきましたが、三菱UFJ国際eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)は、8つの資産に分散投資している投資信託です。
ベンチマークとする指数は、8種類。日本株、先進国株、新興国株、日本債券、先進国債券、新興国債券、日本リート、先進国リートです。「均等型」と名称にあるように、すべて「12.5%」の配分で組み入れられています。
リート(REIT)とは、不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて不動産投資をおこない、得た収入を投資者へ配当します。
組入上位10通貨は以下の通りです。
| 1 | 日本円 | 2 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| 3 | ユーロ | 4 | 香港ドル |
| 5 | 中国元 | 6 | ブラジルレアル |
| 7 | 台湾ドル | 8 | インドルピー |
| 9 | 英ポンド | 10 | メキシコペソ |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)は、投資先が株式だけでは不安な人、リスクを分散させたい人におすすめです。
資産を株式や債券、リートに配分している投資信託を「バランス型」と呼びます。4資産や6資産に分けているものもあるため、自分にあったバランス型を検討してみましょう。
フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060
| 投資対象 | フィデリティ・インデックス・US・ファンド フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケッツ・ファンド フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)ファンド フィデリティ・インデックス・UK・ファンド フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド バンガード・トータル・インターナショナル債券市場ETF バンガード・米国トータル債券市場ETF (※フィデリティ・インデックスの内容は交付運用報告書で確認可能) |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.36%〜0.38%程度 |
| 投資対象国 | 日本、先進国、新興国 |
| 投資商品 | 日本株、米国株、欧州株、新興国株、国内債券、海外債券など |
| トータルリターン(3年) | 18.59% ※2023年8月31日時点 |
フィデリティ・ターゲット・ デート・ファンド(ベーシック)2060は、償還日に向けて資産を配分していく投資信託です。
2023年時点では株式の比率が高いものの、2040年、2050年と残存期間が少なくなるにつれて債券の配分が多くなり、安定資産で運用することが予定されています。
主なインデックスの株式構成は以下の通りです。
| 組入上位5銘柄 | 割合 | |
|---|---|---|
| フィデリティ・インデックス・US・ファンド | 1.アップル 2.マイクロソフト 3.アマゾン 4.フィデリティ 5.アルファベットA |
52.4% |
| フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド | 1.トヨタ自動車 2.ソニー 3.キーエンス 4.三菱UFJフィナンシャルグループ 5.東京エレクトロン |
15.1% |
| フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケッツ・ファンド | 1.台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(台湾) 2.テンセント(中国) 3.サムスン(韓国) 4.アリババ(中国) 5.フィデリティ(米国) |
14.7% |
米国株に52.4%、日本株に15.1%、新興国株に14.7%の配分で投資をしています。この他に、欧州株や英国株にも投資されています。
2023年現在は残存期間が37年あるため、株式比率が多い状態です。残存期間が10年になると、世界債券や国内債券の比率が高まる予定です。現金化する日を決めておきたい人や、資産配分を自動で組み替えたい人におすすめの商品です。
コモンズ30ファンド
| ファンドの種類 | インデックスファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬 | 1.078% |
| 投資対象国 | 日本 |
| 投資対象 | 日本株 |
| トータルリターン(3年) | 16.04% ※2023年8月31日時点 |
コモンズ30は、今後の成長が見込まれる企業30銘柄に対して集中投資しているアクティブファンドです。日経平均の値動きを上回るリターンを出せるよう、独自の銘柄選定をおこなっています。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | 三菱商事 | 2 | 丸紅 |
|---|---|---|---|
| 3 | ディスコ | 4 | 味の素 |
| 5 | 信越化学工業 | 6 | デンソー |
| 7 | KADOKAWA | 8 | シスメックス |
| 9 | コマツ | 10 | 東京エレクトロン |
他にも「日立製作所 <6501> 」や「旭化成 <3407> 」といった銘柄が採用されています。
コモンズ30は、SBI証券の「SBIプレミアムチョイス」に選定されています。これは、長期で保有するのに適した運用実績と、投資の中身がわかりやすく、質の高い情報開示をしている銘柄をSBI証券がセレクトしたものです。
日本株に投資をしつつ、積極的にリターンを狙いたい人にコモンズ30はおすすめです。
フィデリティ・米国優良株・ファンド
| ファンドの種類 | アクティブファンド |
|---|---|
| ベンチマーク | S&P500 |
| 信託報酬 | 1.639% |
| 投資対象国 | 米国 |
| 投資対象 | 米国株 |
| トータルリターン(3年) | 21.80% ※2023年8月31日時点 |
フィデリティ米国優良株ファンドは、米国市場以上のリターンを目指した運用をしているアクティブファンドです。アクティブファンドであることから、組入れ銘柄は投資会社が独自に選定した銘柄が含まれています。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | マイクロソフト | 2 | アップル |
|---|---|---|---|
| 3 | エヌビディア | 4 | アマゾン |
| 5 | アルファベットC | 6 | JPモルガン |
| 7 | エクソンモービル | 8 | ウェルズ・ファーゴ |
| 9 | メタ・プラットフォームズ | 10 | トラベラーズ |
同じ米国株へ投資をおこなうものであっても、S&P500インデックスファンドとは構成銘柄が少し異なっていることがわかります。
米国株に投資をおこない、かつ市場の動き以上のリターンを狙いたい人におすすめの投資信託です。
つみたて投資枠は複数の銘柄を購入可能です。バランス型やインデックスファンドをメインに積立しながら、アクティブファンドをサブで運用してみてもよいでしょう。
そもそも成長投資枠とつみたて投資枠の違い
Q「成長投資枠とつみたて投資枠は何が違うの?どっちがおすすめ?」
A「成長投資枠とつみたて投資枠では、投資手法が異なります。初心者はつみたて投資枠を、個別銘柄に投資したい人は成長投資枠を選ぶとよいでしょう。」
成長投資枠とつみたて投資枠は、投資対象商品や投資上限額が異なります。2つの制度の違いを以下の表にまとめました。
■成長投資枠とつみたて投資枠の比較表
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 制度開始 | 2024年1月 | 2024年1月 |
| 非課税保有期間 | 恒久 | 恒久 |
| 年間非課税額 | 240万円 | 120万円 |
| 投資可能商品 | 上場株式、ETF、投資信託、REITなど | 金融庁が「長期、積立、分散」に適していると認定した一定の投資信託のみ |
| 買付方法 | 通常の買付と積立 | 積立投資のみ |
NISAとは
NISAとは、個人投資家向けの税制優遇制度のことです。通常、株式や投資信託を売却して利益が出ると、利益に対して20.315%の税金がかかります。しかし、NISA口座での利益に関しては税金がかかりません。
例えば、通常の課税口座において10万円で買った株が20万円に値上がりして、売却したとしましょう。利益は10万円ですが、そのうち20.315%は税金として引かれるため、手元に残る利益は7万9,6858円です。
一方、NISA口座の場合は利益に対して税金が課せられません。先ほどの例だと、10万円の利益がそのまま手元に残ります。
成長投資枠では年間240万円の非課税枠が設けられています。購入可能な金融商品は、株や投資信託などです。金融商品の選定や売買のタイミングを自分で決める必要があることから、投資の知識をある程度備えた人向けの制度といえるでしょう。
つみたて投資枠とは
長期積立や分散投資を支援する非課税制度です。成長投資枠と異なり、投資対象商品は「投資信託」に限られます。
年間非課税投資枠は120万円で、月々にすると「100,000円」が上限です。証券会社によっては100円からの積立も可能なので、少額投資に適した非課税口座といえるでしょう。
毎日500円の積み立てを20日間継続すれば「500円×20日間=1万円」になります。例えば、毎月1万円を年利3%で20年間運用した場合、最終積立金額は「328万3,020円(うち、運用収益88万3,020円)」です。少額を長期間積み立てることで将来の資産形成を図れるのが、つみたて投資枠の魅力です。
一度積み立てを設定すれば自動で買付されるため、放っておいても問題ありません。投資初心者や、毎日相場をチェックできない人にはつみたて投資枠がおすすめです。
つみたて投資枠の口座開設におすすめの証券会社の選び方
Q「つみたて投資枠用の証券会社はどうやって選べばいいの?」
A「取扱商品の多さ、貯まるポイント、積立頻度や最低積立金額で選ぶとよいでしょう。」
取扱商品の豊富さで選ぶ
つみたて投資枠で買付できる商品の豊富さで証券会社を選ぶのも、おすすめの方法の1つです。
つみたて投資枠で買付できる投資信託は、金融庁が「長期の積立分散投資に適している」と認めたものだけです。ただし、その銘柄数は200以上もあり、投資先や投資手法も異なります。
つみたて投資枠は金額内であれば、何本もの投資信託に分散して投資することも可能です。
「日本株と米国株、投資先を2つに分けたい」
「1つは米国株中心のインデックスファンドにして、もう1つは新興国株中心のアクティブファンドにしたい」
取扱商品が少ない証券会社の場合、欲しい投資信託や選びたい投資対象を取り扱っていない可能性があります。自由度の高い銘柄選びをしたいなら、つみたて投資枠の対象商品を豊富に取り扱っている証券会社がおすすめです。
貯まるポイントで選ぶ
貯まるポイントで証券会社を選ぶのも大切です。
最近では「ポイ活」などで、スマートフォンやクレジットカードを使い、特定のポイントを貯めている人も少なくありません。証券会社のなかには、成長投資枠やつみたて投資枠での取引でポイントが貯まる会社もあります。
例えば楽天証券では、楽天カードで投資信託を積立した時や、投資信託の保有残高に応じて楽天ポイントが貯まります。貯めた楽天ポイントは1ポイント=1円で、株式や投資信託の買付代金に使用可能です。楽天経済圏を利用している人にとって、魅力的なサービスといえるでしょう。
なお、証券会社によっては成長投資枠やつみたて投資枠ではポイントが付与されないこともあるため、ポイントサービスの内容は詳しくチェックしておきましょう。
積立頻度・最低積立金額で選ぶ
積立頻度や最低積立金額で選ぶ方法もあります。
つみたて投資枠の場合、毎月10万円が積立可能額です。しかし、初心者が月に何万円も投資に使うのはハードルが高いことかもしれません。
証券会社によっては100円から積立できるので、少額から始めたい人や余裕資金に不安がある人は少額投資から始めてみましょう。つみたて投資枠は途中で金額変更ができるため、100円で始めてみて、感覚を掴んで慣れてきたら増額することも可能です。
SBI証券や楽天証券は「毎日積立」が設定できるので、設定頻度から選ぶのもよいでしょう。月に1万円積み立てるという目標も、1日300円程度の積立なら実現しやすくなります。
少額から積立を始めるのも、投資初心者におすすめの方法です。
つみたて投資枠のおすすめ銘柄の選び方
Q「つみたて投資枠のおすすめ銘柄はどうやって選べばいいの?」
A「コスト、ファンドの種類、投資対象、トータルリターンの4つのポイントがあります。」
コストで選ぶ
コスト面で、つみたて投資枠の銘柄を選ぶのもおすすめです。
つみたて投資枠では、買付手数料や口座管理料はかかりません。政令によって、つみたて投資枠の対象商品の販売手数料はノーロード(無料)と定められています。
つみたて投資枠で気にすべきコストは「信託報酬」です。信託報酬とは、投資信託を保有している間にかかる費用のことです。投資信託は、個人の代わりに投資のプロが運用する仕組みであるため、運用や管理に対して一定の手数料が発生します。
一般的に、信託報酬は低いほど投資家に有利です。銘柄選びの際には、証券会社の商品紹介ページや対象商品の目論見書を通じて信託報酬額をチェックしてみましょう。
ファンドの種類で選ぶ
投資信託は、大きくインデックスファンドとアクティブファンドの2種類に分けられます。投資初心者の場合は、リスクの少ないインデックスファンドを選ぶのがおすすめです。
インデックスファンドとは、市場全体の値動き(インデックス)に連動するように運用されている投資信託のことです。例えば、日経平均株価がベンチマーク(運用指標)の投資信託の場合、日経平均株価が下がれば投資信託も値下がりし、上がれば投資信託も値上がりします。
保有期間間も、なぜ投資信託の価格が変動しているのか理解しやすいのがインデックスファンドの特徴です。投資初心者におすすめといえるでしょう。インデックスファンドは運用に手間がかからないため、一般的に信託報酬が低めに設定されています。
一方アクティブファンドは、特定の指数を上回るように運用されている投資信託のことです。インデックスファンドと異なり、運用会社やファンドマネージャーが独自の調査や分析をして優良な銘柄を探し出し、タイミングを計りながら運用しています。
そのため、インデックスファンドより投資判断が難しく、組み込まれている銘柄も会社独自のものになります。運用に手間がかかるため、信託報酬もインデックスファンドより高い傾向です。リスクを取りながらも大きなリターンを狙いたい人におすすめの投資信託といえるでしょう。
投資対象で選ぶ
投資対象で選ぶのも、つみたて投資枠では大切なことです。
以下に、つみたて投資枠で購入可能な商品タイプを整理しました。
■つみたて投資枠で購入可能な商品タイプ一覧
| 投資国 | 投資対象 | インデックス |
|---|---|---|
| 国内 | 東証プライムに上場する225銘柄 | 日経平均(日経225) |
| 東証プライムに上場している全銘柄 | TOPIX | |
| 全世界 | 全世界47カ国の大・中型株式 | MSCI ACWI |
| 全世界47カ国の大・中・小型株式 | FTSE Global All Cap | |
| 米国 | 米国市場に上場する大企業500銘柄 | S&P500 |
| 米国市場に上場するほぼ全ての銘柄 | CRSP U.S Total Market | |
| 先進国 | 日本を除く先進国22カ国の大・中型株 | MSCI コクサイ |
| 新興国 | 新興国24カ国の大・中型株 | MSCI Emerging Markets |
| バランスファンド | 4資産:日本、先進国の株式・債券 6資産:日本、先進国、新興国の株式・債券 8資産:日本、先進国の株式・債券・不動産+新興国の債券など |
|
投資先の選択肢が多いことがわかるのではないでしょうか。全世界の株式でも、大型、中型株だけに投資したいのか、小型株を含めたいのかで連動するインデックスが変わります。
また、日本を除く場合は「先進国」ですが、投資先に日本を含めたい場合は「全世界」を選ぶことになります。
成長投資枠やつみたて投資枠は、1つの銘柄しか買えないわけではありません。日本株と米国株、全世界株とバランスファンドというような分散も可能であるため、自分に合った銘柄を選びましょう。
トータルリターンで選ぶ
投資信託をトータルリターンで選ぶ方法もあります。トータルリターンの計算方法を確認していきましょう。
トータルリターンは、「現在の評価額」+「累計分配金受取額」+「解約金額」-「累計買付金額」で計算できます。購入してから現在までのトータル損益額をイメージするとわかりやすいでしょう。
例えば、SBI証券の投資信託パワーサーチで「トータルリターン」から検索をかけると、2023年8月時点で以下のような表示になりました。
右下に表示されている366という数字は、「3年間で20%以上のリターンがあったものが366銘柄ある」という意味です。このなかでつみたて投資枠に対応している銘柄は44銘柄、ファンドレーティングが星5のものは10銘柄ありました。
2023年8月28日時点でのトップ5を以下に紹介します。銘柄選びの参考にしてください。
| 銘柄名 | 1年のトータルリターン | 3年のトータルリターン | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 19.48% | 25.51% |
| 2 | 大和ーiFree S&P500インデックス | 19.33% | 25.32% |
| 3 | SSGAー米国株式インデックス・ファンド | 18.87% | 24.97% |
| 4 | ブラックロックiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 19.41% | 24.94% |
| 5 | 三井住友DSー大和住銀DC国内株式ファンド | 25.82% | 24.87% |
トータルリターンで選ぶ場合は、長期的に継続して積み立てた結果であることを忘れないでください。1年、3年のリターンとあるように、年単位で保有した結果であるため、短期的に大きなリターンが得られるわけではありません。
NISA口座のおすすめ銘柄〜投資信託編〜
Q「成長投資枠で投資信託を買いたいのだけど、おすすめは?」
A「インデックスファンド、バランスファンド、アクティブファンドの3種類から、自身のリスク許容度に合わせて選ぶのがよいでしょう。」
ファンドの種類とリスク許容度のポイントは以下の通りです。
| インデックスファンド | 特定の株価指数(インデックス)に連動する。コストが低く、値動きが把握しやすい。リスクを抑えて資産運用したい人向け。 |
|---|---|
| バランスファンド | 相場に合わせて自動で資産を組み替えてくれるタイプと、均等に分けているタイプがある。長期保有が前提。資産配分によって、リスクを積極的に取れる人向けのものと、リスクを抑えたい人向けに分かれる。 |
| アクティブファンド | 株式メインの運用。独自の調査や分析で運用するため、コストが高く、値動きも大きい傾向にある。リスクを取ってリターンを狙いたい人向け。 |
成長投資枠に対応し、株式メインで運用されている銘柄を紹介していきます。
三菱UFJ国際ー日経平均好配当利回り株ファンド
| 運用方針 | 日経平均採用銘柄のなかでも、予想配当利回りの高い上位30銘柄に投資 |
|---|---|
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬 | 0.693% |
| 投資対象国 | 日本 |
| 投資対象 | 日本株 |
| トータルリターン(3年) | 30.60% ※2023年8月31日時点 |
「日経平均好配当利回り株ファンド」は、日経平均225銘柄に採用されている企業のなかで、配当の高い企業上位30銘柄で構成される投資信託です。
組入上位の10銘柄と予想配当利回りは以下の通りです。
| 1 | 川崎汽船 | 2 | 三菱UFJフィナンシャルグループ |
|---|---|---|---|
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | みずほフィナンシャルグループ |
| 5 | 商船三井 | 6 | 日本製鐵 |
| 7 | ソフトバンク | 8 | 日本たばこ産業 |
| 9 | 武田薬品工業 | 10 | 日本郵政 |
この投資信託は年2回分配金を支払っています。2023年9月7日現在、基準価格が15,950円、直近の分配金が330円(税引前)です。仮に100万円投資した場合、「100万円÷1万5,950円=62.69口」を購入できます。分配金が前回と同じなら、「330円×62口=2万460円」が分配される計算です。
日本株へ投資をしたい人や、好配当の銘柄に投資したい人は「日経平均好配当利回り株ファンド」を検討してみましょう。
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
| 運用方針 | S&P500配当貴族指数に連動する投資成果を目指した運用 |
|---|---|
| ベンチマーク | S&P500配当貴族指数 |
| 信託報酬 | 0.55%以内 ※信託財産留保額:0.1% |
| 投資対象国 | 米国 |
| 投資対象 | 米国株 |
| トータルリターン(3年) | 23.03% ※2023年8月31日時点 |
S&P500配当貴族指数とは、S&P500指数の構成銘柄のうち、25年連続で増配し、時価総額が30億米ドル以上の企業で構成される株価指数です。
構成銘柄の上位3社と配当利回り(2022年12月期の実績値)を紹介します。
| 1 | ペンテア | 1.22% |
|---|---|---|
| 2 | スタンレー ブラック&デッカー | 3.45% |
| 3 | シャーウィン ウィリアムズ | 14.7% |
ただし、本ファンドは配当利回りの高い企業ではなく、増配している企業で構成されている点に注意しましょう。
配当利回りの高い企業で構成されている投資信託としては、「SBI・V・米国好配当株式インデックス・ファンド」があります。こちらは運用開始日が2021年6月29日と、まだ運用開始から日が浅い投資信託です。
米国株のなかでも連続増配の企業、配当利回りの高い企業、時価総額の大きい企業に絞って投資をしたい人は、「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族」を検討しましょう。
野村ー小型ブルーチップオープン
| 運用方針 | 日本の中小型株が主要投資先 |
|---|---|
| ベンチマーク | RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
| 信託報酬 | 1.672% ※信託財産留保額:0.5% |
| 投資対象国 | 日本 |
| 投資対象 | 日本の中小型株 |
| トータルリターン(3年) | 22.66% ※2023年8月31日時点 |
小型ブルーチップオープンは、日本の中小型株式で構成されている投資信託です。一般的に、時価総額と流動性の高い上位400銘柄のことを「中型株」、大型株と中型株以外の銘柄を「小型株」と分類します。
一般的に、注目の集まる大企業のほうが調査しやすく優先されるため、大型株より中小型株のほうが対象とされにくい傾向があります。そのため、中小型株のほうが将来高い成長が期待できる「ダイヤの原石」のような銘柄が眠っている可能性が期待できます。
小型ブルーチップオープンが採用している中小型株の上位10銘柄は、以下の通りです。
| 1 | アドバンテスト | 2 | 豊田通商 |
|---|---|---|---|
| 3 | ローム | 4 | 横浜ゴム |
| 5 | ディスコ | 6 | いすゞ自動車 |
| 7 | NOK | 8 | 東洋炭素 |
| 9 | 古河電気工業 | 10 | T&Dホールディングス |
熟成している大型株より、今後の成長に期待できる中小型株に投資をしたい人におすすめと言えるでしょう。
三井住友DSー高成長インド・中型株式ファンド
| 運用方針 | インドの中型株式をメインに投資を行う |
|---|---|
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬 | 2.0505% ※信託財産留保額:0.3% |
| 投資対象国 | インド |
| 投資対象 | インド株 |
| トータルリターン(3年) | 29.71% ※2023年8月31日時点 |
高成長インド・中型株式ファンドは、その名の通りインドの中型株式に投資をする投資信託です。安定した大企業ではなく中型株式を対象とし、なおかつ新興国であるインド市場であるため、リスクは高くなります。
加えて、新興国の株式に投資する場合は、コストが高くなる傾向にあります。新興国への投資は手段が少なく、どうしても運用コストが高くなるためです。
信託報酬が高いと敬遠してしまう人も多いでしょう。ただし、自分では投資できない対象へ代わりに投資してもらうことでもあるため、ある程度の手数料は仕方ないと割り切るのも1つの考えです。
高成長インド・中型株式ファンドは、価格の上下が激しいファンドです。設定来のトータルリターンを解説します。
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.69% | 13.27% | 29.71% | 13.50% | 443.81% |
保有期間によってトータルリターンは大きく異なります。運用開始以降のトータルリターンが大きい点は、アクティブファンドの魅力といえるでしょう。リスクを取って新興国へ投資をしたい人に、高成長インド・中型株式ファンドはおすすめです。
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 運用方針 | 世界のプレミアム・ブランド企業の株式を中心に投資を行う |
|---|---|
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬 | 1.65% |
| 投資対象国 | 全世界 |
| 投資対象 | 全世界の株 |
| トータルリターン(3年) | 22.62% ※2023年8月31日 |
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドは、世界中のプレミアムブランドに分散投資をしている投資信託です。プレミアムブランドとは、小売業のなかでも特別な地位にある企業を指します。本ファンドでは、最高級かつ一流のサービスを提供する企業に厳選している点が最大の特徴です。
特定の国や企業に集中せず、多様な国のプレミアムブランド企業の株式に投資しています。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 1 | マリオット・インターナショナル | 2 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン |
|---|---|---|---|
| 3 | フィナンシエール・リシュモン | 4 | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス |
| 5 | VISAアルファベットA | 6 | フェラーリ |
| 7 | ロレアル | 8 | インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ |
| 9 | アップル | 10 | ルルレモン・アスレティカ |
世界を代表するブランドで構成されていることがわかります。3位のフィナンシエールは、カルティエやピアジェ、万年筆のモンブランなどを手掛けている企業です。
国別の構成を見ると、上位から「米国、フランス、イタリア、スイス、英国」となっています。世界の一流ブランド、有名企業に投資をおこないたい人は、ぜひ検討してみてください。
NISA口座のおすすめ銘柄~個別株編~
Q「NISA口座でおすすめの個別株を教えてほしい。」
A「大型好配当や株主優待のある銘柄などで、おすすめの銘柄をピックアップしました。」
【おすすめ銘柄選定の際の参考条件】
銘柄を選定する際に使用した条件を記載しておきます。あくまで一例ですが、ご自身で銘柄検索する際にご活用ください。
| 選定条件 | |
|---|---|
| 大型好配当 | 時価総額2,000億円以上、予想配当利回り2%以上 |
| 輸出関連株 | ドル円レート感応度1.00以上、海外売上高比率50%以上 |
| 内需関連株 | 建設業/不動産業/電気・ガス/小売業、海外売上高比率50%以下 |
三菱UFJフィナンシャルグループ <8306>
三菱UFJフィナンシャルグループは、国内最大の民間金融グループです。三菱UFJ銀行の他にも、信託、証券、カード、リース業などを営んでいます。米州(北米、南米)やアジアなど、海外へも展開しています。
三菱UFJフィナンシャルグループは、2023年8月現在、最高益を更新し、連続増配している銘柄です。具体的に配当利回りを見てみましょう。
2023年には、1株あたり合計32円を配当しています。年間配当利回りは、2023年9月8日時点で2.63%です。
安定した大企業であれば保有中も安心感があり、配当金を受け取ることで保有継続のモチベーションも上がるのではないでしょうか。
トヨタ自動車 <7203>
トヨタ自動車は、世界販売台数で4年連続トップシェアを誇る自動車メーカーです。国内シェアも3割を超え、日野自動車やダイハツが傘下になっています。
一概には言えませんが、輸出企業であるトヨタ自動車の場合、円安が追い風となって売上高が高まる傾向があります。反対に円高になると輸出販売に伸び悩み、株価が下がる要因となることを覚えておきましょう。
また、三菱UFJフィナンシャルグループと同様に、2023年8月時点で増配している企業です。2022年度に1株あたり52円であった配当金を、2023年度には60円へと増配しています。
トヨタ自動車は世界的に有名な大企業であり、増配もしている点が魅力的な銘柄です。ぜひ銘柄選択の候補に検討してみてください。
オリックス <8591>
オリックスは、好配当でありながら株主優待がもらえる銘柄です。
オリックスはリース事業の他に、生命保険や不動産など多角的な事業を展開しています。海外進出もしており、環境エネルギー事業や空港運営などの事業も手掛けています。
経営状況も良好で、2024年3月期の連結純利益は過去最高を見込んでいる状況です。現在の配当利回りは3.0%です(2023年9月8日現在)。株式取引という観点からいうと、オリックスの魅力は株主優待にあります。
オリックスは毎年3月時点で100株以上を保有する株主を対象に、「ふるさと優待」というカタログギフトを贈呈しています。全国各地の取引先から厳選された商品を集めたカタログギフトとなっており、眺めるだけでも楽しめる優待サービスです。
残念ながら、2024年3月をもって株主優待制度の廃止が決定しています。しかし、2024年3月31日の時点で株主名簿に記載された100株以上保有の株主であれば、最後のふるさと優待が受けられます。気になる人はオリックスの株の購入を検討してみてください。
ニコン <7731>
ニコンは輸出関連株の1つです。海外売上高比率は約80%と高く、グローバル企業として確固たる地位を築いています。輸出先も米国、欧州、中国と幅広く、世界中にニコン製品のファンがいることが強みといえるでしょう。
輸出関連株は為替が円安になれば株価が上がり、反対に円高になると株価が下がる傾向にあります。円安に振れた時に、株価が上がるような銘柄を検討している人にはニコンがおすすめです。
また、ニコンは増配している銘柄でもあります。2022年度に40円であった配当金が、2023年度には45円へと増配されています。
三井不動産 <8801>
三井不動産は内需関連株の1つです。内需株は海外の売上高比率が高くないため、「日本の景気が良くなりそうだ」という場面に株価が上がる傾向にあります。
三井不動産は総合不動産の大手であり、ビルの賃貸が主力です。加えて、東京ドームシティやホテルなどの運営も手掛けています。東京ドームシティは大規模リニューアルしたところ、需要が回復。ビル賃貸も好調であったことから、2023年度3月期の連結決算で最高益を記録しました。
配当金も2022年度の55円から2023年度は62円と、増配しています。保有期間中に配当金が受け取れるので、じっくり長期で保有する楽しみがある銘柄といえるでしょう。
NISA口座のおすすめ銘柄の選び方
Q「NISA口座でおすすめの銘柄はどうやって選ぶの?」
A「配当利回りや株主優待、テーマから選ぶとよいでしょう。」
配当利回りで選ぶ
1つ目の方法は、配当利回りで選ぶ方法です。配当とは、株主に分配される現金配当のことです。保有している株数に応じて配当金が受け取れます。企業によって異なりますが、分配金は年2回支払う会社が多く見受けられます。
例として「ソフトバンク <9434> 」を見てみましょう。2023年度、ソフトバンクは3月と9月に43円ずつ計86円の配当金を分配しています。なお、ソフトバンクの株価は1,710円(2023年9月8日時点)です。
これらの情報にもとづいて計算してみると、「86円÷1,710円×100%=5.02%」配当利回りということがわかります。ソフトバンクは100株単位の銘柄であることから、17万1,000円ほどで株を購入し、1年間で8,600円の配当金が受け取れるイメージです。
通常の配当金に対しては、20.315%の課税が発生します。しかし、NISA口座で保有している株については、配当金も非課税です。なお、非課税で分配金を受け取るためには、配当金を銀行振り込みではなく、証券会社の取引口座で受け取る設定にしておく必要があります。これを「株式比例配分方式」と呼びます。
また、配当金を受け取るためには、「権利付最終日」までに株を購入しておく必要があることを覚えておきましょう。
株主優待で選ぶ
2つ目の選び方は、株主優待で銘柄を選ぶというものです。株主優待とは、企業が自社の株を購入してくれた株主に対し、サービスや商品を提供する制度を意味します。株主優待の内容は、自社の買い物優待券や商品など多岐に渡ります。
例えば、バイトルを運営する「ディップ <2379> 」では、株主にクオカードを贈呈しています。100株以上500株未満で500円相当、500株以上で1,000円相当のクオカードがもらえます。
なお、株主優待を受け取る場合は、配当金と同じく「権利付最終日」まで株を保有していなければなりません。
テーマで選ぶ
3つ目の選び方は、これから伸びそうな業種をテーマで選ぶという方法です。SBI証券やマネックス証券では、テーマから銘柄を選定できます。
「人工知能」「半導体」「インバウンド」など、これからの成長が期待できそうなテーマを選んで、有望な銘柄を探してみましょう。
例として、SBI証券の「テーマキラー!」で「生成AI」を見てみましょう。10銘柄がピックアップされたので、抜粋して紹介します。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 6701 | NEC | 東証プライム | 7,512 |
| 3993 | PKSHA Technology | 東証スタンダード | 2,550 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 東証グロース | 9,660 |
東証スタンダードやグロースに上場する、比較的新しい企業も含まれていることがわかります。テーマ投資を利用すると、普段の生活では出会いにくい企業を発見できるので、ぜひ活用してみてください。
NISA口座がおすすめされる4つのメリット
Q「NISA口座を開設するメリットは?」
A「利益が非課税になること、恒久で間非課税で保有できること、自分の好きなタイミングで売却できる点などが挙げられます。」
NISA口座を開設するメリットは4つあります。
- 利益が非課税になる
- 自分の好きなタイミングで売買できる
- 年間360万円の非課税枠が活用できる
- 株取引ができる
詳しく説明します。
利益が非課税となる
NISA口座で得た利益は非課税です。
通常、株式投資で利益を得ると、利益に対して20.315%(所得税15%、住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。
例えば、30万円で購入した株が50万円に値上がりしたと仮定しましょう。利益は20万円なので、これに20.315%の税金がかかります。4万630円が税金として差し引かれ、手元に残る利益は15万9,370円です。
なお、税金がかかるのは株の売却益だけでなく、配当金も同様です。
一方、NISA口座では利益に税金がかかりません。先ほどの例でいえば、20万円の利益がすべて手元に残ります。また、NISA口座で保有している銘柄の配当金についても非課税です。
このように、NISA口座を活用すれば、利益や配当金で税制上の優遇が受けられます。
好きなタイミングで売却できる
NISA口座で保有している金融商品は、好きなタイミングで売却可能です。
つみたて投資枠の場合、年間の非課税投資枠は120万円が上限です。長期積立を目的とした制度であることから、利益が大きくなるまで長期的な投資スタンスが求められます。同じく積立型のiDeCoは、資金の払い出しに制限があります。
一方、成長投資枠の場合は、自分の好きなタイミングで売却が可能です。「自分の判断で売買したい」という人に適した制度といえるでしょう。なお、非課税枠の範囲内で購入した商品は、いくら値上がりしても非課税期間内であれば税金はかかりません。
自分で銘柄を選び、好きなタイミングで売買したい人におすすめなのが成長投資枠です。
年間360万円の非課税枠が活用できる
成長投資枠の非課税投資枠は、年間240万円です。つみたて投資枠の年間上限が120万円です。
資金に余裕がある人にとって、つみたて投資枠の非課税枠は少し物足りないケースもあるでしょう。その点、成長投資枠は毎月20万円のペースで投資できるため、まとまった資金を投資に使いたい人にぴったりです。
また、つみたて投資枠であれば月々の積立額に制限がある一方で、成長投資枠にはありません。
株取引ができる
成長投資枠では、株式投資が可能です。
つみたて投資枠で購入できるのは、金融庁が認めた投資信託に限られます。一方、成長投資枠なら国内株や投資信託はもちろんのこと、外国株にも投資可能です。
外国株の例として、AppleやAmazonは日本でも認知度の高い企業です。また、決算が好調で最近注目を集めている大手半導体メーカーNVIDIAなど、米国株には多くの魅力的な銘柄があります。
成長投資枠を利用すれば、投資信託の他に、株やREITなど多岐にわたる金融商品を非課税で取引可能です。
国内外の株式投資に興味がある人は、成長投資枠の口座を開設しましょう。
保有している投資信託や株をNISA口座に移せない
通常の課税口座の金融商品は、NISA口座には移せません。
すでに証券会社に口座を持っており、株式や投資信託を保有している場合、利益や配当が非課税になるNISA口座へ金融商品を移したいと考える人もいるでしょう。しかし、通常の口座からNISA口座へは移管できないためご注意ください。
NISA制度による取引をする場合は、NISA口座を開設して新たに株式や投資信託を買付する必要があります。
損益通算の控除が適用されない
非課税口座であることから、NISA口座は損益通算や繰越控除の適用外です。
NISA口座内での取引は、利益に課税されません。損失も含め、税務上ないものとみなされます。そのため、通常口座や他の証券会社での取引と損益通算することはできません。
損益通算とは、その年の利益と損失を相殺することです。通常、株式や投資信託の売買で利益が出ると、税金が課されます。一方で、損失が出た場合は利益から差し引くことが可能です。損益通算してもマイナスになる場合は、確定申告すれば3年間繰越できます。
ただし、株式投資初心者でNISA口座しか開設しない、という人であれば、損益通算については深く考えなくても問題ありません。
NISA口座の作り方
Q「NISA口座はどうやって作るの?」
A「証券会社で開設します。4ステップで完了するので解説します。」
NISA口座は証券会社や銀行、郵便局などで開設できます。オンラインで開設できる証券会社であれば、最短2営業日でNISA口座が開設可能です。
NISA口座開設の大まかな流れは以下の通りです。
- Web上で必要事項を入力し、本人確認書類をWebでアップロード
- 証券会社側が書類や入力情報を確認
- 税務署の審査に通れば口座開設完了
税務署の審査では、申請者がすでにNISA口座を保有していないかを確認します。過去に他の金融機関でNISA口座を作ったものの、そのまま放置して忘れていたという場合は、NISA口座を開設できないので注意しましょう。
NISA口座は1人1口座です。複数の金融機関で開設することはできません。
NISA口座は銀行と証券会社どっちがおすすめ?
Q「NISA口座は銀行と証券会社、どっちで開設するのがおすすめですか?」
A「担当者に相談したい人は銀行へ、自分で決めたい人はネット証券会社がおすすめです。」
NISA口座を開設する場合、おすすめなのはネット証券会社での口座開設です。投資信託の取扱い本数も多く、最低積立金額も100円からと少額です。また、取引に応じてポイントが付与されるネット証券会社も多いため、総合的にみてお得といえます。
大手メガバンクにおけるNISAの基本情報は以下の通りです。
| 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | |
|---|---|---|---|
| 投資信託の取扱本数 | 592本 つみたて投資枠:12本 |
195本 つみたて投資枠:4本 |
195本 つみたて投資枠:4本 |
| 最低積立金 | 1,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 積立頻度 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
| ポイント | Pontaポイント | Vポイント | なし |
大手メガバンクの場合、投資信託の取扱い本数が少なく、積立頻度も毎月と限定的になっています。ただし、窓口で担当者に相談できるといったメリットもあります。
一方、ネット証券会社の松井証券も、コールセンターで専門スタッフへ相談しながら投資を進められる証券会社です。アドバイスを聞きながら投資を始めたいという人は、ぜひ口座開設を検討してみてください。
NISA口座に関するよくある質問
NISA口座に関してよく聞かれる質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
NISA口座は元本割れしますか?
NISA口座は元本を保証しているものではないため、元本割れすることもあります。
元本割れとは、購入した金融商品の価格が元の価格を下回ることです。一方、元本保証は元の投資額(元本)が運用期間中に減らないことを意味します。
株式や投資信託においては、銀行預金と異なり高い利益が見込める反面、元本割れのリスクがあります。ただし、信用取引などのようにレバレッジをかけて取引しない限り、元の投資額以上の損失は発生しません。例えば、10万円で購入した株式が大幅に下落して1万円になったとしても、9万円損しただけで、借金が発生しているわけではないということです。
できるだけ元本割れを防ぎたい場合は、インデックスファンドのようにリスクの低い投資信託を選んだり、業績の堅調な企業の株式を購入するよう心がけましょう。
NISA口座で買えない銘柄はありますか?
即日現金預託の株式、上場新株予約券、商品’外国投資法人債券)のETFは、NISA口座で購入できません。
NISA口座を作るならどこが良いか?
5種類のポイントに対応しているSBI証券がおすすめです。
SBI証券は投資信託の取扱い本数が多く、手数料も割安になっています。日本株、投資信託、外国株と幅広い商品を取引できるため、投資初心者にもおすすめです。
銘柄スクリーニングやテーマキラーなど、銘柄選定ツールも多く、買いたい銘柄をすぐに見つけられるでしょう。NISA口座の開設は最短2営業日で口座開設が完了するため、忙しい人にもおすすめです。
NISA口座の弱点はなんですか?
NISA口座の弱点は、損益通算ができないことや、損失の繰越控除ができない点です。NISA口座は非課税口座であるため、口座内で出た利益は「なかったこと」になります。それと同じく、損失についてもなかったことになるため、損益通算などはできません。
まとめ
本記事では、NISAの概要やおすすめの銘柄を紹介しました。
投資初心者であれば、積立投資枠を通じたインデックスファンドの積立がおすすめです。一方、すでに投資経験があり、何を買いたいか銘柄が決まっている人なら、成長投資枠で自由に売買したほうがよいでしょう。
投資信託を選ぶときは、自分のリスク許容度を知ることが大切です。また、積立は長期間、一定額を買い続けることで価格変動のリスクを抑えられる仕組みになっています。価格が下落した時も慌てず、長期的な資産形成を見据えて投資に取り組みましょう。